再論――ヘリコプターは
再論――ヘリコプターは
銀座通りにも着陸できる
―― Helicopter can land on the
Ginza Street ――

この主題は昨年11月2日、第7回日本航空医療学会で一般演題として発表したものである。そのときの抄録前刷り集に掲載された要旨は本頁にも掲載してあるが、以下の本文は昨年の要旨に大幅加筆して『日本航空医療学会雑誌』(2001年10月30日刊)に掲載された。
いま、わが国の構造改革に関する論議の中で道路公団のあり方が問われている。反対勢力はますます長大な道路建設を主張する。これによって立派な道路が無駄に八達し、誰も使わぬまま少数のカーマニアだけが気持ちよくぶっ飛ばすようになる。結果として事故が重なり、犠牲者が増えることになりかねない。
にもかかわらず、その建設を主張する国土交通省、完成した道路を管理する道路公団、そして交通の安全を守るべき警察は、何故かこぞって救急ヘリコプターの路上着陸に反対する。そこには自らの利権を守り、欲望を満たすために国民の犠牲を無視する政治家と官僚たちの、タリバンにも似た国家支配の本性がうかがえる。
ヘリコプターは最良の救急手段である。その特性を生かし、効果を挙げるためには患者のそばに着陸し、その場で救急治療に当たらなければならない。航空法はそのことを想定して、第81条の2に飛行場外での離着陸を禁止する条項(法第79条)を免除する特例を定めている。平成12年2月からは民間企業の運航するドクターヘリも特例が認められることとなった。
そのドクターヘリの導入と運用のあり方については、平成11年度の委員会で検討がなされた。席上最も大きな問題となったのは高速道路の交通事故に対するヘリコプター救急である。今その結論を振り返ると必ずしも十分なものではなく、その場にいた筆者としても内心忸怩たるものがある。
ヘリコプターはどうやら、一般的にはよほど脆弱で危なっかしいものと見られているらしい。たしかに航空における最大の課題は安全である。小さな錯誤や見過ごしが大きな事故につながることは否めない。けれども、安全上の問題を踏まえて、関係機関の総力を結集したシステムを組み上げるならば、大都市ロンドンで毎年千回余の救急出動をしながら10年以上にわたって無事故で飛んできたロイヤル・ロンドン・ホスピタルの救急ヘリコプターのような見事な成果を上げることもできる。われわれも安全運航と救命効果の双方を踏まえたヘリコプター救急システムの構築を急がねばならない。
はじめに――増加する交通事故
ヘリコプター救急は交通事故の犠牲者を減らすために始まった。ドイツでは1960年代後半、自動車の普及につれて急増したアウトバーンの死者を救うため、1970年からヘリコプターが路上の救急に使われるようになった。米国でも1972年、ベトナム戦争で経験したヘリコプター救助が「交通戦争」に向けられることになった。
フランスも同様で、運輸省が道路交通の安全を高めるため、「移動ICU」ともいうべきシステムを1965年に導入した。大型車の中に基礎的な蘇生装置と集中治療器具を取りつけ、医師が同乗して現場に駆けつけるという体制で、救急組織SMUR(le Services Mobiles d'Urgence et de Reanimation:救急蘇生移動サービス)に発展、全国統合の救急組織SAMU(Les Services d'Aide Medicale Urgente:救急医療支援サービス)の誕生につながった。SAMUがヘリコプターを使うようになったのは1983年である。
近年は交通安全施設の改良、自動車の安全性向上、交通安全教育の推進など、さまざまな要因によって交通事故が減少し、ヘリコプターの救急出動における交通事故の割合もやや減少傾向にある。しかし、その重要性は決して減ることはない。
とりわけ日本ではヘリコプター救急がはじまったばかりである。そのうえ交通事故件数は1970年のピークを境にいったんは減るかと見えたが、80年から再び増加に転じ、いまだに減る気配がない。幸い死者の数は1992年の11,451人をピークとして減少しはじめた。けれども2000年は9,066人となって、再び前年を上回った。しかも事故発生件数と死傷者の総数は過去10年以上にわたって増えつづけている。これらの状況は下図に見るとおりである。
このままでは新たな対策を講じない限り、交通事故は今後も増えつづけ、2005年の「道路交通事故死者数は9,000〜10,800人程度になる」というのが『平成13年版交通安全白書』の予測するところである。
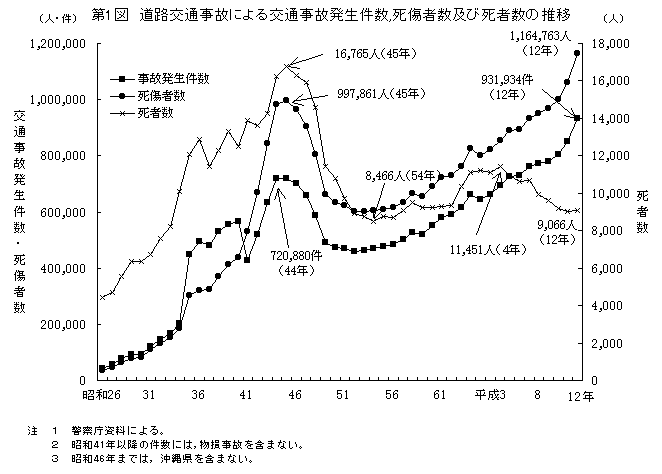
[出所]「平成13年版交通安全白書」(平成13年6月12日)
では「新たな対策」としては何が考えられるのか。白書は平成13年3月16日、政府が「中央交通安全対策会議を開催し、13年度から17年度の5年間において国及び地方公共団体が実施すべき交通安全施策の大綱を定めた第7次交通安全基本計画を作成した」として、下表1のような重点施策を掲げている。
|
この表の中から、今ここでは「(7)救助・救急体制の整備」に注目する。その具体的な内容は「救急救命士の養成・配置等の促進、ドクターカーの活用の推進を図るとともに、消防・防災ヘリコプターによる救急業務、ドクターヘリによる救命医療の実施、高速自動車国道のサービスエリア等における緊急離着陸用ヘリポートの整備の推進等を図ること」と説明されている。
ここで初めてヘリコプターが交通安全対策の手段として本格的に取り上げられることになったといってよいであろう。
ドクターヘリ委員会での論議
ヘリコプターが交通安全対策の手段となるについては、その背景に平成11年度の「ドクターヘリ調査検討委員会報告書」がある。委員会の内容と結論は今も首相官邸のホームページに報告書と議事録が公開されているから誰でも見ることができる。
その中から交通事故に関連する部分を見てゆくと、次のようになる。まず報告書の冒頭部分に「ドクターヘリ事業の目的の一つは、事故等の発生後、最短の時間で治療を開始することにある」と明記されている。
この「最短の時間で治療を開始する」ためには、ヘリコプターが事故現場に着陸し、医師を降ろさなければならない。交通事故ならば道路への着陸である。そこで報告書は「交通事故や大規模な事故の発生時に、ドクターヘリが道路で離着陸する場合には、警察官により、所要の交通規制等が行われる必要がある」と述べている。
とりわけ問題になるのが「高速道路における緊急離着陸」である。そこで「高速道路本線において緊急離着陸を行うためには交通を完全に遮断する必要があることから、まず、当面の取組みとして、離着陸が可能なSA(サービスエリア)、PA(パーキングエリア)を選定し、必要な条件整備を図った上、離着陸訓練を行う」となっている。
また「各地域(都道府県単位)において、離着陸が可能な本線部分、SA、PA等を調査し、関係機関と必要な調整を図った上、あらかじめ、緊急離着陸が可能な部分を確定しておくことも必要」としている。
実は、この結論に至るまでには、さまざまな議論があった。そのもようを公開された議事禄で見ると、たとえば建設省は「ドクターヘリによる救急業務についても、人命の救命率向上、あるいは後遺症発生の抑制等に関わるので、道路管理者としても可能な限り協力していくというのが基本姿勢」としながら、日本の道路は諸外国にくらべて幅員が広くないし、山岳地帯や横断が多く、トンネルや橋梁が多い。さらにカーブが多く、横断勾配がきついといった特殊性がある。
「そのほかに、高速道路上には、ガードレール等の防護柵あるいは照明灯、標識、樹木……遮音壁といった構造物も設置されているということで、対向車線への影響などから、救急ヘリコプターの離発着可能な箇所が非常に限られている」
したがってヘリコプターの離着陸ができるのは「サービスエリア、パーキングエリアの障害物がない箇所に限定されてしまう」。また片側3車線以上の広い道路でも、ヘリコプターが運転手に与える心理的影響やダウンウォッシュの影響を考慮すると、救急業務のために新たな被災者が出ないか危惧される、という説明を展開した。
戦闘機ですら発着できる
なんだか高速道路へのヘリコプターの着陸は不可能だし、やめるべきだと言わんばかりである。そこで委員の1人から「まず、だめですよということから話が始まる」。そして「最後に……二次災害が起こるから……だめだという結論」になっているのはおかしいという反論が出された。繰り返しになるが、これらは全て公開された議事録の引用である。
また、この委員会は「ドクターヘリをうまく飛べるようにしようという会なので、前向きに考えていただきたい」「ブラジルでもドイツでもアメリカでも、どこでもできていることが何故日本でできないんだ」「降りられるようにするにはどのように法を変えていけばいいのか」「運輸省でも規制をどういうふうに変えれば動くか提案していただき、それに対して建設省や警察庁が改善点を指摘するといった議論をしていかないと前に進まない」など、役所とそれ以外の委員との間で、考え方が対立するような場面も議事録から感じ取ることができよう。
結論は、委員会の報告書にあるように、高速道路のSAやPAにヘリコプターが着陸できるよう条件整備をするという一種の妥協が成立した。しかし、それとても役所側は「サービスエリア、パーキングエリアでも事故は突発的に生じるので、例えばお昼どきや渋滞時等々で利用者の車の排除にかかる時間も考慮しなければいけない」という条件をつけている。
報告書の「SA、PAを選定し、必要な条件整備を図」るというのは、具体的にどのようなことになるのかよく分らないが、SAやPAを拡張したり、着陸帯をつくったりするのかもしれない。無論そんな工事は無駄なことで、交通事故の場合はやはり路上に着陸する必要がある。
委員会でも韓国や北朝鮮では「ハイウェイ・ストリップ」が設けてあって、いざというときは戦闘機ですら道路から飛び立つという発言があったが、道路と滑走路は本質的には同じもので、救急ヘリコプターも障害物さえなければ、そこへ着陸するのが技術的に最も容易であろう。
第一、特殊な工事をしたSAやPAにしか降りられないとなれば、そこから事故現場まで偶然近ければよし、さもなければ何のためのヘリコプターか。たいていは救急車で運んだ方が早くなってしまうであろう。結果として、救われないのは患者の方である。
ドクターヘリの場外離着陸を解禁
だが救いもあった。「航空法施行規則」の改正である。運輸省は平成12年2月1日、委員会の結論がまとまるのを待たずに施行規則を改めた。上の討議があって半年も経たない短期間の改正である。これには、かねて航空の自由化をめざす大幅な法律改正が2月1日に予定されていたという別の要因もあったが、運輸省の反応はきわめて迅速果敢であったというべきだろう。
その後にまとめられたドクターヘリ報告書も「平成12年2月の航空法施行規則改正により、消防機関等からの依頼又は通報によるヘリコプター運航会社のドクターヘリの救急現場への緊急離着陸について、消防・防災ヘリコプターによる捜索・救助の任務に適応される運航と同様な取扱いとなったことは、ヘリコプター運航会社の活用による全国配備を進める上で大きな前進」と評価している。
改正の内容についてもう少し補足すると、航空機の飛行場外での離着陸を禁止する航空法第79条(離着陸の場所)は、周知のように第81条の2(捜索または救難のための特例)によって警察、消防など官公庁の航空機が「捜索又は救助のために行う航行については、適用しない」ことになっている。
この適用除外に加えて、今回の改正は航空法施行規則第176条に、これらの「機関の依頼又は通報により捜索又は救助を行う航空機」をつけ加え、救急業務に従事するヘリコプターが民間事業会社のものであっても、運輸大臣の事前の許可を取らずに飛行場外で離着陸をしてよいこととなった。
条文の詳細は表2のとおりだが、これでドクターヘリ運用の自由度は大きく拡大されたといってよいであろう。あとは警察や道路公団の交通規制がうまくできれば、事故現場の路上への離着陸も、むろん電線や街灯などの障害物のあるところは別として、患者のすぐそばに着陸し、その場で医師の応急処置ができることとなったのである。
|
患者のすぐそばに着陸
ここでロンドンに眼を転じてみたい。市内中心部に近いロイヤル・ロンドン・ホスピタルでは屋上にヘリポートを設け、1990年から救急ヘリコプターの運用をはじめた。その対象地域は東西約60km、南北約50kmの範囲で、日中だけではあるが年間千回を超える出動をしている。
使用機は最初の10年間がAS365Nドーファンだったが、現在は2000年10月以来MD902エクスプローラーを使っている。その活動の中で最も注目すべきは、必ず患者のそばに着陸するということである。
いうまでもなく、ロンドンは世界有数の大都会である。たしかに公園が多く緑は多いけれども、交通事故が公園の中や広場で起こることはまずない。多くは高速道路や雑踏する市街地だが、現場に近くて、安全かつ最適な場所を選定するのは決して容易ではない。しかも瀕死の重症患者が待っているわけだから、パイロットには咄嗟の判断が要求される。そうした困難を克服して、ヘリコプターの運航がはじまってから最初の6年間に4,800件以上の救急出動をしたが、その中で事故現場の近くに適当な場所がなくて着陸できなかったのは14件だけであった。
人と建物が密集する大都会で、たとえばネルソン提督の銅像をのせた高い塔が立つトラファルガー広場でも、ピカデリーサーカスの雑踏の中でも、ウェストミンスター寺院の前でも「ローター直径の2倍の広さがあれば着陸する」というのが、筆者がこの病院を訪ねたときの機長の言葉である。
この着陸地点と患者との距離は表3に示すとおりで、2年間に出動した2,207回のうち4割が患者から50m以内、6割が100m以内、4分の3が200m以内であった。
|
|
|
|
|
50m以内 |
|
|
|
50〜100m |
|
|
|
100〜200m |
|
|
|
200〜500m |
|
|
|
500m以遠 |
|
|
|
記録なし |
|
|
|
|
|
|
[出所]リチャード・アーラム編『トラウマケア』、1997年
では何故そのような実績が残せるのか。それは人命救助という一点に向かって、あらゆる機関の協力体制ができているからである。当然のことながら、如何にパイロットの腕がよくても、如何にヘリコプターの性能が良くても、如何に現場が広くても、如何に交通規制ができていても、如何に野次馬の整理ができても、如何に立派な通信機器があっても、それらがバラバラでは今や年間千回以上、毎日3回前後となった出動が大都市の中で安全かつ的確に繰り返され、10年以上にわたって無事故で飛びつづけることは難しい。
消防、警察、病院、ヘリコプター会社、航空局といった関係機関はもとより、現場周辺で交通規制を受ける一般車両や市民に至るまで、すべての人びとが協力する体制ができているのである。そうした協力体制は、その場限りの善意や好意といったものでは不充分である。法規やマニュアルに裏付けられた制度やシステムでなければならない。
ヘリコプター・システムの具体例
具体的には、たとえばロンドン消防局の傘下にあるロンドン・アンビュランス・サービスがロイヤル・ロンドン・ホスピタルの屋上ヘリポートへ救急ヘリコプターの出動要請を出す場合、同じ情報が同時に自動的にロンドン警視庁へも送り出され、そのまま現場所轄の警察へ届く仕組みができている。したがって事故現場の警察官は直ちにヘリコプターの飛来を知り、着陸地点を定めたり、交通規制をしたり、野次馬の整理をすることができる。
屋上ヘリポートでは出動要請が入ってくると同時にベルが鳴り、パイロット、医師、パラメディック、消防士がいっせいに行動を起こす。このときコンピューターからは現場の位置、飛行方位、事故の内容、さらには現場周辺の複数の病院をリストアップした出動指令書が打ち出される。運航管理者はそれをパイロットに渡すと同時に、航空保安事務所に電話を入れ、今から救急飛行が始まることを伝える。
折り返しコントロール・タワーからは機長に「MEDEVAC」という特別のコールサインが与えられ、あらゆる航空機に優先して飛行する許可が出る。これによりヘリコプターはMEDEVAC機として出動指令から2分以内に離陸する。それが接近してきたときは、旅客機もホールドして空域をあけなければならない。
ヘリコプターが現場上空に着くと、地上の警察官や救急車との間で無線通信がはじまる。パイロットは警察官と交信しながら、その助言を受けて着陸地点を見定め、安全を確認しつつ着陸する。

(樹木や街灯に囲まれた狭い場所に着陸したロンドンHEMSの救急ヘリコプター)
患者のところに駆けつけた医師が救急処置または初期治療をしている間、パイロットはヘリコプターのエンジンを停めて待機する。しかし医療スタッフの人手が足りないときは手伝いをしたり、病院との連絡に当たる。警察官も同様、周囲の警戒はもとより、「どうした、どうした」という野次馬の質問に答えたりする。
さらに応急処置を受けた患者は、必ずしもロイヤル・ロンドン・ホスピタルに搬送されるとは限らない。症状に応じて最適の病院へゆくことになる。このとき先刻の指令書にリストアップされた病院、診療科目、空きベッド、電話番号、所在地、飛行方位、距離などが役に立つ。
たとえば診療科目は、どこの病院で何ができるか。病院ごとに脳外科、心胸部外科、熱傷、小児科、形成外科、眼科、耳鼻咽喉科などの診療科目がチェックされ、さらにヘリポートの有無が記載されている。したがって、ヘリポートのないところへは、時間的な余裕を見て救急車で患者を送ることになる。いずれにせよ、関連情報のすべてが手もとにあり、いちいち問い合わせをする必要がなく、患者は直ちに最適の病院へ送りこまれる。
結 語
かくて、われわれは日本でも、内閣官房を事務局とするドクターヘリ調査検討委員会の結論を踏まえて、関係機関と関係者のすべてが人命救助の一点に向かって行動し、交通事故の犠牲者を一気に減らすシステムの構築を急ぐ必要がある。そのシステムが完成すれば、救急ヘリコプターは高速道路はもとより、必要に応じて銀座通りにも安全かつ容易に着陸することが可能となるであろう。
【参考文献】
1)『平成13年版交通安全白書』、平成13年6月12日
2)内閣官房内閣内政審議室編『ドクターヘリ調査検討委員会報告書』、平成12年6月
3)Richaed Earlam, TRAUMA CARE - HEMS London,1997
(西川渉、『日本航空医療学会雑誌』掲載、2001年10月30日刊)
