救難航空隊
救難航空隊
他者の生還はわれらが喜び
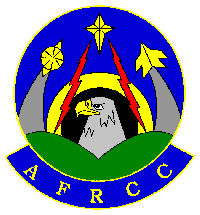
今のヘリコプター救急は、戦場における負傷兵の救助がきっかけになったといわれる。第2次世界大戦から朝鮮戦争やベトナム戦争を通じて、兵員の救助におけるヘリコプターの活用が増えるにつれて、死亡率は減少していった。
そのもようは、ベル社によれば下表のとおりである。
戦場における米軍負傷兵のヘリコプター救命効果
|
|
|
|
|
|
期 間 |
1939〜45年 |
1950〜53年 |
1965〜73年 |
|
死亡率 |
4.5% |
2.5% |
1.0% |
|
病院到着時間 |
約9時間 |
不詳 |
1時間余 |
|
ヘリコプター搬送人数 |
不詳 |
約2万人 |
94,000人以上 |
こうした死亡率の低下は、ヘリコプターの効果ばかりではないかもしれない。医薬品の改良や医療技術の進歩もあっただろう。けれども、ヘリコプターはどんなに危険な場所へも飛んで行き、敵地深いところから見方の兵士を救い出してくる。
とすれば、これを交通戦争に使ってはどうかというのが、とくにアメリカのヘリコプター救急の発端であった。以下の作文は25年ほど前に書いたものである。
「他者の生還はわれらが喜び」――アメリカ空軍の誇る救難航空隊は、隊員の誰もがこのモットーを心に刻んで、義務を果たしつつある。その存在は華々しい戦闘部隊の陰にかくれてはいるが、任務の内容は決して安易なものではない。むしろ戦闘部隊以上に、危険で困難な場面に立ち向かうことが多いのである。
北ベトナムからの生還
1972年6月1日――激しい戦いが続くベトナム・ダナン基地では、第40救難飛行隊が出動しようとしていた。北ベトナムの奥深く、ハノイ北方で撃墜されたF-4ファントム戦闘機の後席員、ロジャー・ロッシェル大尉の救出作戦である。
航空機の編成は、ピックアップのためのシコルスキーHH-53大型ヘリコプターが2機、捜索と地上砲火の制圧、さらにヘリコプターを誘導するマクダネルダグラスA-1地上攻撃機が2機、救出作戦全般を指揮し、ヘリコプターに空中給油を行なうロッキードHC-130キング司令機が1機、そしてこれらの護衛に当たるF-4およびF-105サンダーチーフ戦闘機が多数。
ロッシェル大尉は、これより先の5月8日、彼にとって407回目の出撃中、ミグ21のミサイルによって撃ち墜とされた。このとき乗機のファントムは、ミサイルが命中するとすぐ操縦不能に陥り、コクビット後方から火を発して炎がキャノピーを包み、外部が見えなくなると同時に機首が下がり始めた。
「ペイル・アウト!」
大尉はパイロットに呼びかけ、脱出用のハンドルをぐいと引いた。次の瞬間、大きな爆発音がして、眼をあけたときはパラシュートにつかまって空中をただよっていた。その直後、火に包まれたファントムが大地に突っこみ、大爆発を起こすのが見えた。
ロッシェル大尉は草木の生い茂った谷間に降下した。足が地面につくと素早くパラシュートを外し、しばらくその場にしゃがんで周囲の物音に耳をすませた。
それから23日間、彼は木の実や野イチゴを食べながら、1日ごとに自分の位置を移動した。この問25kmを歩き、体重は7kgも減って、極度に弱っていた。頭上には時おりアメリカの友軍機が見えたが、手もとの携帯無線機ではどうしても交信することができなかった。
しかし23日日、ついに2機の米軍機が大尉の呼びかけに応じてきた。こうして第40救難飛行隊が出動することになったのである。
その第1日日、6月1日にはミグ戦闘機の要撃が激しく、どうしても現場に近づくことができなかった。続いて翌日、救難部隊は再び北ベトナムをめざした。A-1を先頭とする編隊は絶え間ない地上砲火を浴びながら、北方への針路を維持し続けた。
やがて部隊は、ロッシェル大尉の上空に達した。まずA-1が大尉の位置を確認し、そこにHH-53が接近した。このとき付近の山あいから自動火器の銃声がひびき、弾丸がヘリコプターに集中した。が、ヘリコプターからもミニガン2門が応射する。
地上砲火が沈黙する間、救難隊員のひとりがホバリング中のヘリコプターからホイストで地上に降り、大尉を救出した。ホイストを引き上げる途中、まだ大尉が宙吊りになっている間にも、ヘリコプターは敵の砲火を逃れるために上昇を開始した。
地上からの攻撃は、部隊の帰り道でも休むことなく続いた。どの村からも、汽車やトラックの上からも、至るところから弾丸が飛んできた。この問、A-1サンディはヘリコプターの周囲につき、地上の敵と闘い続けた。
こうして無事、基地に戻ったロッシェル大尉は、ヒゲだらけの満面に喜びを表わし、ヘリコプターから降りてきた。「ジョリーグリーソとサンディはまことに素晴らしい。彼らは私を救い出すために、みごとな働きを見せた。私は、何といって感謝をLたらいいか分からない…‥」
救難航空の発祥
航空機、もしくは飛行手段によって、危難を逃れようとする発想は、遠くギリシャにも登場する。有名なダエダロスとイカロスの伝説である。クレタ島の迷宮から脱出しようとしたダエダロスは、自分と息子のイカロスのために鳥の羽根をろう付けして翼をつくり、うまく逃げ出すことができた。
もっとも、この話は脱出の成功に気を良くしたイカロスが太陽に近づきすぎて翼のろうが溶け、海中に墜落したことになっている。それでも、これは一種の救難または脱出飛行といえるだろう。
現実の救難飛行は1870年、フランスとプロシャが戦った普仏戦争に始まる。ビスマルク軍にパリが包囲されたとき、フランス軍が気球を使って160人の患者を脱出させたのである。
また第1次大戦中にも、再びフランスがドイツ軍に攻めこまれたとき、実用になったばかりの飛行機が負傷者の護送に使われた。
だが本格的な救難航空の歴史は、第2次大戦に始まる。欧州戦線では大陸反攻の攻撃に向かった爆撃機や戦闘機が地中海や英仏海峡で傷ついて、洋上に脱出する乗員が多かった。米・英連合軍はその救出のために、捜索用P-47、パトロールおよび救難用としてOA-10カタリナ飛行艇、救命ボート投下のためにB-17爆撃機を使用した。
このうちOA-10は、陸軍初の救難航空隊――1943年10月に編成された第1緊急救難飛行隊が最初から使用した機材で、第2次大戦中に多数の航空機乗組員を救出した実績をもっている。
一方、太平洋戦線で最初に行なわれた救難活動は、アメリカ第5航空軍第5戦闘軍団によるものであった。当時ニューギニアにあった同部隊は、1943年7月、出撃によって行方不明になった僚機を必ず捜索するという方針を打ち出した。
そして8月から4機のOA-10を加え、組織的な救難活動を開始した。以後わずか9か月間の1944年4月までに、455人の被撃墜者を救い出し、捜索救難活動の重要性を実証したのである。
また、これより先の1943年1月2日、第13航空軍のナサーン・トワイニング司令官がガダルカナルからB-17で飛び立ち、14人の幕僚と共に珊瑚海で行方を絶ったことがある。このときは空と海からの大規模な捜索が行なわれ、6日日になって海軍のPBY飛行艇が救命ボートで漂流中の一行を発見した。
このトワイニング司令官救出の成功は、アメリカ軍の中に救難活動の重要性に対する認識を確立させ、そこからいくつもの緊急救難飛行隊が編成されることになった。
そのひとつ、第4救難飛行隊はハワイに本拠を置き、日本の本土爆撃に向かう航空機の救難に当たった。B-29による空襲は1944年11月、サイパンなどのマリアナ群島に基地を置く第21爆撃兵団によって開始されたが、終戦までの9か月間、マリアナから出撃したB-29乗組員のうち1,310人が撃ち墜とされ、654人が救出された。
こうした中で最も大規模な救難態勢が敷かれたのは、8月6日と9日、原爆投下作戦が実施されたときである。この両日マリアナを飛び立ったB-29エノラゲイとボックスカーは、広島と長崎に原爆を落として、いずれも無事に帰投した。
しかし万一にそなえる救難態勢は.マリアナから日本沿岸まで、原爆機の飛行コースに沿って48磯のOA-10、8機のB-17、多数のB-29が空中待機を続け、海上には16隻の駆逐艦を含む152隻の艦船が配備についていた。そして日本の海岸に最も近い位置には、潜水艦が待ち受けたのである。
これは以後、重大な航空作戦には必ず並行して救難態勢をととのえておくことの前例となった。
ヘリコプターの登場
1950年6月25日未明、北朝鮮軍が38度線を突破して韓国に侵入、朝鮮戦争が始まった。
いらい3年間にわたる朝鮮戦争と救難航空との関係は、特にヘリコプターが登場して大きな役割を果たし、いっそう本格的、画期的な救難システムを確立したことにある。
朝鮮戦争の勃発から間もなく、アメリカ軍は世界各地に散らばっていたヘリコプターを集め、次々と戦場に投入した。新しいシコルスキーH-19も、その頃から量産に入り、1951年実戦配備についた。
が、ヘリコプターの数は、常に不足ぎみであった。というのは、朝鮮半島のような山岳地形では、ヘリコプターがまさに救難機として最適であることをみずから実証し、どこの部隊でも引っ張り凧だったからである。
第2次大戦中の救難活動は、必ずしも日常的なものではなかった。救難部隊ははるか後方に控えていて、第一線の戦闘行為とは無縁の存在だった。しかし朝鮮では、これが初めて日常活動となったのである。
アメリカ空軍第3救難飛行隊のヘリコプターは、戦闘の激化と死傷者の増加につれて、休む暇なく出動を要請された。負傷者を後送する場合、ジープでは道路が悪くて1時間もかかるようなところを、ヘリコプターは、初の実用機となったショルスキーH-5小型機でも、パイロットのほかに患者2人と看護兵1人を乗せて、5分で到達できる。
このことは、特に負傷者が頭や呼吸器に傷を受けている場合に重要で、いかに早く治療するかが生死の別れ目になる。第2次大戦中ならば、この種の負傷兵は前線から手術台に運ばれるまでに死んでしまうのがふつうだった。しかしヘリコプターは、その多くを救い、生還させることになったのである。
ヘリコプター機上では、さらに、負傷者を輸送しながら、応急手当や輸血が行なわれるようになった。1950年10月12日、第3救難飛行隊は、国連軍として活動していた英空軍のパイロットが、北朝鮮軍の背後に撃墜されたことを知らされる。直ちにH-5が出動したが、この救難飛行は朝鮮戦争における最も勇敢な行動のひとつとなった。
ヘリコプターは敵地の中を往復200kmも飛ばなければならなかった。現場に到着すると、そこは敵に包囲されていた。H-5はその中に着陸し、機長のマクダニエル中尉の援護射撃の中を、同乗のシユーメイト大尉が200mも走って、撃墜された英軍機に取りついた。その中から、彼は傷ついたパイロットを引き出し、肩にかついで再び砲火の中をヘリコプターに駆け戻った。
かつがれる英人パイロットは体重80kg以上、かつぐシユーメイトは60kgというハンディ。帰りの機上で、彼は負傷者に緊急輸血をしたが、これは戦場上空におけるヘリコプターの中での史上最初の輸血であろう。それからはほとんどの救難機が輸血装置を装備するようになった。
敵弾に撃たれた飛行機からパイロットが脱出するときは、通常、自分の位置と状況を僚機に知らせ、そこから戦闘本部に通報がゆき、救難機の出動が要請される。これらの救難機は戦闘機の援護のもとに現場へ飛び、無線機で地上と航空機の連絡が保たれる。
1951年1月26日、2人のジェット・パイロットが敵地深く飛んできたヘリコプターに救出されたことがある。この2人は2機の戦闘機で編隊を組み、敵前線のはるか北方で行動していたものだが、1機が地上砲火に撃たれ、パイロットは水田に降下した。もう1機はその上空にとどまり、救難機の到着を待ちながら、攻め寄せてくる敵兵に機銃掃射をくり返していたが、これも燃料が切れて脱出しなければならなくなった。
それから3時間後、ようやくヘリコプターがやってきた。この救出作業の最中にミグ戦闘機が現われ、F-86セイバーとの空中戦になった。この空中戦で、F-86は3機のミグを撃墜、地上の2人は激戦の末に救い出された。
こうした救難活動は、朝鮮戦争中に何百回となく行なわれた。救難飛行隊は全部で9,680人を救出、または後送したが、そのうち9,219人がヘリコプターによるものであった。また、このうち996人は敵地から救出され、そのうち846人がヘリコプターによるものであった。
このようにして朝鮮半島の砲声が止んだのは、1953年7月27日のことである。
進歩を続ける救難航空
朝鮮戦争から20年近く、ベトナム戦争におけるアメリカ空軍の航空救難態勢は、いっそう進歩して強大なものになっていた。
その中枢となる第3航空宇宙救難回収群は、サイゴンのタンソニュット基地に本部を置き、南ベトナムとタイの8か所に前進基地を設けていた。行動範囲はインドシナ半島4か国とシャム湾の広大な地域で、さらにトンキン湾と北ベトナム海岸線を、アメリカ海軍の救難部隊が担当していた。
使用機の第1はHC-130HおよびHC-130Pキング。ハーキュリーズ輸送機の航続性能を上げ、捜索、救難、回収用に改造して、救難作戦の調整をはかり、ヘリコプターヘの空中給油を行なうタンカーでもある。
ヘリコプターは西側最大のHH-53を主力とし、これにHH-3や近距離用のカマンHH-43が加わる。
航空救難回収群の最も大きな強みは、作戦の実施に当たって、空軍はもとより、海軍や陸軍からも航空機や兵員を自由に引き抜いて使えるという点にあった。
したがって、その救難行動はHC-130の指示に応じて、少なくとも2機のA-1と2機のHH-53がチームを組んで行なうのが普通だが、敵の火力が手に負えないときは、ファントムを始めとする空・海軍の戦闘機やA-7、A-37などの地上攻撃機、陸軍の武装ヘリコプターなどを呼び寄せることができた。
ひとつの救難作業に、数十機の戦闘機や攻撃機が参加することは決して異例ではなく、激しい地上砲火を処理するために100機以上の支援機が集まってきたこともある。ときには、この支援戦力が敵戦闘機との間で、最新鋭機同士の空中戦を演ずることもあった。
こうして地上砲火が制圧され、敵機が付近にいないことが確認されると、HH-53救難ヘリコプターが現場に接近する。これらのヘリコプターは7.62mmのミニガン3門という武装をしているが、もちろんもA-1も援護のために空中で待機する。
2機ひと組のHH-53による救難作業は、1機が低く下がって実際の救出に当たり、もう1機が後方高く飛んで見守るというのが標準的な方式である。これは、救出作業のために空中で停止するヘリコプタが、地上砲火によって撃墜された場合にそなえるためで、万一の場合は上空の僚機が次の救難機になるのである。
こうしたベトナム戦での救難作業は、ほとんどジャングルの上で行なわれた。撃墜された航空機や乗員は、生い茂った樹木の間にかくれてしまうが、彼らは無線機で救難横と交信し、最後に発煙信号によって自分の位置を知らせる。
ヘリコプターは、この信号を目標に低く下がり、密林の中に重い金属製の矢じりのような形をした「ペネトレーター」と呼ばれる救難器具を吊り降す。この中には3人分のシートがたたみこまれ、ホイストの長さは最大75m。地上の遭難者は、このシートに体をあずけて機上に引き上げられるのだが、怪我のために自分でシートにのれない者があるときは、救難隊員が地上に降りてゆくこともしばしばであった。
救難作業は夜間に行なわれることもある。そのためには、暗闇の中で遭難者の位置を知らなければならないから、ヘリコプターに薄明用テレビや赤外線探知器などの特殊装備がつけれる。
また最近は、遭難者の位置割り出しに人工衛星を利用する方法も開発された。
こうして第2次大戦から朝鮮戦争、ベトナム戦争を経たアメリカ空軍の航空救難技術は、使用機材を含めて著しく進歩した。
だが、そのすぐれた活動を支えるのは、「わが任務は他者の生還にあり」という不動の信念を高く掲げる救難隊員の1人ひとりであろう。隊員たちは極めて困難な状況の中で、ときには敵の手中にとびこんで、みずからの義務と名誉と国家への忠誠を一身に背負って任務を遂行してゆくのである。
その犠牲的、献身的人道主義は、戦時ばかりでなく、平時にあっても災害や海難に遭遇した一般市民の救済に向けられる。救助された遭難者や家族からの感謝の手紙は、今もひきも切らない。
アメリカ空軍の航空宇宙救難回収部隊が救助した遭難者の数は、1976年だけで1,352人(民間人850人以上を含む)を数え、1976年末までの30年間に総計17,493人に達している。
(西川渉、『航空ジャーナル』別冊、1977年9月)
