<ドクターヘリの安全>
パイロットから議会への提言
2009年4月17日米ヘリコプター事業用操縦士協会 PHPAは事業用の資格を持つヘリコプター・パイロット4,000人以上の会員から成り、そのうち1,500人余が救急飛行の実務にあたっている。
われわれはヘリコプター救急飛行(HEMS)の安全性向上策が決して容易いことではなく、費用もかかることを承知している。だからといって、放置しておくことはできない。PHPAとしてもかねてから、救急飛行の事故多発を憂慮してきた。
幸か不幸か、ここにきてNTSBの公聴会を初め、政府機関、業界、メディア、そして社会一般の人びとがHEMSの安全問題に関心をもつようになったことは喜ばしい。しかし、対話や論議ばかりで、実行がなければ、安全を回復することはできないことも知っていただきたい。
われわれパイロットとしては、事故原因の多くが「パイロット・エラー」という結論になっていることについて、大きな疑問を抱いている。これはコクピットの外側から見ただけの結論に過ぎないのではないだろうか。
ヘリコプター事故の詳細について、最近では国際ヘリコプター安全チーム(IHST)が世界的に努力を重ね、分析を進めている。しかし、まだ統計的な処理にもとづく分析にすぎない。
不幸にして、ヘリコプターには旅客機のような飛行記録装置(FDR)が搭載されていない。したがって事故原因の究明も隔靴掻痒の感を免れない。
対地衝突(CFIT)の原因にしても、なぜベテラン・パイロットが正常な航空機を操縦して、山や地面に突っこむのか。本当のところはよく分からぬまま、パイロット・エラーとして片付けられてしまう。
この場合パイロットはむしろ、事故の犯人ではなく犠牲者なのである。この問題について、パイロットは長年沈黙してきたが、事故の背景にあるのは適切な装備や訓練がなされてこなかったということだ。というのもヘリコプター業界の経済的な現実から見て、同じパイロットとはいえ定期航空のパイロットとは大きく異なるところである。
たしかに事故の罪をパイロットに着せれば、話は簡単であり、おそらく正しいかもしれない。たとえば小型の単発ヘリコプターが限度いっぱいの重量で夜間、暗視装置もなければ対地接近警報装置(TAWS)もなく、コパイロットやオートパイロットも乗せないまま、ギラギラした明かりで照射された交通事故の現場から漆黒の闇に向かって飛び立てば、電線にぶつかったり方向を見失ったりすることもあろう。しかし、だからといって、こんなことから生じた事故をパイロットの所為だというだけでは、次もまた同じことが起こるであろう。

われわれパイロットたちは、繰り返しになるが、救急飛行の安全確保は決して簡単かつ安価だと思っているわけではない。救急ヘリコプター業界が、その総意として、真に定期航空の安全水準にまでゆきたいと考えるならば、それと同じ方法を取るべきである。ヘリコプターの操縦は大型旅客機の操縦よりもやさしいとは限らない。むしろ複雑で、飛行条件も困難な状況にあることが多い。
定期航空業界は安全性を高めるために、過去数十年にわたって機体装備、訓練、支援体制など目に見える形で改善の努力をしてきた。ヘリコプターについても同じ努力が必要だが、そのためには莫大な費用と時間がかかるであろう。しかし、だからといって、立派な基準をつくるだけで、それに従うか従わないかは企業や個人の任意でよいというのでは、事態は変わらない。
新しい基準ができたことによって、パイロットがそれを気にする分だけ、新しい種類の事故が起こるかもしれないのだ。社会一般の人びとも、結局いかに緊急事態だからといって、そんな危ない手段で救急搬送をしてもらいたいとは思わないであろう。
アメリカのそんな状態にもかかわらず、隣国カナダでは救急飛行も定期航空と同程度の安全水準にある。すなわちカナダでは過去30年余り、同じような救急飛行を続けていながら、HEMSの死亡事故は一度も起こしていないのである。
提 言 以上により、われわれPHPAは次のように提言する。これは豊富な経験をもったプロ・パイロットたちが飛行のたびに、その責任を充分に自覚しつつ、安全に目的を完遂することを願ったものである。
1 航空機の信頼性 PHPAは目下、IHSTの調査研究の結果を待っており、その結果に応じて見解をまとめる予定である。
2 パイロットの信頼性 (1)訓練
パイロットの飛行時間と経験について、HEMS以外の分野におけるものは必ずしも、そのパイロットが救急飛行に適しているかどうかを測る目安とはならない。新たに雇用したパイロットを直ちに単独で機長としてHEMSの仕事につけるかどうか、それとも既存の経験あるパイロットのもとで副操縦士として同乗し仕事に慣熟させるかどうか、いずれにせよ相当量の訓練が事前に必要であることは疑いない。
米国では今のところパイロット2人乗務の救急飛行はおこなわれていない。そのためPHPAとしては新人パイロットを機長として仕事につけるには、社内訓練を充分におこなうことが重要と考える。この訓練の中には不整地への着陸、夜間飛行、悪天候下での飛行も含めるべきである。
さらに新人パイロットばかりでなく、救急飛行に経験のあるパイロットについても、緊急操作などの再訓練が必要である。再訓練は年に数回、そのパイロットが普段乗っている機種を使って、普段飛んでいる地域でおこなうのが望ましい。
ただし、こうした訓練を頻繁におこなうのは費用もかかるので、精度の高いシミュレーターが利用できれば、それを使うのもよいであろう。
(2)乗員の休養
乗員については、一般的な基準にしたがって休養を与えるようにする。(3)安全への動機づけ
運航者は組織内に安全管理システム(SMS:Safety Management System)を構築する必要がある。安全は単なる文書や口先(リップ・サービス)だけで保てるものではない。 とりわけ組織のトップにある人びとの姿勢や言動が重要である。これについては外部からの観察と規制がものをいう。たとえば保険会社は航空機の保険を引き受けるにあたって、その会社の安全への取り組みを充分に見きわめ、SMSもできていないような企業に対しては保険料を高くするなどの措置が必要であろう。
また安全に関する法規に違反しているような企業に対しては、当局もきびしい罰則を科すべきである。
3 基礎的支援システム (1)NVG
救急飛行は日常的に夜間でも飛んでいることから、夜間暗視装置(NVG:Night Vision Goggles)か、それに相当する装備を早急に取りつけ、パイロットの訓練をする必要がある。この取りつけ期限は向こう2年以内とし、それ以降は、こういうものを装備していないヘリコプターの夜間飛行を禁じ、昼間出動に限定する必要がある。(2)TAWS
対地接近警報装置(TAWS:Terrain Awareness and Warning System)は、現用機に関しては向こう3年以内に取りつけることとする。また新たに買い入れる機体については、最初から装備することとする。(3)電線衝突防止装置
現用機については全機、電線衝突防止装置を直ちに取りつける。また新たに買い入れる機体については、最初から装備することとする。(4)GPSマップ
GPSを利用したカラー・ムービング・マップは、今後1年半以内に救急ヘリコプターの全機に取りつける。(5)FDR
フライト・データ・レコーダー(FDR:Flight Data Recorder)はコクピット・ボイス・レコーダーを含めて、向こう4年以内に救急ヘリコプターの全機に取りつける。ただし旧式の小型機などは、正規のFDRが大きすぎたり重すぎたりするだろうから、そのときは最小限ビデオによって計器類をモニターし、記録する仕掛けを取りつける。このようにして得られたデータは事故予防のための再訓練に使用する。(6)計器飛行装備
救急ヘリコプターは計器飛行装備をする必要がある。その期限は5年以内とし、それ以降は計器飛行装備のない機体は昼間飛行に限定することとする。(7)パイロットの2人乗務
パイロットの2人乗務は、ヒューマン・エラーを防止するための最良の手段である。とりわけ夜間の不整地着陸などにあたっては必須の条件であろう。どうしても2人乗務ができないときは、自動操縦装置(オートパイロット)が必要である。ただしオートパイロットはコパイロットの代わりにならないことを承知しておかねばならない。(8)多発機
救急ヘリコプターは多発機を試用し、カテゴリーA、すなわち離着陸時および飛行中にエンジンの一つが止まっても安全な飛行が続けられるような機能をもつ機種とする。(9)気象情報
FAAと気象庁は全国各地に自動気象観測ステーションを設け、せまい地域の気象が正確に把握できるようなシステムを構築し、救急ヘリコプターのパイロットが飛行中も飛行前も、いつでも情報が取れるようにすべきである。これによって、気象の急変に遭遇して起こる救急ヘリコプターの事故は大幅に減らすことができるであろう。(10)ADS-B
FAAは2005年、衛星利用の航法システムADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) を整備するといって担当部局まで設置しながら、作業はいっこうに進まない。このシステムは特にせまい地域で低空を飛ぶヘリコプターにとっては極めて有効であり、他機との間隔を保ち、相互に通信することもできる。議会は、このシステム整備に必要な予算を十分に認めると共に、FAAによる整備作業の進捗状況を監視する。
(11)運航管理
救急出動に際して、特に気象条件の悪いときなど、パイロットには面と向かってではなくとも、無言の圧力がかかる。しかし、このことは飛行の安全にとって負の影響をもたらす。FAAは、もっと積極的に、救急飛行を認可された事業者の運航管理体制や出動決定の手順について、冷静な判断がなされるような指導をすべきである。(要約:西川 渉、「HEM-Net安全研究報告書」2010年3月刊所載)
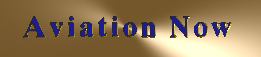
(表紙へ戻る)
