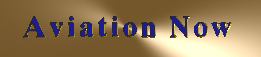<ファーンボロ2004>
エアバス対ボーイング(4)

ファーンボロ・ショーの会場で、エアバスとボーイングの受注競争はいつまでも続いた。
トルコ航空は、15機のボーイング737-800を発注する覚え書に署名したと発表した。正式の売買契約は8月末までに調印の予定という。
ただしトルコ航空は、その前日、エアバス機についても36機を発注すると発表したばかりで、報道陣を混乱させている。エアバスに対する発注の内訳は、A320が19機、A321が12機A330-200が5機。引渡しは2005年からはじまるという。
トルコにつづいて、インドの新しい格安エアライン、キングフィッシャー航空も4機のA320を発注した。ほかに8機の仮注文も出したという。

こうした受注競争と同時に、両社の貿易論争も激しい。ボーイング社に言わせれば、エアバス社は欧州各国政府の支援や補助金を受けているので、競争上不公正ではないか。WTO(世界貿易機構)に提訴するぞという脅かしである。
しかしエアバス社の方も、ボーイングは軍用機の開発研究で多額の資金を米政府から受けている。提訴などすれば、自ら墓穴を掘るようなものという。それに7E7の開発資金は多額の部分を日本が負担しているようだが、その中には日本政府の補助金も含まれているではないかと、日本までが論争の引き合いになる始末。
私も、ここでエアバスの肩を持つつもりはないが、なぜアメリカの一民間企業の製品開発にわれわれの税金が使われるのか。恐らくは、国民の測り知れない国家戦略があるのだろうが、理解できないところである。
さて、ボーイング社はファーンボロ会場で、向こう20年間の民間航空需要に関する予測を発表した。それによると乗客数は毎年平均5.2%ずつ伸びてゆく。これに応ずべきジェット旅客機の数は今の2倍ほど必要になる。そのためには今後20年間に25,000機、金額にして2兆ドル相当の機材が生産される。内訳は下表のようになるだろうと予測している。
|
|
|
|
|
リージョナル・ジェット |
|
|
|
単通路旅客機 |
|
|
|
中型双通路旅客機 |
|
|
|
747以上の大型旅客機 |
|
|
|
|
|
|
上表25,000機のうち現用機の引退に伴う代替機は6,400機。純増は18,600機で、20年後の全世界のジェット旅客機は35,000機になるという。つまり2倍以上の機数増だが、これは格安エアラインの伸長などによって、大型機よりも小型機の伸びが大きいためという。
加えてボーイング社は、今後の旅客需要の増加に対して、中型機による直行便の運航と便数の増加によって応じてゆくことになるという基本的な見解をもっている。したがって747以上の大型機はさほど増えない。つまりA380ではなくて、7E7のような機材が中心になる。これによって路線が増え、便数が増えれば、旅客は好きなときに好きな場所へ行くことができる。その柔軟性が求められているというのである。
対するエアバス社は、大型機が増加すると見ている。旅客の伸びは5%程度と変わらないが、それに対応する機材が中・小型機だけでは空港や空域の混雑ばかりを招いて、運航そのものが難しくなる。当然、大型機の導入が必要というので、A380が登場した。
そこで、このような両社の需要予測を比較してみよう。ただし双方の条件は必ずしも同じではない。たとえばエアバス社の予測は2002〜2022年の20年間で、リージョナル・ジェットは含まれないなどの違いがある。やむを得ず、やや乱暴だが、ボーイングの上の予測表からリージョナル・ジェットを除いて、エアバス社の予測を並べて見ると下表の通りとなる。
|
|
|
|
|
単通路旅客機 |
|
|
|
中型双通路旅客機 |
|
|
|
747以上の大型旅客機 |
|
|
|
|
|
|
この表に示されるように、エアバス社の見方は、中型機については余りボーイングと変わらないが、大型機はほぼ2倍で、その分だけ小型機が少ない。結果として全体の機数もボーイングより2割ほど少なくなっている。
こうした見方のどちらが正しいか。両社の論争は、20年たたなければ勝負がつかないわけで、まだまだ続くにちがいない。

(西川 渉、2004.7.26)