

ティルトローター機の実用化がせまってきた。
米国ではベル社とボーイング社が共同開発を進めてきた軍用型V-22オスプレイが史上初のティルトローター機として量産に入り、来年から引渡しがはじまる。また民間型ティルトローター機609も、ベル社単独の開発にはなったものの、すでに63機の注文を集め、順調に開発作業が進んでいる。これも来年には初飛行し、2001年――文字通り21世紀初頭には実用化される見通しである。
ここでは、そうしたティルトローター機の開発経緯を整理しながら、モデル609の内容を見てゆくことにしよう。
去る4月下旬、岐阜市内で3日間にわたって開催された国際会議、Heli Japan 98 で、ベル・ヘリコプター社の上級副社長、トロイ・ギャフィ氏の講演を聴く機会があった。「実用間近いロータークラフト技術」という演題で、ベル社が開発中のいくつかの新しい技術上の課題に関する解説であった。ここでは先ずその内容をたどってみよう。
ギャフィ副社長によると、ロータークラフト技術は50年前の実用化いらい3世代に分けられるという。第1世代はヘリコプターの基本的な技術が確立された時期で、たとえば主ローターのサイクリック・コントロール、尾部ローターによる反トルク機構、そして荷重疲労を抑える方法といったものが実現した。
第2世代の技術はターボシャフト・エンジンの実用化、高強度の金属材料や複合材の出現、あるいは空力的な理論の進歩で、現在の技術にほかならない。今のヘリコプターは、これらの技術を採り入れて開発され製造されている。
そして、これから実現するのが第3世代のロータークラフト技術である。その中にはティルトローターとコスト削減技術が含まれる。つまり、これからは安くて高性能のヘリコプターが実現し、ティルトローター機も実用化されるというのである。
では、実用化がせまったティルトローター機の利点はどこにあるのか。いうまでもなく、ヘリコプターのように垂直に離着陸し、空中ではターボプロップ機のように飛ぶことができる。
先ず固定翼の両端にエンジンを垂直に立て、その先に取りつけたローターをヘリコプターのように水平に回して揚力と操縦性を発揮し、離陸する。第2段階はエンジンおよびローターを前方に傾けながら加速してゆく。速度が増すにつれて主翼が揚力を発揮するようになり、操縦力はローターから操縦翼面の方へ移ってゆく。
最後にエンジンが水平位置になると、ふつうのターボプロップ機として飛ぶようになる。揚力は主翼で支え、操縦も飛行機と同じ操縦翼面を動かしておこなう。
このような基本原理によって、ギャフィ氏によれば、ティルトローター機は、同程度のエンジン出力をもつヘリコプターにくらべて、ほぼ2倍の速度性能を発揮する。下図では離陸出力1,000shpのエンジン2基をもつヘリコプターの場合、最大速度は150ktくらいになる。理論的に有害抵抗がないものとすれば、170ktまで行けるが、現実にはむずかしい。
そのヘリコプターに対して、1,250shpのエンジン2基をそなえたティルトローター機は最大293ktの速度に達する。まさにヘリコプターの2倍である。
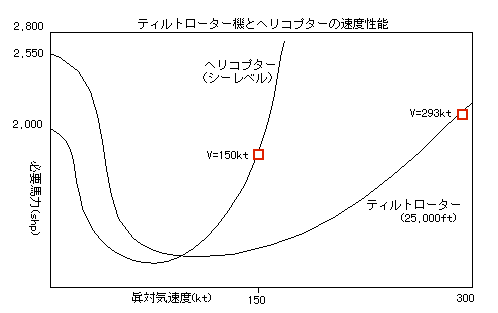
航続距離も長い。次図のように、約1トン半のペイロードを搭載した場合、ヘリコプターの航続距離は800km、ティルトローター機は1,350kmになるし、計器飛行条件のもとではヘリコプターが650km、ティルトローター機が1,100kmである。
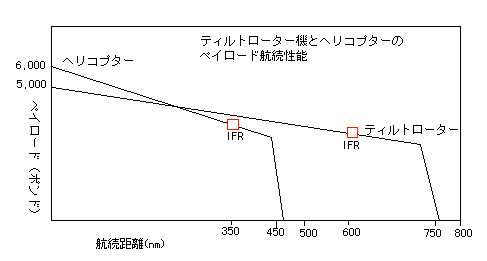
ティルトローター機は騒音も少ない。今のヘリコプターにくらべて、ホバリング中も低速飛行中も高速巡航中も、いずれもティルトローター機の方が静かである。
さらにティルトローター機は安全性が高い。ヘリコプターのような尾部ローターがなく、高度7,000m以上の高空を飛ぶので気象条件の影響を受けることも少なく、もちろん山にぶつかることもない。そしてヘリコプターのような振動がや荷重が少ないから、部品のいたみも少ない。いずれも安全性を高める要素である。
実際の飛行ぶりはどうなるか。次図に示すように、ヘリコプターのように垂直に離陸したのち、徐々にローターを前傾させて加速する。約1分で地上600ft、速度200ktに達し、出発地から3km近く離れるまでに遷移飛行を完了、ターボプロップ機としての飛行状態になる。そこから、さらに加速しながら高度を上げてゆき、15分後には80km余りを飛び、高度20,000ftに達する。そして速度275ktで巡航飛行に入るのである。
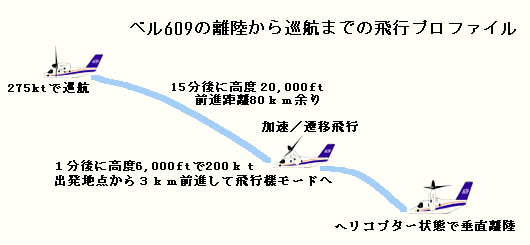
そうしたティルトローター機の実用化はいつになるのだろうか。ギャフィ氏によれば、軍用型V-22オスプレイは1999年5月から量産機の引渡しがはじまり、2001年には実戦配備につく予定。いっぽう民間型609も2000年4月に原型1号機が初飛行し、2001年12月には引渡しに入るという。
そうなると、いずれは欧州のメーカーが構想中のユーロファーやひょっとして日本からも、別のティルトローター機が出現する可能性も出てくるが、いまのところ具体的な動きは見られない。しばらくはアメリカ勢が独占的にティルトローター機を提供することになるだろうというのがギャフィ副社長の見解である。
さて、このようなティルトローター機の発端は半世紀近くさかのぼることができる。1950年、ロバート・リヒテンがティルトローター機を商用機として開発するための会社をつくった。同社のモデル1-Gは1954年に飛び、何度かホバリング飛行をしたが、ヘリコプター状態から飛行機への完全遷移飛行はできないままで終わった。
ここで問題となったのは機体の重量とエンジン出力である。通常のヘリコプターに対して、ティルトローター機は固定翼がつけ加わる上に、ローター・マストを前向きに傾けるという複雑な構造が必要になる。そのうえ機体には飛行状態によって垂直方向と水平方向の2種類の応力がかかるため、その分だけ強度を高めなければならず、ますます重量がかさむ。その重い機体を垂直に持ち上げるにはいっそう強力なエンジンが必要になる。
そんな問題をかかえながら、リヒテンは自分の会社をたたんでベル社に入り、XV-3実験機の設計に着手した。その試作が完成したのが1955年2月10日のことであった。
ベル・ヘリコプター社の工場の中でベールをぬいだXV-3は、固定翼の両端に3枚ブレードのローターをもち、エンジンはP&W R-985ピストン・エンジン(450馬力)1基がコクピット後方の胴体内部に取りつけられていた。そこから長く複雑なドライブシャフトを介して出力が伝えられ、二つのローターを駆動する仕組みである。またローターマストを前傾させるには各マストの根元に取りつけた電動モーターを使うようになったいた。
XV-3単発ティルトローター機の初飛行は1955年8月11日。コクピットは前後2座席のタンデム形式であった。機は地上6m付近でホバリングしながら、前後左右に移動したが、安定性に欠け、それ以上の飛行はできなかった。それから、さまざまな手直しがおこなわれ、1955年末ようやく本格的な試験飛行がはじまった。
XV-3は、その後も振動に悩まされた。ローターマストは6種類も試作され、固定翼には振動を抑えるための支柱が取りつけられた。それでも振動はおさまらず、こまかい試験と手直しと、さらには大がかりな風洞実験をやり直すなどして、ついに固定翼機への転換飛行に成功したのは1958年12月18日のことである。そのとき固定翼機としてのXV-3は高度1,200mを213km/hの速度で飛行した。
その後もXV-3は4年間にわたって試験飛行を繰り返した。その間、1959年4月16日には飛行機として巡航飛行をしながらローター回転数を4割減とするのに成功した。この回転数が通常の固定翼機状態では最良の効率を発揮するのである。また同年6月5日には、固定翼機として飛行しながらエンジンを切り、ヘリコプター状態に戻ってオートローテイションをするのにも成功した。これはエンジン故障の場合の緊急事態にそなえる実験である。
こうしてXV-3は1962年末までに250回以上の飛行をして、100回を越える完全遷移飛行に成功した。この間の飛行時間は450時間を越え、最大高度は3,600m、最大速度は291km/hであった。
ティルトローター機の可能性は、こうしたXV-3の実験飛行によって実証されたのである。
1968年、ベル社はXV-3の実験結果にもとづき、再び新しいティルトローター機の研究に乗り出した。この研究は1973年、まだトランスミッションのテスト運転中にNASAと陸軍の契約を受け、実機の製作をすることになった。契約金額は当時の金額にして5,000万ドルである。
この実験機はXV-15と名づけられ、2機が試作された。XV-3に対してXV-15が大きく異なる点は、前者が単発ピストン機であったのに対し、XV-15は双発タービン機になったことである。しかもXV-3はエンジンを胴体内部に搭載して、1基で2つのローターを駆動していたのに対し、XV-15はローターを直接取りつけたエンジンを主翼両端に置いた。これでXV-3のような複雑なトランスミッション系統は要らなくなった。
胴体は通常のアルミ構造で、総重量6,800kg。主要諸元は表1の通りだが、試作の目的はティルトローター機の空力特性、操縦系統、エンジンその他の問題点を探り、解明することであった。
実機は、組立て完成後もNASAのエームズ研究センターの大型風洞の中で慎重な試験が繰り返された。その風洞試験で見つかった問題点の一つは、ローターを前傾させて、ある角度になると主翼にぶつかった後流が多くの渦を生じ、それが胴体尾部に激しい振動を起こすという問題だった。そのためXV-15は尾部が再設計され、強化されて、後流の渦にも耐えられるようにした。
こうしてXV-15は1977年5月3日、ようやく1号機の初飛行に漕ぎ着けた。2号機が飛んだのは79年4月23日で、この2号機が同年7月24日初めての遷移飛行に成功した。飛行速度は1年後の80年夏に480km/hを越え、最終的には615km/hに達している。
こうした試験飛行中、XV-15は実際にエンジンの片方が停まったことがある。しかし、かねて用意の安全構造によって、不意の故障にも無事に対応することができた。左右のエンジンが長いクロスシャフトでつながっているために、一発停止の場合も残りの片発で両方のローターを駆動することができたからである。
また記録飛行では3,000mまでの上昇に4分24秒、6,000mまでの上昇に8分29秒という公式記録をつくっている。
1981年6月のパリ航空ショーでは、XV-15のデモ飛行がおこなわれた、これを見た多くの人が航空界に新しい時代のきたことを知った。ショーにきていた米国の政治家や政府高官たちも見事な飛行を目の当たりにして、ティルトローター機の将来に期待する賛同者が増えた。のちに国防省からJVX計画が持ち出されたときも、多くの政治家が違和感を示さなかった。このJVX――3軍統合の垂直離着陸機計画から、今のV-22オスプレイの開発がはじまったのである。
|
|
|
|
|
|
全 長 全 幅 全 高 エンジン 出 力 最大離陸重量 自 重 座席数 最大速度 巡航速度 運用高度限界 航続距離 |
13.3m 18.3m 4.5m PT6C-67A 1,850shp×2 7,265kg 4,763kg 1+9 510km/h 465km/h 7,620m 1,390km |
12.83m 17.42m 4.67m LTC1K-4K 1,550shp×2 6,804kg 4,341kg 2 615km/h 561km/h 8,840m 825km |
9.23m ―― 4.1m P&W R-985 450hp×1 2,177kg 1,633kg 2〜4 291km/h ―― 3,600m ―― |
JVXと呼ばれた新しい軍用ティルトローター機の開発のために、ベル社とボーイング社が共同開発チームをつくったのは1982年のことである。のちにV-22と名づけられた同機は米4軍のすべてが使うことを目的として、航続距離、速度、多用性、生還性、着艦能力、それに長距離の自力展開能力といった設計仕様が定められ、最も近代的な航空機として開発されることになった。
XV-15との違いは、機体構造部に複合材が使われ、操縦系統がフライ・バイ・ワイヤになったことである。もしも複合材を使わなければ、機体は重くなり過ぎて、ペイロードはきわめて小さなものになったに違いない。操縦系統も昔ながらの機械的な連接では、複雑で重いものになったであろう。この二つの新しい技術の採用によって、V-22は機体構造が簡単になり、重量が軽減され、また操縦性も向上したのである。
試験飛行がはじまったのは1989年3月19日。以来これまでに総計1,000回、1,200時間以上の試験飛行がおこなわれた。その結果、V-22は通常のヘリコプターにくらべて速度が2倍、航続距離が3〜5倍で、ペイロードも相当に大きいことを実証した。
しかし、ここに来るまで、同機の歩んだ道筋は決して平易なものではなかった。ひとつは、こともあろうに発注元の国防省で、リチャード・チェイニー長官がV-22の開発中止を数年にわたって主張したのである。国防省の予算要求からV-22計画を削ったものだが、その都度、議会側の主張によって、予算が復活するという奇妙な結果になった。
もうひとつは原型4号機の事故である。1992年7月20日、ポトマック川に墜落して、乗っていた7人が全員死亡した。調査の結果、引火性の油液――燃料か油圧液が漏れてエンジン・カウリングの中にたまっていて、着陸態勢に入るために、そのカウリングをヘリコプターのように立てたとき、油液がエンジン空気取入れ口から中に入って爆発的に火を発したことが原因であると判明した。その結果、エンジンばかりでなく、両エンジンをつなぐクロスシャフトまで破損し、飛行不能に至ったものである。もとより現在では、カウリングにドレーン口を開け、油液がたまらないようになっている。
V-22の開発は、この事故によってぐらついたが、幸いなことに事故の直後、1993年初めにクリントン政権が発足、新たに就任したウィリアム・ペリー国防長官がティルトローター機の支援者であった。むろん基本的には、事故の原因がはっきりして、ティルトローター原理そのものに起因するものではないことが判明したことで、V-22の開発計画も続けられることになった。
1997年2月からは、前量産型の試験飛行もはじまった。米海軍のパタクセントリバー基地でおこなわれている。
国防省は、これまでに16機のV-22を発注している。最終的な調達計画は海兵隊が425機、空軍が50機、海軍が48機で、量産1号機は1999年、まず海兵隊に引渡される。
V-22は米3軍が向こう25年間に約523機を調達する計画である。また米3軍のみならず、外国からも関心が寄せられている。
ティルトローター機がここまで現実味を帯びてくると、次は当然、民間機として利用できないかという期待が出てくる。特にアメリカ議会は、かねてティルトローター機の開発を党派を超えて熱心に推進してきた。かつての国防長官の反対もこれによって押し切られたものだが、その見方はティルトローター機がまず軍用機としてすぐれた能力を発揮できるということであり、その開発に成功したならば次は民間機としても利用価値が高いというものであった。
「ティルトローター機はアメリカの技術でもある」と議員の一人はいう。「ティルトローター技術には多くの国が注目している。しかし実際に開発に踏み切った国は今のところアメリカだけだ。したがってアメリカは世界で初めてティルトローター機を実用化する国となるし、やがては国外へも輸出するようになるであろう。とりわけ民間型ティルトローター機の開発は、世界の航空宇宙工業界における米国の主導的な立場を今後とも維持するのに役立つだろうし、輸出商品生産のための新しい職場を創出するものとなろう」
「ティルトローター技術は、航空界における眞に革新的な技術である。それは固定翼機の安定性とヘリコプターの多用性を兼ねそなえ、21世紀の航空界における新しいチャレンジであると共に、国際競争場裡における米国の立場を強化するものである。米国は今の絶好の機会を逃してはならない」
「空港の混雑は、今や世界中で進みつつある。といって新空港の建設も莫大な費用がかかり、滑走路の追加や延長すらも難しい時代になってきた。そこでティルトローター旅客機は、滑走路を使わずに一般旅客を輸送することができる。空港をバイパスして、旅客の出発地から目的地まで、それが都心部であろうと郊外であろうと、直接輸送することができる」
空港混雑の問題は、実は日本も米国以上に深刻なのだが、いかに広いアメリカであろうと、大都市周辺に新しい空港をつくるのは決して容易なことではない。今世紀最後の10年間を見ても、米国内で新設された大空港はデンバー新空港1か所だけに終わり、滑走路の増設ができたところも数か所しかないのである。
そこで米運輸省は1990年代初めから、如何にして既存の空港と航空路の容量を広げ、一定空域の中を一定時間内に通過する航空機の量を増やすかという問題を真剣に検討しはじめた。この検討は今も続いており、最終的には空域構造をつくり直し、管制方式を改めるところまで考えが進んでいる。
こうした航空輸送に関する構造改革の基礎となっているのが、1992年の「空港および航空路の改善に関する法律」である。この法律によって、米国ではここ数年来さまざまな研究調査がなされているが、「民間型ティルトローター機開発諮問委員会」(CTRDAC:CTR委員会)の発足と調査検討もそのひとつであった。
委員会の目的は旅客機としてのティルトローター機について技術的な可能性と経済的な現実性を探ると共に、それを全米の航空輸送システムに組みこむことの実現可能性について検討し、もって空港混雑の解消ができるか、米国の航空輸送システムが改善されるか、さらには米国としての経済的利点があるかといった課題を調査研究することであった。加えてティルトローター機を実用化するための開発費を、政府と航空工業界がどのような割合で負担すべきかも問われた。
委員会のメンバーは米運輸省、FAA、NASA、州政府、地方輸送機関、それに米航空業界の代表者など31人で構成された。そして与えられた課題について2年以上にわたる調査研究の結果、1995年12月アメリカ議会に宛てた報告書が完成した。
それによると、民間向けティルトローター機の開発は技術的に可能であり、また旅客にとって便利な場所に乗降施設を整備するならば、公的補助がなくても一定の旅客輸送市場において経済的に使うことも可能である。加えてティルトローター旅客機は今の空港混雑の解消にも役立ち、アメリカの貿易赤字の解消にも貢献できるという結論になっている。
ただし、こうした新しい輸送システムを構築してゆくには、政府と民間とが協力し合う必要があるというのが基本条件である。そして航空交通管制技術の開発は、ティルトローター機に適した飛行方式を含めて、政府の責任であるとした。またヴァーティポートなどの地上施設は、政府の主導のもとに自治体などの公的機関と民間企業との調整をはかりながら建設を進めること。そして一般国民がこの新しい技術を受け入れるよう啓蒙すべきことも盛りこまれた。
一方、実際のティルトローター機の設計や製造には民間企業が当たるべきであり、そのための費用も大半は企業が負担すべきであるという答申になっている。すなわち、ティルトローター機の開発については航空工業界が資金上の責任をもつのが基本であるけれども、ヴァーティポートの建設、ティルトローター機の運航に適した新しい航空管制方式の設定、そして所要の研究などは公的資金を基本とするというのである。なお新しい管制システムはGPSにもとづくものとなっている。
|
|
|
|
|
全 長 全 幅 全 高 エンジン 出 力 最大離陸重量 滑走離陸時(STOL) 垂直離陸時(VTOL) 自 重 ペイロード 座席数 最大速度 巡航速度 運用高度限界 航続距離 |
17.47m 25.54m 6.63m T406-400 6,150shp×2 25,909kg 24,032kg 15,032kg 約4.5トン 2+兵員24 630km/h 509km/h 7,925m 1,760km |
21.1m 26.3m 7.2m ターボシャフト 7,260shp×2 ―― 19,572kg 12,983kg 約4トン 2+旅客40+1 648km/h 583km/h 9,750m 1,100km |
ティルトローターの基本的な技術は軍用機も民間機も変わらない。したがってV-22によってティルトローターの設計、開発、製造といった実用的な技術が進歩すれば、民間型ティルトローター機の開発も比較的容易になってくるであろう。さらにV-22が実戦配備について、実用に供されるようになれば、一般国民もそれに馴染み、受入れやすくなるであろう。またティルトローター機にかかわるパイロットや整備士も増えてゆき、全体として普及への道を開くことになるであろう。
CTR委員会の報告書では、乗客40人乗りのティルトローター旅客機を中心に検討が加えられた。これはV-22とほぼ同様の大きさで、全米の航空輸送システムの中では、次のような3種類の役割が考えられるという。
第1は主要都市の都心部と都心部を直接結ぶ直行路線。第2は都心部と郊外の空港を結ぶフィーダー路線。第3は都心部や小さな空港から大きくて混雑したハブ空港へ飛ぶトランスファー路線である。
米国内で考えるならば、こうしたティルトローター路線は、北東部の大都市や空港が密集した地域で成立する可能性が最も大きい。滑走路の要らないヴァーティポートを都心部や空港隣接地につくればいいのである。
これによって、空港の混雑や飛行便の遅れが解消される。たとえば現在、アメリカの混雑度の激しい空港のうち7か所では離着陸する飛行機の23〜36%が50席以下の小型機であり、800km以下の近距離を飛んでいる。その分の旅客をティルトローター機で輸送するようになれば、飛行機の離着陸回数は3割前後が減る計算になる。
つまりティルトローター機は空港を使わず、市内または郊外の小さなヴァーティポートから近距離客をのせて飛べばよい。また長距離便への乗り継ぎ客も、ティルトローター機によって滑走路を使わず、飛行機とは別の場周経路で空港に入ってゆけばよい。
かくてCTR委員会は表3の通り、2010年までに全世界で1,160〜1,600機のティルトローター輸送機が飛ぶようになるだろうという需要予測を出した。
もっとも40人乗りの旅客機の開発には、やはり時間がかかる。そこでCTR委員会は当面、小型ティルトローター機を実用化して、その経験と実績の上に立って旅客輸送用の大型ティルトローター機を開発してはどうかと提案している。
まさしく、その提言通りになったのが、1996年11月、ベル社とボーイング社が開発に着手したモデル609であった。
モデル609は、大きさの点から見れば、XV-15によく似ている。しかし開発時期が違うし、V-22の開発経験から得られた数多くの技術を含めて、最新の技術が採り入れられている。たとえば機体は複合材製であり、コクピットの電子機器も大きく進歩した。
モデル609の開発には20〜30億ドルの資金が必要と見られる。その全てが民間資金でまかなわれる。そして旅客輸送用には、やや小さいかもしれぬが、それ以外のさまざまな用途に使われるようになろう。その中には、今のヘリコプター同様、近距離の旅客輸送にも使われるかもしれない。それが軌道に乗れば、次はもっと大きな機材が必要ということになって、いよいよ40席前後の民間型ティルトローター機が開発されることになろう。旅客路線における609は、それまでのつなぎの役を果たすのである。
|
|
|
|
米国・カナダ 欧 州 日 本 オセアニア 小 計 |
300〜 400機 300〜 400機 100〜 125機 1,085〜1,450機 |
|
|
|
|
|
|
ベル社とボーイング社は、V-22オスプレイの成功が確信された頃から、民間型ティルトローター機の開発を検討しはじめた。まずV-22に多少の手を加えて、そのまま民間機とする40人乗りの機体が考えられた。さらに、これをもっと大きくする70人乗りの本格的なティルトローター旅客機も構想された。逆にXV-15に新しい技術を組みこんだ小型ティルトローター機も検討された。
そして最終的に着手された開発計画が今のモデル609である。その開発に当たって、ベル社とボーイング社の考えた基本的な設計目標は次のような特性を持つ航空機であった。
同クラスのヘリコプターにくらべて速度と航続距離が2倍で、乗客にとっては快適な乗り心地が享受できること。そのためキャビン内部を与圧して高々度を飛び、気象条件の影響をできるだけ少なくし、全天候飛行が可能であること。既知の氷結気象状態の中にも入って行くことができること。
また機内の騒音が静かであるばかりでなく、機外騒音も小さく、急角度の進入を可能にして、離着陸地の周辺に及ぼす騒音の影響を最小限に抑えること。
安全な飛行が可能であることは当然だが、計器飛行のための統合アビオニクスを装備して、片発停止の場合も飛行継続が可能であること。そして運航費が安いこと、というものであった。
航空機としての設計仕様は乗員1人、乗客9人、最大離陸重量7,257kg、運用自重4,762kg、有効搭載量2,495kg、最大巡航速度509km/h、実用上昇限度7,500m、航続距離1,389km、キャビン長5.33m、キャビン高1.54m、キャビン幅1.52mで、FAAの新しい輸送用ティルトローター機の設計基準にしたがって、今のヘリコプターでいうカテゴリーAの飛行が可能で、パイロット1人の計器飛行基準にも適合することになっている。
また機体には複合材が多用され、ローターも複合材製。エンジンは2基のPT6を固定翼両端に取りつけ、操縦系統にはフライ・バイ・ワイヤが採用される。
主キャビン内部はさまざまな仕様が考えられる。乗降ドアは機体右側にあり、標準的な座席配置は操縦席2席のほかに乗客9人乗りだが、これを乗客6人乗りのデラックス配置とすることもできる。
また片側に担架2人分を置き、そのわきに医師、看護婦、またはパラメディック(救急救命士)がすわって、救急機とすることもできる。さらにドアから救難用の吊り上げホイストを張り出せば、捜索救難機にもなる。軍用機としては、V-22大型ティルトローター機の訓練機や兵員12人分の座席をつけて兵員輸送機とすることも可能。
また機体の大きさは、シコルスキーS-76やビーチ・キングエア200双発ターボプロップ機とほとんど変わらない。
以上のような特性から、モデル609はヘリコプターと固定翼機の両方の役割を果たすと共に、ヘリコプターの運航者にとっては速度と航続距離の増大をもたらすし、ターボプロップ機の運航者にとっては垂直離着陸を可能とするものとなるのである。
このような民間型ティルトローター機、モデル609の開発計画が、ベル、ボーイングの両社から発表されたのは1996年11月18日であった。ワシントンにあるスミソニアン航空宇宙博物館で、共同の記者会見がおこなわれたのである。
発表によると、両社は「ベルボーイング609」と呼ぶ6〜9人乗りの民間型ティルトローター機を設計開発し、型式証明を取り、販売し、技術支援をしてゆくために共同企業体ををつくるという内容であった。出資金額はベル社が51%、ボーイング社が49%という比率である。
この記者会見に際して、当時のベル社、ウェブ・ジョイナー会長は「新しいティルトローター機はV-22オスプレイによって軍事的に開発された技術を民間向けに再利用するものである。ターボプロップの速度と航続性能にヘリコプターの垂直離着陸能力を加えることにより、柔軟で多様な運用性を発揮することになろう」と語った。
またボーイング社のジム・モリス副社長は「民間型ティルトローター機は、世界の輸送システムの進歩のために重要な能力を有する。旅行者は混雑した空港を使わなくても、出発地から目的地へ直接飛ぶことが可能になる。またトップ・ビジネスマンにとっては最良の交通手段となり、石油開発、救急医療、災害救助の面でも劇的な能力を発揮するにちがいない」と語った。
この開発決定に至るまで、両社は2年間にわたって徹底的な市場調査をしてきた。その結果、米国および外国政府、企業、医療機関、石油会社などの発注が期待されることが分かった。機材も、これらの顧客の要請に合うように設計することにしている。
それから半年、1997年6月のパリ航空ショーでは、史上初の民間型ティルトローター機について初めて受注数が発表され、同時にモックアップ(実大模型)が展示された。その主翼両端には意外に大きなエンジン・ナセルが取りつけられ、先端にはローターもついて、今にも飛び上がらんばかりに見えた。この純白の機体はショーの会期中いつも多数の人に取り囲まれ、係員は質問攻めに大わらわであった。そして同機の展示によって、実際はモックアップだったにもかかわらず、他のヘリコプターの展示は影が薄くなったというのがベル社の主張である。
事実、ショーの初日には29機と発表された受注数は、最終日には36機に増えていた。わずか1週間余りで7機の注文を受けたことになる。
これらの発注者は必ずしも全ての名前が公表されたわけではないが、その中には米ペトロリアム・ヘリコプター社(PHI)、カナディアン・ヘリコプター社、米エバグリーン・ヘリコプター社、ノルウェーのヘリコプター・サービス社など世界有数のヘリコプター会社が含まれていた。加えて、米マサチュセッツ生命保険会社、ロイズ投資会社、そしてロス・ペロー2世のヒルウッド開発会社などの名前も見られた。価格は1機あたり800〜1,000万ドルという。
パリ航空ショーでは、今後の開発日程も発表された。それによると原型機は4機製作され、1号機は1999年に初飛行し、2001年までに型式証明を取って引渡しに入るというものだった。
こうしてモデル609の開発作業は本格化した。97年5月までに予備設計を終わるや、ただちに詳細設計がはじまり、同年夏にはコンピューターの描いた図面が続々と吐き出されていった。それに合わせて、ボーイング社のフィラデルフィア工場では8月から部品の製造に着手、ベル社のフォトワース工場でも主翼の組立準備がはじまった。
また、かねて割り当てが決まっていた装備品の下請けメーカーでも、いっせいに部品の製作がはじまった。これらのメーカーには、PT6C-67Aターボシャフト・エンジンを担当するプラット・アンド・ホイットニー社、降着装置のメシエ・ダウティ社、プロ・ライン21アビオニクスとディスプレイのロックウェル・コリンズ社、そして複合材を提供する日本の東レなどが含まれる。
パリ航空ショーから半年、1998年初頭までにモデル609の受注数は50機を越えた。ところが2月12日になって、突如ボーイング社が609の共同開発からおりることが発表された。
ボーイング社のロータークラフトに関する基本戦略の変更によるもので、今後は軍用機だけに絞って行くという方針が打ち出された。同社は97年夏、マクダネル・ダグラス社を吸収した。これによりマクダネル・ダグラス・ヘリコプターがボーイングの傘下に入り、AH-64アパッチ攻撃ヘリコプターや、MD520N、MD600、MD900といった小型ヘリコプターがボーイング社の名前で生産されることになった。しかし半年たって、民間ヘリコプターの製造は他社へ譲渡するというのが、この日の発表である。
つまりアパッチやV-22などの軍用ロータークラフトは今後も開発と生産を続けるが、モデル609は全てをベル社に委ね、民間向け小型ヘリコプターは新たな譲渡先を探すというのである。
折から国際ヘリコプター協会(HAI)の年次大会の直前だった。そのため、同大会ではさまざまな話題と憶測を読んだが、結果的に小型ヘリコプターも、MD900を除いて、ベル社が引き受けることになった。
こうしたことから、ベル社は98年3月1日、モデル609の開発を一手に引き受けることになった。ただしボーイング社も下請けメーカーの形で609の開発に協力し、胴体の製造などを担当することになっている。
この2月中旬のHAI大会で公表された受注数は61機である。その中の3機は三井物産エアロスペース社からの注文だったことが1週間後のシンガポール航空ショーで明らかにされた。このように日本からの注文が出たことは、取りも直さず日本の航空局もティルトローター機に関する耐空性審査基準や乗員の資格認定基準をつくらなければならないことを意味する。
そしてシンガポール・ショーの直後、609の受注数は63機に伸びたことが明らかになった。最後の2機はシンガポールのリージョン・エアからの注文である。これで同機の注文を出している国は世界7か国、発注者は37社になる。
同時に609の開発のために、ベル社がボーイングに代わる新しいパートナーを探していることも明らかにされた。当面は姉妹会社のテキストロン・エアロストラクチャー社がリスク負担で計画に参加する予定だが、同社はこれまでもV-22の尾翼の製造をしている。ほかにもベル社は、メーカー何社かと話し合いを進めているもよう。
なおモデル609の最終組立ては、ボーイング社の撤退の如何にかかわらず、それ以前からベル社のフォトワース工場でおこなうことに決まっていた。 今後10年間の販売見通しは350〜450機という。
ティルトローター機の研究開発は、ここまで見てきたように、XV-3、XV-15、V-22のいずれも軍用機をめざすものであった。したがって技術上の課題も軍事面から見た空力特性、飛行性能、安全性、操縦性などが対象であった。しかし民間型ティルトローター機を実用化するには、もうひとつ別の観点が必要となる。たとえば構造上の重量軽減、信頼性、コクピット技術、ヒューマン・ファクターなどの問題が考えられるが、とりわけ騒音と安全性と経済性の3点こそは最大の課題であろう。
安全性に関する課題は、特に旅客機として使う場合、軍用機はもとより一般的な使用事業に使う機材よりもきびしい耐空性基準が求められる。今の航空機の基準からすれば、飛行中に何らかの故障が起こってもパイロットが混乱することなく、そのまま安全な飛行が続けられるようでなければならない。とりわけティルトローター機は建物や人通りの多い市街地で離着陸できることが大きな利点である。そんなときにエンジンが停止したらどうなるか。
ティルトローター機に特有の安全性基準を考えなければならないのは、こうしたエンジン故障の場合である。ティルトローター機が固定翼で飛んでいるときのエンジン故障は、たとえ両方が停止しても、パイロットはグライダーのように滑空して着陸することができる。
ただし、その場合、ローター前傾のままで接地すれば直径が大きいのでブレードが地面に当たって吹き飛ぶだろうから、大変なことになる。したがって接地に際しては必ずエンジン・ナセルが垂直またはななめに立ち上がらなくてはならない。あるいはエンジンが正常であっても、ナセルの前傾作動装置が故障して元に戻らなくなればどうなるか。車輪が接地するよりも先にブレードが滑走路面に当たって、その破片が機体の中に飛びこんでくるかもしれない。
そのような疑問に対して、たとえばXV-15の場合、少なくとも45°まで持ち上げることができれば、ローターブレードが地面に当たらず、安全に着陸することができる。この作動装置は2重になっていて、どちらかが故障しても、片方で両方のナセルを動かすことができる。しかも、その動力源は油圧と電源の2種類があって、どちらでも作動する。なおかつ油圧も電源も2重だから、動力源は4重になる。
そのうえ電気系統が完全に故障しても、機械的に作動させることができる。パイロットがコクピットの中のハンドルを引っ張ると、油圧バルブが開いて作動装置を動かし、ナセルを垂直位置に戻すのである。これらの仕組みが、XV-15以降のティルトローター各機に組みこまれていることは当然である。
またヘリコプター状態で飛んでいるときのエンジン故障は、一発停止の場合、両エンジンをつなぐクロスシャフトによって双方のローターを回して安全な飛行を続けることができる。また両エンジン停止の場合は、安全なオートローテイション着陸が可能でなければならない。
上のようなベル社の安全対策とは別に、ローターブレードを望遠鏡のように伸び縮みできるして、安全と効率をはかろうという考え方もある。これは、先ずブレードを伸ばし、ローター直径を大きくして離陸する。ローター直径が大きければ揚力が大きく、垂直離陸が容易になる。同時に、両エンジンが停止してもオートローテイションが容易になる。沈下速度も遅くてすむから、機内の搭乗者にかかる衝撃も少ない。そして上空に上がってからは直径を縮めて回転数を上げ、飛行機のプロペラと同じような効率で巡航飛行をする。
もうひとつの課題はアビオニクスと操縦系統であろう。この技術も如何によって、ティルトローター機は悪天候の中でも安全に飛行できるようになるに違いない。
また複合材が多用されてることも考慮しなければならない。609には外板はもとより、機体の構造部材にまで複合材が使われる。それらの複合材について、いかなる耐空性基準を設けるかが問題となろう。
騒音問題は、これも容易ではない。ローターの回転音がもっと小さくならなければ、CTR委員会の報告書にもあるような便利な場所にヴァーティポートを建設することは難かしいかもしれない。ただし委員会は、ティルトローター機の騒音と排気は今のFAAの基準よりも小さくすることができると判断している。
CTR委員会はさらに、徹底した経済分析をおこない、ほかの輸送手段にくらべてティルトローター機の使用が経済合理性を持ち得るものかどうかを分析した。結果は手放しで喜べるようなことにはならなかったが、人口の多い大都市周辺の交通に使うならば、40人乗りのティルトローター機は今の大空港の旅客の10%を引き受けることができるということになった。
一般的に、ティルトローター機を使えば、旅客の移動時間は短くてすむ。ティルトローター機にとって空港混雑による遅れは考えられないし、都心部に直接降りることができるからである。
しかし実際に、どのくらいの時間節約になるかは推定困難であった。また旅行者が、そうした時間節約のためにどのくらい余分の運賃を払ってくれるかという問題もよく分からない。ティルトローター機は購入費も運航費も、普通の固定翼機にくらべて高くなることは間違いない。委員会としては、したがって、これを米国北東部の路線に投入した場合、通常の運賃よりも45%高くなるのではないかと推定した。
いま米国では民間型ティルトローター機の実用化のために、さまざまな機関が協力しながら計画を進めている。軍用型V-22は先に見たように、国防省が中心となって開発を進めてきた結果、いよいよ実用段階に近づいた。その成果を受けて、NASAは軍事技術から民間向けの技術を取り出すための研究をすすめつつある。またFAAはティルトローター固有の耐空性基準や操縦資格基準の制定を進めると共に、空域および管制システムを見直し、自治体に協力してヴァーティポートの増設方策を進めつつある。そして航空工業界はティルトローター機そのものの設計開発研究に取り組みはじめた。
こうした作業がいつ完成するのか。いつになったら現実の航空輸送システムの中にティルトローター旅客機が導入されるのか、必ずしもはっきりしない。が、少なくともCTR委員会は表3で見たように、2010年までに北米の旅客輸送に385機を越えるティルトローター旅客機が飛ぶことになろうと予測した。ちなみに日本も欧州全域に肩を並べて300〜400機の需要があると見られている点に注目しておく必要があろう。
このようなティルトローター旅客機の実現を、軍用機から民間機への技術移転と見るならば、ボーイングB-47大型ジェット爆撃機が1947年に初飛行してからボーイング707ジェット旅客機が1958年に就航するまで11年を要したことにたとえられるかもしれない。
同じような調子で行けば、1989年にV-22が初飛行してから11年後の2000年に同クラスのティルトローター旅客機が就航してもいいかもしれない。実際は、まだそこまでの準備はできているようには見えないが、609が代役を努めるのであろう。
予測というものは、つい楽天的になり勝ちである。だが技術的な突破口は、しばしば楽天的な考え方によって開けるものである。そもそも今のティルトローター機だって、ベルXV-3を実現させたロバート・リヒテンがいなければ、果たしてここまで進むことができたかどうか。「構想は大胆に、準備は慎重に、予測は楽観的に」と語ったのも、この人であった。
モデル609の販売を担当する三井物産エアロスペース社は、楽観的とも見える予測のもとに3機を発注した。その大胆な構想が21世紀初めには日本でも実現するに違いない。
(西川渉、『エアワールド』誌98年8月号掲載)
![]() (「本頁篇」目次へ戻る) (表紙へ戻る)
(「本頁篇」目次へ戻る) (表紙へ戻る)