<原油価格>
航空事業への影響 

航空機にとって燃料は、人間における食料のようなもの。これがなければ飛ぶことができない。つまり生きてゆけないわけで、最近の燃料の値下がりは、われわれの食費が安くなったことに等しい。したがって大型旅客機を飛ばしているエアライン業界は、IATA(国際航空運送協会)によれば、昨年後半から予想以上に利益が上がるようになったという。
逆に、燃油費が下がれば、エアラインとして燃料効率の良い新製機へ買い替える必要がなくなってくる。旧来の旅客機を使い続ける方がいいというので、旅客機の発注が減るかもしれない。ということは航空機メーカーに不利な影響が及ぶのではないかという見方も出ている。

一方ヘリコプター事業は、その基盤を石油開発に置いているため、原油の値下がりによって油田開発が低調になればヘリコプターの利用も減り、事業規模も縮小する。
油田開発の支援に使われるヘリコプターの役割は、陸上基地と沖合い遠くの油田プラットフォームとの間で石油作業員の交替輸送をすることにある。この人員輸送の2〜3割は試掘段階にある現場への輸送、残りは生産段階にある油田への輸送である。そこで今後、原油価格が下がれば試掘作業が減ることにもなりかねない。
ただし幸か不幸か、日本は周辺海域で石油が出ないので、この分野の事業は皆無に等しい。
油田開発向けのオフショア飛行が盛んにおこなわれているのは、世界の油田地帯――メキシコ湾、アラビア湾、北海、インドネシア海域などで、人員輸送だから大型ヘリコプターが使われる。その数は現在、世界中で約2,300機という。
それらの機材を製造しているメーカーは、シコルスキー、エアバス、アグスタウェストランドで、民間向けヘリコプターの年間売上高60億ドルのうち、ほぼ4割が石油開発向けの機体であった。たとえばシコルスキー社の場合、民間機の製造は3分の2が石油開発向けで、影響も大きい。ちなみに軍用ヘリコプターの販売額は年間160億ドルである。
ヘリコプター運航会社の方も、原油の値段が下れば油田の開発が下火になり、事業規模が縮小する。すでにカナダを本拠として世界的に展開しているCHCグループは売上高が7割減、ERAグループは29%減、ブリストウ・グループは24%減になったと伝えられる。
もっともCHCやブリストウは強気の姿勢を崩していない。海底油田は今後なお沖合い遠くなる趨勢にあり、ヘリコプターの利用はさらに増えるという。しかし原油価格は最近1バレル48ドル付近まで半減したが、今後もこのような状態が続くならば、ヘリコプター界にも大きな打撃となろう。

それにつけても思い出すのは1970年代後半、石油ショックが世界中を襲ったときであった。中東のOPEC諸国が石油の輸出を制限し、原油の価格を引き上げて、世界中に混乱を巻き起こした。日本では何故か、トイレット・ペーパーの買い占め騒ぎが起こった。
このときエアライン各社は燃料の値上がり経費を如何にして吸収するかという問題もさることながら、燃料そのものの確保にも腐心することとなった。
われわれヘリコプター会社も燃料がなくては飛べないので、その確保のために、燃料会社と交渉して長期的な購入協定を結んだり、貯蔵タンクを拡大して貯蔵量を増やしたりしたものである。
その一方で、当時の石油開発公団が日本周辺の海域を初め、インドネシア、フィリピン、台湾、韓国、中国、バングラデシュ、マレーシアなどの海域で油田開発を急ぐことになり、ここに上述したようなヘリコプターの需要が生まれることとなった。
筆者の勤務先でも石油開発公団や、その傘下の石油資源開発、ならびに出光、帝石といった石油関連会社と交渉し、各国政府の飛行許可を取って、国外でヘリコプターを運航した。ところが石油が出るようなところは文化果つる辺地ばかりで、現場に送り出されたパイロットや整備士は汗と涙にまみれて仕事をしたものである。
そうしたことが10年余りも続いたであろうか。石油開発ラッシュによって当時、会社の規模が拡大し、いずれは世界的なヘリコプター会社に肩を並べ、世界ランクの中で5位、できれば3位以内に入ることをめざした。
それと同時に全く目標物のない海の上を200〜300キロの遠くまで飛ぶために、独自の計器飛行も工夫した。まだ今のようなGPSのない時代である。中国渤海湾の石油開発に従事したときは、ベル212を現地へ持ってゆくために、長崎県福江空港から上海まで茫漠たる洋上を直接飛行して、小さなヘリコプターで何故そんなことができるのか、航空関係者を驚かせたこともある。その成功の蔭には、機体の改修や計器類の較正、HF無線による長距離通信、そして日本、中国、韓国の飛行許可など、事前の準備や実験飛行を繰り返すといった努力のあったことはいうまでもない。
しかし現地で、石油が見つかって生産段階に入り、仕事が安定してくると、相手国が自国のヘリコプターを使うことを主張するようになり、われわれの機体も引き揚げざるを得ないこととなった。以来、何年も日本のヘリコプター会社による海外事業は見られない。
石油は、価格の上下と産出量の増減によって、いつも航空界に大きな影響を及ぼすことになる。
(西川 渉、2015.1.23)
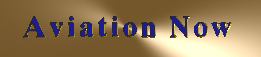
(表紙へ戻る)

