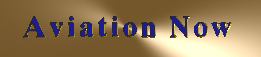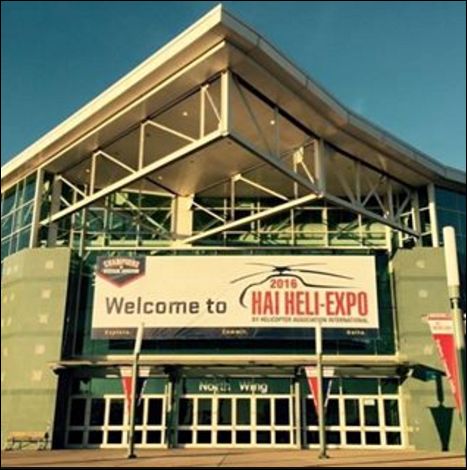<HELI-EXPO 2016>
60機近いヘリコプターを展示

国際ヘリコプター協会(HAI)の主催する「ヘリ・エクスポ2016」は、今年3月1日から3日まで、米ケンタッキー州ルイビルのエクスポジション・センターで開催された。出展企業は700社以上、展示されたヘリコプターは60機に近く、入場者はおよそ14,000人。同時に、単なる製品展示ばかりでなく、さまざまな研修会や安全セミナーが開かれた。
その中から、ここでは主要なヘリコプター・メーカーの動向と新しい機材の開発状況を見て行くことにしよう。
展示会場のケンタッキー・コンベンション・センター
ブルーエッジ100時間の飛行 展示会場は全米最大級の大きさがある。その中でも広い面積を占めていたのがエアバス・ヘリコプターズ社。展示機は警察向けの装備をしたH125エキュレイユ単発機、その発達型で軍用仕様のH130、社用ビジネス機の内装を備えたH135とH145双発機、大型多用途機H215スーパーピューマの5機種であった。
そのほかH175と開発中のH160については、ヴァーチャル・リアリティ装置が設けられ、そこに映し出される映像で視覚的にコクピットやキャビン内装を体験することができた。
このうちH175は、2014年12月から実用段階に入り、海洋石油開発の人員輸送を主な任務として、1号機は最初の1年間で1,000時間の飛行を記録した。この間の可動率は95%を超える信頼性を示し、北海の石油開発に従事する運航会社も同機の安全性、柔軟性、さらに高いペイロードと費用効果に満足しているという。総重量は7、500kgだが、近く7,800kgまで認められる予定。これでペイロードが300kg増となり、航続距離も70kmほど延びる。最近までの受注数は36機。
もうひとつのH160は原型1号機が2015年6月13日の初飛行以来ほぼ100時間の試験飛行をこなし、2号機も今年1月27日から飛び始めた。最大の特徴は「ブルーエッジ」と呼ばれる主ローター・ブレードで、後方へ二重に曲がりくねったような平面形を有し、空気抵抗と騒音を減らすと共に、速度、航続距離、ペイロードの向上に寄与している。さらに尾部ローターも角度12°の傾斜がつく一方、水平安定板は複葉になって低速飛行時やホバリング中の安定性が良くなった。エンジンは新しいターボメカ・アラノ(1,100~1,300shp)が2基。強力で、すぐれた燃料効率が特徴である。
ローター・ブレードの曲がりくねったH160
REGA向けのAW169は完全防氷装備 もうひとつの欧州メーカーは、イタリアのフィンメカニカ・ヘリコプター事業部。今年1月、これまでのアグスタウェストランド社が親会社の名前に従って改称したもの。
ここも、ゆったりした区画を取って、AW109、AW009、AW169、AW119Kxが展示された。このうちAW109トレッカーは従来のAW109Sグランド双発機を、車輪式の引っ込み脚から単純構造のスキッド式に改め、軽量化をはかって飛行性能を向上させたもの。最大速度は311㎞/h、航続800kmで、総重量は3,175kgだが、将来は3,400kgまで増やし、ペイロードを上げて物資輸送にも使えるようにするという。エンジンはPW207Cターボシャフト(815shp)が2基。
会場に展示されたのは救急装備をした機体で、機内は患者搬送用のストレッチャー1台とドクターやナースなど3~4人乗りだが、ストレッチャー2台の搭載も可能。標準型のキャビンは乗客6人乗りとなる。一方で最新のグラス・コクピットを備えて操縦負担を減らし、パイロット1人で計器飛行もできる。
折からトレッカーは、このエクスポ期間中の3月2日、原型1号機がイタリアで初飛行した。今後は原型2機で試験飛行をおこない、本年中に型式証明を取得する予定。最近までの受注数は20機。
AW109トレッカーの初飛行AW169は昨年、型式証明を取って、今年初めから実用段階に入った。最新のグラス・コクピットを備え、操縦席から見た視界も広い。総重量4,600kgで、パイロット1~2人と乗客8~10人乗り。エクスポ会場では救急仕様の機体が展示されたが、ビジネス機として要人輸送にも使える多用途機。スイスの救急救助法人REGAからは完全防氷装備をした捜索救難機として3機を受注。ほかに世界20ヵ国、50社から注文を受けている。
AW009は、かつてポーランドで開発されたPZL SW-4に手を加えた改良型の単発機。RR250-C20ターボシャフト・エンジン(450shp)1基を装備して飛行性能を上げている。総重量は1,800kgで、5人乗り。近く米FAAの型式証明を取って米国向けに売り出す計画で、警察、救急、訓練、自家用などの用途が考えられる。すでにカリフォルニアの警察から発注意向が表明された。
もうひとつのAW119Kx単発機は救急仕様の機体が展示され、中国から25機の受注が発表された。また、これらの展示とは別にフィンメカニカは、日本の静岡エアコミューターから今年1月AW109グランドニュー1機の注文を受けたと発表した。同機は今年秋から新潟県ドクターヘリの2号機として、長岡赤十字病院で救急飛行が始まる。
AW169
AW609の今後に強気の姿勢 フィンメカニカの話題はもうひとつ、民間向けティルトローター機AW609の今後が注目される。エクスポ会場では3月2日、フィンメカニカとアメリカの運航会社ERAとの間で覚え書きが交わされ、同機の救急仕様について共同開発をすることになった。この開発作業には内装、運航、法規、整備などに関する事項が含まれる。特に重要なのは、FAAの型式証明取得にあたって、ERAの運航者としての協力が得られることであろう。
またティルトローター機による救急飛行は、患者の近くに着陸できると同時に、最大500㎞/hの高速で航続1,300kmの飛行性能を持つこと。さらに計器飛行も可能で、救急患者の救護時間を大幅に短縮することが期待される。そのため原型機のひとつを将来、救急仕様に改め、実験飛行にも使う計画。
なおAW609は昨年10月30日、原型2号機がフィンメカニカの工場から50kmほどの地点で、高速飛行試験中に事故を起こし、乗っていた2人のテスト・パイロットが死亡した。同機はこのときまでに2006年の飛行開始以来、567時間を飛んでいる。
事故原因については、イタリアの飛行安全当局が調査にあたっており、フライト・レコーダーを解析中。その結果がはっきりするまでは、アメリカで試験飛行をしていた原型1号機も飛行を自粛している。
しかしフィンメカニカ社は強気で、原因はほぼ察しがついているとし、多少の手直しをするだけで間もなく飛行を再開するという。
【追記】原型3号機はイタリアで組立てが終わって、5月4日から地上試験を開始した。この夏から飛行試験に入る予定。また4号機は来年試験を開始、AW609としては2018年に型式証明を取得する計画である。最近までの受注数は約60機。実用になれば、石油開発、旅客輸送、パトロール、救急飛行などに使われる。
試験飛行の再開が待たれるAW609ティルトローター機
ベルV-280は来年初飛行 ティルトローター機は、ベル社からもV-280ヴェイラーの実物大モックアップが展示された。ベル・ヘリコプター社が第3世代のティルトローターとして米陸軍向けに開発中の機体で、巡航速度510㎞/h――すなわち名前の由来通りの280ktで、作戦半径900~1,500km、戦略的展開距離3,800kmの飛行性能をもつ。
その特徴は、AW609やV-22オスプレイと異なり、左右の固定翼両端にエンジンを固定し、そこに取りつけたローターマストだけが水平から垂直まで変向する。したがって、エンジンとローターが一緒に動くオスプレイにくらべて機構は簡単で軽量、部品数も少なく、信頼性が高いという。
また機体重量に対してローターの回転面が比較的大きいので、ディスク・ローディングがオスプレイより小さい。そのためダウンウォッシュも弱く、胴体側面の大きなドアからホイスト作業をするのも楽になる。乗降には胴体左右に幅1.8mのサイド・ドアがつき、兵員11人が迅速に乗りこむことができる。ほかにパイロットや射撃手など4人の乗員が乗り組み、操縦系統には3重のフライ・バイ・ワイアがつく。
こうしたV-280について、ベル社は2017年から試験飛行に入り、2030年代の実用化をめざしている。これが軍の採用になれば、約4,000機が調達され、現用UH-60多用途機、AH-64アパッチ攻撃機、 CH-47チヌーク、OH-58カイオワに取って代わるという計画。機体価格は今のV-22オスプレイの半値になるとか。
さらにV-280を民間向けに転用すれば、現用ヘリコプターに対して速度が2倍、航続距離も2倍という飛行性能を発揮、石油開発や要人輸送などに使えるという見方も出ている。しかしベル社は今のところ、そうした計画はないとして民間型構想を否定した。その代わり、かつてはアグスタ社と共同開発を進めながら、2011年に手放したAW609ティルトローター機の実用化に協力し、支援していく意向を表明している。
なお。ティルトローター機に関するベル社の基本的な考え方は、そのすぐれた飛行性能に誰も疑問はないが、これからは「信頼性、整備性、経済性を理想的な形で実現することが大切」というもの。V-280の初飛行は2017年後半に予定されている。
エクスポ会場に展示されたV-280モックアップ
ベル中・小型ヘリコプター群 ほかにベル社は505軽単発機と新しい525中型双発機を展示した。505ジェットレンジャーXは2014年11月10日、525リレントレスは15年7月1日に初飛行しており、ここに展示されたのも試験飛行中の実機である。505はすでに原型3機で500時間以上を飛び、今年末までに型式証明を取って、量産機の引渡しに入る予定。また525は2機でこれまで140時間を飛び、370㎞/hの高速を記録している。型式証明の取得は2017年の予定。
なお505には350機以上、525には80機近い予約注文がきている。さらにエクスポ会場では525について中国から10機を受注したことが発表された。捜索救難や人員輸送に使われるもよう。
ほかにベル社からは429, 407GXP, 412EPI、407GXが展示された。このうち407GXPは出力強化型の単発機で、米エアメソッド社へ救急機として向こう10年間に200機を引渡す契約が発表された。
ベル525
S-97レイダーの開発進む シコルスキー社は昨年11月、ユナイテッド・テクノロジー・グループからロッキード・マーチン・グループに移った。この新しい環境の中で、どこまでシナジー効果が発揮できるか、注目されるところである。
ヘリ・エクスポ会場では、タイのヘリコプター運航会社から5機のS-76Dと2機のS-92を受注したことが発表された。いずれも海洋石油開発の支援に使われる予定で、原油価格の値下がりによって開発作業が下火になっている現状で、このような発注は珍しいといえるかもしれない。なお、S-76はこれまでの飛行実績が700万時間に達し、S-92も2004年以来275機を引渡し、ほぼ100万時間を記録している。
展示されたのは新しいS-92GWE(Gross Weight Expansion)。その名のとおり、総重量が12,020kgから12,565kgへ500kg余り増加し、ペイロードが増えた。
もうひとつ、シコルスキー社ではS-97レイダーの開発が進んでいる。二重反転ローターと機体尾部の推進用プロペラを特徴とする高速実験機で、昨年5月22日の初飛行以来、さまざまなテストを続けてきた。今後は2016年中に60時間を飛んで速度性能と運動性の飛行範囲を拡張していく。当面の開発目標は軍用機だが、将来は民間機としても捜索救難、救急飛行、要人輸送などを想定している。
二重反転ローターのS-97レイダー
MDヘリコプター改めて民間市場へ MDヘリコプター社は、小型軍用ヘリコプターの開発と製造に重点を置いてきた。エクスポ会場での発表によれば、マレーシア政府からMD530G偵察攻撃ヘリコプター6機の注文を受けた。すでに試験飛行が始まっており、来年初めまでに全機引渡す計画。530Gは、30年前に実用化された530Fを近代化するもので、2013年に初飛行、降着装置を強化して総重量を1,700kgに増やし、ロケット弾や機関砲など火器の搭載量や航続距離を伸ばす。最大速度は240㎞/h。
さらに同社は新しい単発攻撃ヘリコプター6XXの開発を進めており、ロールスロイスM250エンジン(675shp)1基を装備して出力を強化、燃料効率を高めて、航続距離を740kmまで伸ばし、新しい攻撃ヘリコプターとして2018年末までに完成する計画。
こうして、MDヘリコプター社は長らく小型軍用機の開発と製造に余念がなく、民間向けMD902エクスプローラーをおろそかにするきらいがあった。しかし今回のヘリ・エクスポ会場では、これからはMD902の改良発展にも努めたいという表明がなされた。ノーター・システムの強化、機体構造の軽量化、自動操縦装置の改善などをほどこした新しい902を来年初めにも完成させる計画である。

ロビンソンからR44訓練機 原油価格の値下がりは、石油開発に使われる大型ヘリコプターの売れゆきを減らすばかりでなく、小型ヘリコプターも影響を受けるもよう。今年のヘリ・エクスポでも前年にくらべて、機体購入のニュースが少なかった。運航会社の方も用心深くなっているのであろう。
原油が下がれば、航空機の燃料費も下がる。そうなると運航者も新しく燃料効率の良い機材を無理して買い替える必要がなくなる。したがってメーカーの方もいろいろ魅力的な新機材を展示しているが、なかなか具体的な受注には至らない。
そんな状況の中で、R22、R44、R66といった小型ヘリコプターを製造しているロビンソン・ヘリコプター社は、新しいR44カデットを展示した。従来の4人乗りR44から後部の2座席をなくし、2人乗りの訓練機としたもの。安定性が良く、単発ピストン・エンジン(225hp)にも出力の余裕があって、訓練飛行に適するという。またIFRアビオニクスを装備すれば計器飛行訓練にも使うことができる。
型式証明は間もなく取得できる見込みで、価格は339,000ドル(約3,800万円)。本来のR44より3万ドルほど安い。最近までの受注数は「多数」というだけで、具体的な数字は明らかにされなかった。
なおロビンソン・ヘリコプターの引渡し数は、2014年が合わせて329機、15年が347機だった。一見増えたように見えるが、2013年の523機にくらべるとはるかに少ない。しかも2016年はドル高のせいもあって15年より少なくなる気配さえ見えるという。

2015年中の民間向け引渡し実績 もう一つの小型ヘリコプター・メーカー、エンストローム社も2012年オーナーが中国の企業に変わったが、中国経済の不振も重なって期待通りの売れゆきは望めない。そのうえ去る2月、小型ピストン練習機として開発中のTH180が試験飛行中に事故を起こし、いっそう苦しい状況になった。それでも間もなく原型2号機が飛び、3号機も今年中に飛んで、2017年春までに型式証明を取るとしている。
これらの小型機を含めて、2015年中に各メーカーが顧客へ引渡した民間ヘリコプターは総数954機。前年の998機にくらべて4.4%減となった。下表はジェネラル・アビエーション製造協会(GAMA)の集計によるもので、タービン機は2015年の引渡し数が675機、14年の741機にくらべて8.9%減であった。このタービン機の中で最も製造数の多いのはエアバス・ヘリコプターズの279機だが、それでも前年比13.9%減となっている。次いでベル社の175機が多く、それにロビンソン、シコルスキー、エンストロームと続く。
なお、ここには示されてないが、機種別にはロビンソンR66の117機が最も多く、それにベル407の99機、エアバスH125の90機、H130の69機、ベル429の52機が続いている。
メーカー 2015年
2014年
増減(%)
タービン機
エアバス
279
324
-13.9
ベル
175
178
-1.7
エンストローム
15
14
+7.1
フィンメカニカ
60
65
-7.7
ロビンソン
117
101
+15.8
シコルスキー
29
59
-50.8
ピストン機
全メーカー
279
257
+8.6
合 計 954
998
-4.4

ヘリコプターの安全性向上運動 今回のヘリ・エクスポで注目されたのは、ヘリコプターの安全性向上運動の成果である。運動の主体となる国際ヘリコプター安全チーム(IHST)が「10年間で事故率8割減」という目標を掲げて発足したのが2005年末。その10年目に当たるタイミングだった。
この10年間、IHSTは世界中のデータ収集と分析に当たってきたが、実際に作業を始めてみると、事故率の基本となる飛行時間すらはっきりしない。たとえば日本でも、事業用ヘリコプターの飛行時間は毎年、全日本航空事業連合会でヘリコプター事業会社からの報告を集計している。しかし、それ以外の自家用機などは報告の義務がなく、個々の機体については正確な記録があっても、それらを一つにまとめる仕組みがない。したがって国全体としては、事業用、自家用、さらには警察、消防などのヘリコプターが合わせて何時間飛んでいるか、正確な数字は必ずしも明確ではない。
ましてや世界中のすべての国々について飛行時間を集計するのは極めて難しい。結果としてIHSTは、事故件数はほぼ正確につかみながら、飛行時間は推定値を使わざるを得なかった。それも全世界というわけにはゆかず、米国や欧州など限られた国のみの分析にとどまった。
たとえばアメリカの場合、IHSTの推定では2015年の10万時間あたりの事故率が3.67件であった。当初の目標は10年前の7.97件を8割減の1.59件にするということだったから、それよりも相当に高く、54%減にすぎない。
では、なぜ目標に到達できなかったのか。理由のひとつはもともと、当初の目標が理想的にすぎたからであろう。たとえば軽飛行機についても事故削減運動がおこなわれているが、その目標は1割減ということである。それからすれば、半分以下になったのは逆に好成績といえるかもしれない。
こうしたアメリカの実績を初め、ヨーロッパなどの結果が持ち寄られ、ヘリ・エクスポ会場で検討された。その結果、IHSTの活動がヘリコプター関係者の安全意識を高めたことは確かであり、今後さらに飛行の安全を高めてゆく上で意義があるという結論に達し、今年から改めて第2段階の運動を続けてゆくことになった。
次のヘリ・エクスポは2017年3月7~9日ダラスで、翌2018年は2月25~27日ラスベガスで開催される。
(西川 渉、航空情報2016年6月号掲載)
(表紙へ戻る)