<本の栞>
異常事故 去る3月8日未明、クアラルンプール国際空港を飛び立ったマレーシア航空機が行方を絶った。初めはマレー半島東方の沖合、すなわち北京へ向かう正常な飛行経路沿いに墜落したかと思われたが、のちに西方のインド洋沖かもしれないということになり、さらにはオーストラリア西方の沖合いと見られるにいたった。つまり墜落地点もよく分からず、そこと思われるあたりを探しても何も見つからない。まことに不可思議な事故である。
このMH370便に乗っていた乗客乗員は合わせて251人。事故から早くも2ヵ月近くなるが、今なお機体残骸のひとかけらも見つかっていない。いずれは全貌が明らかになるのかもしれぬが、現状はおそろしく奇妙で異常な事故、あるいは事件というほかはない。

旅客機の事故原因や形態には二つの種類がある。そう説くのは『航空機事故50年史』(加藤寛一郎、講談社、2013年4月1日刊)である。
本の前半はジェット旅客機出現までの50年間の歴史、後半はジェット旅客機登場後の50年間に起きた事故の趨勢を分析している。
その中で、著者は「航空機事故は大別して、恒常的に起こる事故と、予想もしない原因で起こる事故」から成るという。後者は異常な事故が多く、「予想もしない」だけに予想するのが難しく、したがって大きな事故になりやすい。だから滅多に起こらないかと思うが、さにあらず。事故件数にすれば両者ほぼ半々となる。
前者の恒常的に起こる事故とは「同種ないし類似」の事故で、たとえば「高度を下げ過ぎて起こる事故」「新型機に起こる事故」「整備のミスで起こる事故」など、繰り返し発生するものをいう。その基本にあるのは、いわゆるヒューマン・ファクターで、著者の引用するボーイング社の統計によれば「1979〜1988年の10年間のジェット旅客機事故の主要原因は、乗員61.4%、機体18.4%、整備2.9%、気象4.8%、空港/管制5.8%、その他6.8」と、乗員の操作ミス、判断ミス、聞きちがい、思い違いなどが大半を占める。これを防ぐのは教育と訓練の繰り返しだが、分かっていても、人間がやっている限り恒常的に発生し、なくなることはない。
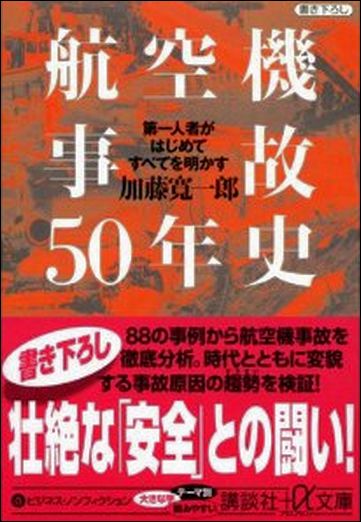

これに対する予想外の「まさか」ともいうべき異常事故にはどんなものがあるか。その「象徴的事例」として、著者は2件を挙げている。ひとつは燃料タンクの爆発――落雷や火災による誘爆は前例も少なくないが、1996年ニューヨークから飛び立って12分後に空中爆発したトランスワールド航空(TWA)ボーイング747の場合は、外部からの誘爆ではなく、「タンク外で起きた電線のショートで過大な電圧を発生……燃料表示系統の電線を介して(使用していなかった)燃料タンク内に侵入」し、そこに残っていたわずかな燃料蒸気に引火した。「純粋な意味でのタンク爆発」の初めての事例という。
もうひとつは超音速旅客機コンコルドの事故で、パリのシャルル・ドゴール空港を火炎と共に離陸し、直後に墜落して乗員・乗客109人の全員と地上の4人が死亡した。この事故を、筆者はロンドンで知った。2000年夏たまたま出張中の出来事で、その夜はホテルの部屋のテレビをつけっぱなしにして、くり返しニュースを見たが、コンコルドが火を噴きながら木立の向こうを飛んで行く映像が見えるだけで、何故こんなことになったのか、深夜まで原因が分からない。
分からないのはアナウンサーが早口の英語でまくし立てるせいかと思ったが、実はこれも予想外の事故だったからである。原因がはっきりしたのはしばらく後になってから、離陸滑走中そこに落ちていた異物を左主脚が踏み、タイヤが損傷して、その破片が翼内燃料タンクを破壊、火災を発生させたのだった。
ほかにも著者は、次のような「まさかの事例」を挙げる。「操縦室の天井裏火災」「滑走路の照明が消えた」「乗員が酸欠に陥った」「自殺が疑われた」「手順無視の度が過ぎた」「機長も副操縦士も何もしなかった」などで、それぞれについて詳しい経緯を説明している。


では何故、このような異常事故が起こるのか。著者は「逆説的にいえば、飛行が進歩し、安全対策が進んだ結果」だという。進歩した安全対策の隙間から発生する事故だけに、却って「『まさか』に見える場合が多い」のだと。
事実、旅客機の安全性は、著者によれば「過去20年間で……年間死亡者数が2,000名から300名を切るまでに改善された。運航と機数の増加を考えれば、安全度は一桁改善されたと考えてよい」
そのように進歩した航空機の安全を確保するには、どうすればいいか。最近の旅客機は「極度に自動化され」「ボタンとノブで飛ぶ」ようになった。「そのシステムを熟知しているのは、むしろ整備に強い」人ではないか。これからはチャック・イエーガーのような人物が安全のリーダーとなり、企業の重役となるべきだ、と著者はいう。「理想的には、整備出身のリーダーが操縦を学ぶのがよいであろう。そうすれば、パイロットの心を理解できる安全のリーダーが現れることになる」
イエーガーは史上初めて音速を突破したパイロットだが、一方で整備士以上に航空機の細部に精通し、整備の実務もできた。だからこそ、きわめて危険な条件の中で、自信をもって音速突破ができたのである。
「イエーガーは、飛行機を隅々まで知ることで、新しい時代を開いた。いま再び、同じ流儀で、安全の新しい世界が開かれるのではないか」


以上に加えて、著者の結論はもうひとつ、「最後の砦は人間である」「安全も、最後は人である」。航空機や安全に関する自分の仕事が「好きで好きでしようがない」ような人でなければ安全を守りきるのは難しい。
かつて著者は世界の多くの国を訪ねて、腕の良い超一流のパイロットの話を聞いて歩いた。「1万人に1人」といえるくらいの腕をもつ30人ほどのパイロットたちから話を聞き、そこに共通するのは「飛ぶことが好きで好きでしようがない。彼らは一生かけて飛行を楽しんでいる」という発見だった。
言い換えれば「一生かけて仕事を楽しんでいる。必ずしも刻苦勉励努力しているわけではない。好きで楽しんでいるからこそ、長続きし、上達する」
「もちろん……超優秀なパイロットたちも……実際には凄い努力を続けている。しかし本人たちに、そういう意識がない。これが私のいう『好きで楽しむ』である」
このインタビューの経緯は『生還への飛行』という本になって1989年に出版された。それが文庫版になるとき、光栄にも筆者は巻末の解説を書くように依頼された。以下はその『生還への飛行』(加藤寛一郎、講談社文庫、1992年8月15日刊)からの抜き書きである。

『生還への飛行』解説 飛行機とユーモアとお酒 ――免許皆伝のパイロットたち―― この本はまことに面白い。
読んでいて動きがある。凄味がある。そして中味がある。
東大教授の書いた本だから、内容が正確で濃密なのは当然かもしれぬが、いかに大学の先生でも、これほどまでに生きいきとダイナミックに、操縦と飛行の世界を描き出せる人は滅多にいないだろう。むしろ絶妙に過ぎて、謹厳たるべき大学教授がそれでいいのかと心配になるほどである。
三年前に本書のハードカバー版が出たとき、一読してそう思ったから、すぐに感想文を書いて、航空専門紙に載せてもらった。それが加藤寛一郎教授のお眼に留まって、この文庫の解説を書くことになった。
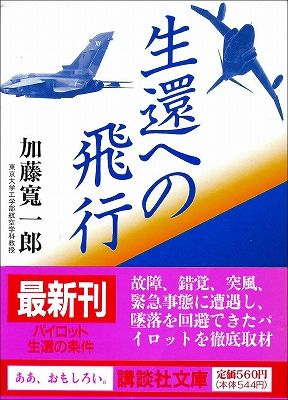

本書の主題は操縦の極意を追求したものである。
操縦がうまいとか下手とかいうのは、どういうことであろうか。なめらかでスムーズな飛行、着陸のときも接地の衝撃を乗客に感じさせないような飛行をいうのかもしれない。けれども、それだけではあるまい。
飛行機が正常に飛んでいるとき――機体の調子もよく、天候もおだやかで、何事もないときは、おそらく、ほとんどのパイロットが「うまい操縦」をするに違いない。
ところが、いったん何事かが起きたとき、対処の仕方は上手と下手、達人と凡人とで大きく分かれる。まかり問違えば事故を起こして、死に至る。そこを間違えずに、無事に生還してこそ、うまいパイロットということになる。それには、何が必要か。
そうした操縦の極意を求めて、著者は世界中の達人たちを訪ね歩く。そして
「あなたの最も危険な体験は?」
という問いを繰り返しながら、最後にひとつの結論にたどり着く。その結論については、本書を読み終った人に繰り返す必要はないし、まだ読み終ってない人に種明しをするのもよくないであろう。いずれにせよ、本書を最後まで読み通したとき、歯切れのいい文体と、少しずつ結論に向かって収斂していく構成によって、それを会得することができるようになっている。

したがって、いまさら何かをつけ加える必要はないが、長年、航空会社に勤めていた関係で、私もパイロットの皆さんの話を聴く機会が多かった。その中で感じた操縦のうまさを、著者と違う言葉でいうならば、少なくとも変事に対して素早く対応できる敏感さと敏捷さが必要であろう。しかし余り敏感すぎて、すぐにカッとなってしまうようではいけないし、鈍感の余り変事の初動を見すごしたり、素早い対応ができなくても困る。
そのあたりの調和を得るには、心の鍛錬と技の演練はもとよりだが、基本となるのは持って生まれた資質ではないだろうか。と言ってしまえば、著者の結論とは違ってくるけれども、その上に立って心と技を鍛え抜かなければならない。軍や航空会社がパイロットを採用したり、養成していくときに、まずは適性によって選別するのも、そういう理由からであろう。
著者は、そうした問題を追求し、最後に極意を見出だすわけだが、問題がむずかしいからといって、しかつめらしく肩肘張って書いているわけではない。それどころか答えを求めて走り回り、話を聴き、ひとりになって考えることが面白くて、嬉しくて、楽しくてたまらないのである。そのあたりの心の動きが読者にも伝わってきて、それがこの本を面白くしている。

たとえば本書には、いたるところにユーモアがある。
私が虚をつかれたのは、例によって著者が危険な体験を問うたとき、 「最も危険な一瞬はプロポーズするときだった」という答えが返ってきたくだりである。
また、テスト飛行中のコクピットの中に熱風が吹き込んできて、「よくフライにならなかったと思う」と語ったパイロットがいる。聞いたとたんにニヤリとしたくなるが、すこし理屈をいうと、このフライは英語ではfry(油で揚げる)である。それをfly(飛ぶ)にかけた洒落を意図したものかどうか。日本語なら、どちらもフライだから問題あるまいなどと考えさせられたりする。
さらにヘリコプターのエンジンが停まって、駐車場に降りたパイロットの話。「警官がとんできて、ここは着陸してはならんと言う」
私も昔、アメリカ人のパイロットからヘリコプターが故障して不時着したときの話を聞いたことがある。
「アリゾナの砂漠に降りて、警察に逮捕された」とは、いささか大げさで、半分は冗談だったのかもしれぬが、当時はアメリカにも「飛行場以外の場所で離陸または着陸してはならない」という規則があったからに相違ない。同じ規則は今も、アメリカ航空法を真似た日本の航空法に残っているが、本場の方はとっくに削除してしまった。そんな規則はパイロットや航空機が信用ならない時代の遺物であると同時に、ヘリコプター本来の特性を阻害するという見識からであろう。また、この本の中で、著者はよくお酒を飲んでいる。いかにもおいしそうな飲みっぷりで、うらやましい限りである。
私もお酒は好きで、だんだん杯が重なってくると急に頭がよくなったような気になるが、やがて意識をなくして眠りこんでしまう。ところが著者は、旅先でパイロットたちの話を聴き、お酒を飲みながら食事をして、ホテルに戻ると、ときには明け方まで、その日の話題を整理し、記録する。好きでなければできないことだが、その努力がこの本に結晶したわけである。私自身も、この次はぜひ見習いたいものと、高望みを抱かずにはいられない。


こうして飛行機とユーモアとお酒という三つの題材がそろえば、話として面白くないはずがない。その三題噺によって、本書は、著者の会ったパイロットたちがいかにして免許皆伝の悟りに達したか、その悟りの境地がいかなるものであったかを、誰にでも分かりやすく、あざやかに語りつくしているのである。(西川 渉、地域航空総合研究所所長、1992)

【追記】
往時、加藤寛一郎先生には大変ご厚誼にあずかり、地域航空総合研究所としてもいろいろご教授をいただきました。それに伴ない、忘れられない想い出も多々ありますが、長くなり過ぎますので、いずれ改めて書くこととし、ここに厚く御礼申し上げます。(西川 渉、2014.5.2)


(表紙へ戻る)
