<本のしおり>
ゴリラとヒトの家族 『サル化する人間社会』(山極寿一、集英社、2014年7月30日刊)を読んだ。久しぶりのサル学だが、やっぱり面白い。
昔はよくサル学の本を読んだ。最初は『高崎山のサル』(伊谷純一郎、光文社、1954年刊)だったような気がする。高校生か大学初年級の頃だったか。今その本が手もとにないのは、父の書棚にあったものかもしれない。
サル学については、いうまでもなく京大霊長類研究グループをつくった今西錦司が筆頭である。ただし、この先生の著作は
『私の霊長類学』(今西錦司、講談社学術文庫、1976)
『自然学の提唱』(今西錦司、講談社、1984)くらいしか読んでいない。
愛読したのは河合雅雄で、手もとにある本を列記すると、以下のようになる。
『ゴリラ探検記(上)』(河合雅雄、講談社学術文庫、1977)
『ゴリラ探検記(下)』(河合雅雄、講談社学術文庫、1977)
『サルの目ヒトの目』 (河合雅雄、平凡社、1980)
『森林がサルを生んだ――原罪の自然誌』(河合雅雄、1979)
『霊長類学への招待』(河合雅雄、小学館、1984)
『人類進化のかくれ里――ゲラダヒヒの社会』(河合雅雄、平凡社、1984)
『望猿鏡から見た世界』(河合雅雄、文化出版局、1986)
『学問の冒険』(河合雅雄、1989)
『人間の由来〈上〉』(河合雅雄、小学館、1992)
『人間の由来〈下〉』(河合雅雄、小学館、1992)
『進化の隣人――サルとの対話』(河合雅雄、毎日新聞社、1992)
『サルからヒトへの物語』(河合雅雄、1992)そして河合雅雄以外の人では
『子殺しの行動学』(杉山幸丸、北斗出版、1980)
『野生チンパンジーの社会』(杉山幸丸、講談社現代新書、1981)
『ゴリラ――森に輝く白銀の背』(山極寿一、平凡社、1984)
『サル・ヒト・アフリカ』(伊谷純一郎、日本経済新聞社、1991)
『サル学の現在』(立花隆、平凡社、1991)などがある。
しかし、この一覧の刊行年から見て、1990年代初め以降はサル学を読んでいないことが分かる。つまり、ほぼ20年ぶりにサル学に触れたのだった。

サル学はいつ、どのようにして始まったのか。『サル学の現在』で、伊谷純一郎が面白い話をしている。1948年頃、今西錦司が野生のウマ、川村俊蔵が野生のシカを対象とする調査研究をしていた。あるとき、この2人に伊谷を加えた3人で宮崎県都井岬へゆき、野生ウマの社会構造を調べていたところ、100頭ばかりのサルの群れが目の前を通り過ぎた。
「群れには、おとなや子ども、オスやメス、いろんな個体がいて、いろんな声を発し、お互いにコミュニケーションを取り合って」いた。「その社会の複雑さ、活発な行動、多彩なコミュニケーション。……多数の個体からなる群れが、あるまとまりを保ちながら移動していく」。そのありさまを見て、3人はウマやシカにくらべて「サルの方が、ずっと高度な社会構造をもっている」ことに気がつく。
「その夜、三人で焼酎をくみかわしながら、お互いに感激を語り合った……そのとき今西さんはウマ、川村さんはシカをやっていた……これだけでは……馬鹿になる。サルを入れよう」ということになったとか。

では、サル学とは何か。サルではなくて、人間を究明するための学問にほかならない。
「人間はどこから来たのか。ヒトがサルから進化したというのはどういうことなのか。いつどこで、どのようにしてサルはヒトになったのか。ヒトになったサルと、ヒトになれなかったサルとのあいだにはいかなる違いがあったのか。このような問いに答えようと思ったら、ヒトはサルに学ぶしかない」と『サル学の現在』はいう。
ここで取り上げる『サル化する人間社会』の著者も「私は人間とは何かということを探ってきました。研究対象はゴリラです。私は人間から一歩離れて、人間の社会を眺めています。人間の鏡であるかのようなゴリラを通して、人間の本性を探っているのです」
そこから「人間の人間たるゆえんは『家族』にある」という結論にいたる。ほかの動物には「人間のような家族」はない。トリやオオカミやサルが繁殖期にだけ、つがいになって子育てをする時期があるが、人間のように夫婦や子供や孫の関係が生涯にわたって続くわけではない。しかも、その起源は人間の文化や文明の発展によるものではなく、「初期人類が熱帯雨林を出て、草原で暮らすようになったころ」に始まる。
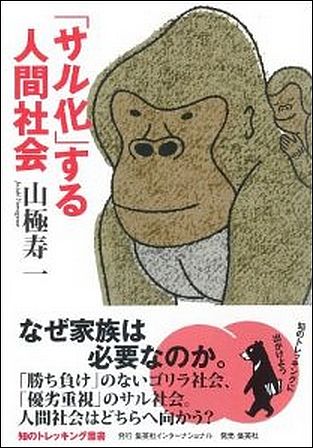

この結論だけを見れば、抽象的でよく分からないだろうが、本書には著者が40年近くアフリカ各地でゴリラの生態を観察してきた内容が具体的に書いてあって、分かりやすく面白い。
初めはゴリラに襲われ、ぶん殴られて大けがをすることもあったが、やがて、ごく間近で見つめ合う挨拶や、「グフーム」という唸り声による挨拶を交わすようになる。さらには、せまい洞穴で雨やどりをしているところへ若いオスのゴリラが無理に割りこんできて、著者の膝の上で眠ってしまうようになるまで、ゴリラの群れに受け入れられ、仲良くなり、信頼されるようになる。
こうして著者は、ゴリラと同じ行動をしながら、1頭1頭に名前をつけ、それぞれの関係を細かく観察してゆく。
そこから、ゴリラ社会には優劣の意識がないことが分かってくる。ニホンザルの社会にはボスを頂点とするヒエラルキーがあって、優位のサルは毛を逆立て、尻尾を上げて、自分の優位性を示しながら歩き回る。劣位のサルは、その視線を避けながら、恐れ入ったような態度を取る。
一方ゴリラには優劣の差異がなく、だれもが平等に暮らしている。ケンカをしていても第三者が仲裁に入り、きわめて穏便に引き分ける。そこには勝ちも負けもない。
食事をするときも、ニホンザルの場合、劣位のサルは優位のサルの前では決して食べ物に手を出さない。めいめいが散らばって、互いに目を合わせないようにして食べる。ところがゴリラは大勢が集まって顔を向け合って食べる。時には若いゴリラが年長のゴリラの食べ物をねだって、分けてもらったりする。あるいは年長のゴリラが食べ物をこまかくちぎって、ほかの仲間に分配する。つまりゴリラの社会には共存と共感と許容の仲間意識があるのだ。


似たような仲間意識が、おそらくは人類の祖先にもあったにちがいない。しかし類人猿と違うのは、熱帯雨林から草原へ進出した点にある。その環境は森の中とちがって、食べ物がいつでもどこでもあるとは限らない。
この過酷な条件の中で、人類は700万年にわたって食料確保のための努力を続ける。その過程で二足歩行、脳の発達、集団の生成、言語の誕生、社会の形成といった進化がなされたにちがいない。
具体的には、おそらく最初10〜15人の「共鳴集団」が成立し、そこから「家族」が生まれる。その家族がいくつか集まって、50人前後の「共同体」が形成され、さらに人数が増えると150人程度の集団になる。これが互いの顔と名前が一致して信頼できる上限で、人類学では「マジックナンバー」というらしい。
こうして家族から集落、集落から社会ができてゆくが、すべての基本となる家族は「人間の組織の中で最も古いものであり、今でも機能している社会形態です」「家族とは……人間性の根本を担う非常に重要なものです」「家族という集団に属していれば、その中で自分の位置は安定します」
「『私には家族がある』……という意識こそが、人間の心の安定の根底にあるもの」で「家族をなくして集団原理だけでやっていくことは、優劣を重視したサル社会に移行することだ」と著者はいう。
しかるに近年、その家族が崩壊に瀕している。おそらく多くの国でそうなのだろうが、日本でも夫婦別姓だの事実婚だの婚外子だのと、わざわざ人為的に、法律をつくってまで家族を壊してゆこうとする動きが国会議員の中にも出てきた。この連中は、人類が700万年もかけてつくり上げてきた人間社会をゴリラ以前のサル社会にまで引き戻し、貶めようとしているのである。


……というだけで終わっては淋しい文章になってしまうので、ゴリラの外見からは想像できないようなやさしい情感を描いた著者のエピソードをつけ加えておきたい。
子供のときに知っていたタイタスというゴリラに、26年ぶりに出会ったときの話である。「タイタスは、当然ですが、ずいぶん老けていました。動作はゆっくりしていて、目に光がありません。……私には気づいてくれませんでした」
「あきらめきれなかった私は、三日後にもう一度タイタスに会いにゆきました。……驚いたことに、私を見るとタイタスはまっすぐこちらに向かってきました。そして五メートルほどの距離で立ち止まると、腰を下ろして私を見つめてきました」
「タイタスの顔が徐々に変わり始めました。……若い表情になったのです。顔につやが出て、目が輝き始めています。私は……『グッ、グフーム』と挨拶しました。すると、タイタスも『グッ、グフーム』と答えました」
「次にタイタスがとった行動は、両手をあげて仰向けに寝転がることでした。小さいころのタイタスの寝相そのままでした。子どもならではの寝方です」。おとなのゴリラはこんなことはしない。
さらに、このゴリラは「グフグフグフ」と笑いながら、近くにいた子どものゴリラと取っ組み合って遊び始めた。「このとき私は気がつきました。タイタスは子どもに戻っているのだ、と。タイタスは私の顔を見て、思い出すうちに、昔の自分に戻ってしまったのでしょう」
「人間のように言葉を持たないゴリラは、心だけでなく体全体で過去に戻るのかもしれません。……胸がいっぱいになりながら、私はタイタスとの再会を終え、山をおりました」
(西川 渉、2014.9.3)
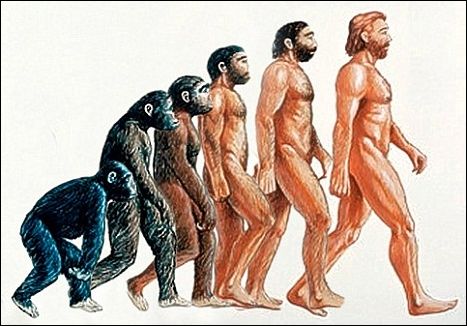

(表紙へ戻る)
