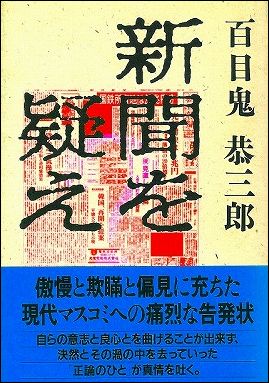<本のしおり>
百の目をもつ鬼 昔、といっても30年前に過ぎないが、『風の書評』(風著、ダイヤモンド社、1985年)という本が出た。週刊誌に「風」という筆名で連載した書評を集成したもので、3年後に『続 風の書評』も刊行された。この続篇では覆面をとった著者が、実は百目鬼(どうめき)恭三郎であったことを明かした。
この2冊は大変に面白く、10年後に再読したことが裏表紙の見返しに小さく記してある。そして今回三読、というよりも拾い読みをしてみると、不思議なことに気がついた。私の愛読してきた著者と風の評価がほぼ一致しているのだ。私が好きな著者は風の評価も高く、私の嫌いな人は風の評価も低い。つまり風の書評と私の好みがよく合うので、それとは意識しないまま、この書評集が面白いと感じたのであろう。
本というものは、いうまでもなく、著者と読者の波長が一致することで響き合い、読書の楽しみも増すのである。ついでにいうと、本の話とは何の関係もないが、りそな銀行という銀行がある。その「りそな」とはどういう意味か。先日そこから電話がかかってきたので尋ねたところ、答えはラテン語の響き合うという言葉だそうである。言われてみれば、なるほど英語にレゾナンス(resonance:共鳴)という言葉がある。恐らくは、それに「理想」の意味もかけているのではないだろうか。


話を戻して、風の書評の中から、私の好きな著者に関する項目を見てみよう。たとえば内田百閒『百鬼園随筆』については「そのコッケイ味が当時の暗い社会の慰謝となった……友人の借金の連帯保証人とされた著者が、女高利貸の家へかけあいに行き、まちがえて女教育家の家に入ってトンチンカンな応答をする、といったコッケイな話の底に、己れの人生観を持して譲らない著者のガンコな姿勢がある」
また開高健『オーパ!』は「解毒剤になるような楽しい本」であり、「釣りと景物、人間の心理などが渾然一体となった文学作品たり得ている」としたうえで「大自然の中での釣り紀行だから面白くなかろうはずはない」「不思議だらけのアマゾンの話を語るのに、開高ほどの適任者はいないだろう」「単調かつ過酷きわまりない旅……を独自の文明批評の面白さで引張ってゆけるのも開高ならではなのである」
向井敏『紋章だけの王国』については「読み出すと止められない……テレビのCMというものが明快にとらえられ、裁断されているからである」「これだけはっきりした輪郭で描いてみせられると、読者は知的興奮さえ覚えるのである。これこそ読んだかいがあったというものだ」
むろん私は、上の3人は長く読みつづけていたが、取り上げられた3冊も出版当時に読んだ覚えがある。

次に私の嫌いな著者について――。たとえば大江健三郎『同時代ゲーム』の場合、「評判がいいので読んでみたが、たいへん失望した。読む苦痛を強いるだけの作品とでもいうほかはない……低俗な劇画にありそうな、コウトウムケイの物語なのである」「アルコール中毒、偏執病者、淫乱症、性的倒錯者、といった連中が登場して描き出すイメージは……ただもうバッチイだけ」
私も若い頃は大江をよく読んだ。しかし猟官運動にも似た働きかけをしてノーベル賞を押戴いてからは「脳減ル症」を患ったのか、語彙も文体も出鱈目で、何が書いてあるのか、何をいいたいのか、意味不明の文章を書くようになった。文章というものは、まず相手(読者)に伝達することが基本の機能であって、その上で芸術的な味わいを加えたり、明晰な論理の筋を通したり、さまざまな工夫をこらすものである。
その基本を無視して、夢の中の譫言(うわごと)のような文字を書きつらねるなどは単なるひとりよがりにすぎない。風も大江について「年をとり、エラクなると……歯どめがきかなくなって、作品は暴走するものらしい」と書いている。
たまたま東大仏文に私の高校時代のクラスメートが2人いて、その1年か2年上に大江がいたはずだから、しばらく前の同窓会で2人に大江をどう思うか訊いてみた。それも同時にではなく、別々の場面で訊いたのだが、両人とも異口同音に嫌いと答えた。
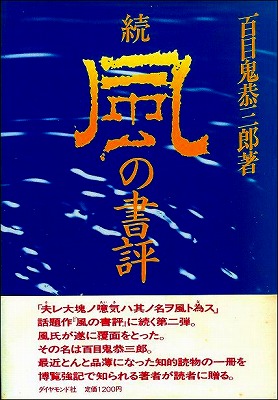

次に本多勝一『ベトナムはどうなっているのか?』について、風は「読むと大いに当てが外れる」と評している。「これは、日本の進歩的ジャーナリストというものが、いかに感情だけで動いているか、ということを知るにはいい本だ」
大岡信『百人一首』については「著者は本当に歌がよくわかっているのかどうか不安になってくる……はっきりいって、著者の知識はいささか杜撰のそしりを免れまい」。私も、この人の本は何冊か読んだが、どうもしっくりこない。こちらに詩歌のセンスがないせいだと思っていたが、必ずしもそうではないらしい。
加藤周一編『読書案内』は「失望した。……岩波新書やクセジュ文庫などの新書類と、文学全集、講座物の類をこき混ぜて、項目別に並べたにすぎない代物である……それに、おなじような入門書をやたらに並べているのも無責任だ。……それでいて……本当に便利な本が抜けている始末」「いったい、筆者はちゃんと多くの本に目を通して比較検討したうえで挙げているのか、と問いたくなってくる」
以上の4人は、いずれも朝日新聞に関係のある物書きで、最近はみんな歳をとったせいか、あるいは他界した人もいて、新聞紙面で見かけることは少なくなったが、それを評価する百目鬼も朝日の記者であった。長く学芸部に所属して、4人との間にも面識があったはず。にもかかわらず、こき下ろすことができたのは、風の筆名で『週刊文春』という朝日新聞の敵方に陣取ったからにちがいない。

余談ながら、これは筆者の好悪とは関係ないが、本田宗一郎『私の手が語る』について論じている中で「著者が開発、普及させたホンダに乗った暴走族の深夜の騒音によって、どれだけ多くの人が迷惑をこうむっているか」「彼らは交通規則を破るために走っているのである。オートバイを作る者は……いくらいじっても騒音が絶対出ないようなメカニズムを工夫すべきだろう」と書いている。全く同感である。
バイクはもちろん乗用車も市街地や静かな住宅地でレース場のような轟音をたてて走る輩(やから)が少なくない。必ずしも暴走族ではないが、あれほど腹立たしいものはない。あの音をなくす技術が、まさかないはずはない。ときどき、オートバイでぶっ飛ばすと「スカッとする」などというバカがいるが、その分だけこっちは頭痛がしたり、脈拍がはやまったりしているのだ。これは、音を消すと売れなくなるのかどうか、メーカーが消音技術をわざと使わないとしか思えない。自動車、オートバイ、スクーターについては法律で、高級乗用車なみの静かな騒音レベルを定め、轟音運転をしたものは警察でつかまえて、高額の罰金を取るようにしてもらいたいものである。

『風の書評』と前後して、百目鬼恭三郎は朝日新聞を退社する。それから半年余り経って『新聞を疑え』(講談社、1984年11月10日刊)が出版された。その中で、著者は在職中の31年間、何の役職にもつかず、「平記者」だったと書いている。
40歳を過ぎた頃、中学時代の友人がやってきて「おまえ、いま新聞社でどんな役についているんだ?」と訊かれ「ただの平記者」と答えると「何か悪いことでもしたのか?」と真顔でいわれたらしい。
といって、本当のことは書いてないから、理由は分からない。けれども本を読んでいて、優秀な書き手であることは分かる。社内でも「名文家」といわれたらしい。同時に「ヘソ曲がり」ともいわれたようで、自分でも「私は、ただ上役というだけでその人物に敬意を払う、というような真似だけは死んでもご免」と書いている。
その結果かどうか「社会部へ飛ばされた」。学芸部では読書面、連載小説、文芸時評などを担当して、人一倍の仕事をしていたから、新聞社にとってはマイナスになったはず、と書いている。読者にとってもマイナスである。
社会部で3年余りブラブラした後、調査研究室へ異動した。そこでも上役とのソリが合わず、しばらくして学芸部へ戻されたものの、いつのまにか「なまけ者」というあり得ないラベルを貼られていた。

つまり、新聞というものは、こういう集団によってつくられているのである。私などは単純に一騎当千のジャーナリストたちが持てる能力を充分に発揮して、精気溌剌と情報発信をしているのかと思っていた。ところが実際は同じ社員が足を引っ張り、伸びようとする頭を抑え、身のまわりのこぢんまりした安全をはかる……人間社会のどこにでも見られる集団――新聞社だからといって決して特別すぐれた会社というわけではないのだった。この本の表題が『新聞を疑え』となっているのは、どうやらそのあたりのことを指すらしい。
ところで、いま問題の「従軍慰安婦」が始まったのも同じ頃である。こんな莫迦げた問題を生み出す素地は、この本には書いてないけれども、当時の社内に充分あったことを察することができる。
朝日新聞が最初の捏造記事を載せたのは1982年9月2日であった。これが時と共に広がり、1990年代に入ると韓国でも問題が大きくなって、92年1月訪韓した宮沢首相は首脳会談で8回も謝罪をくり返した。翌93年には河野何仮死が強制連行を認める官房長官談話を発表し、捏造がばれた今もそれを取り消すつもりはないと開き直っている。こんな非国民が国会の議長というのだから、聞いて呆れる。早く引きずりおろすべきだ。
これらを受けて、96年には国連人権委員会が日本軍の「性奴隷」20万人という報告書を発表、2010年代になるとアメリカ各地に慰安婦の銅像が建ちはじめた。日本はありもしない無実の罪で世界中から辱(はずかし)めを受けることになったのである。
ここまで問題が大きくなる前に、朝日新聞はなんとかできなかったのか。というよりも、なんとかしようなどという人物は一人もいなかったに相違ない。たしかに、慰安婦問題が虚報や捏造であることが分かってからも、朝日新聞社内に訂正や謝罪の機運は生まれなかった。このことは、それ以前に書かれたはずの『新聞を疑え』からも読み取ることができるのである。
(西川 渉、2015.3.23)


(表紙へ戻る)