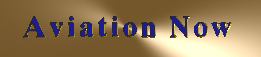<日本航空医療学会誌>
安全の構図
アメリカのヘリコプター救急は事故が多い。昼夜を問わぬ飛行が、営利を目的とする事業として自由競争の下におこなわれているからではないかと思われる。2012年末までの10年間の集計を見ても、事故の総数が119件、うち死亡事故が40件。3ヵ月に1件ずつ、10年間にわたって続いたことになる。死者の集計は見あたらないが、おそらく40件で100人前後となろう。
こうした状況を長年分析してきたシカゴ大学のアイラ・ブルーメン教授は、2012年秋のアメリカ航空医療学会で、次のような4項目の事故防止策を提案した。
- 現場救急は昼間のみとする。
- 現場着陸は、あらかじめ確認された場所だけとする。
- 使用機は双発機のみとする。
- パイロットは2人乗務とする。
すでにお気づきのように、この対策は、わがドクターヘリが現に実行している飛行方式と変わりがない。第4項が違うように見えるが、日本は整備士が同乗して、無線連絡、航法、見張りなど、副操縦士に相当する任務を果たしている。
とすれば、アメリカが多数の犠牲者を出しながら、ようやく見出した安全策を、ドクターヘリは初めから実行していたことになる。このことは密かな誇りとしてよいであろう。ただし、決して慢心があってはならない。いかに制度が良くても、それを運営する人間に油断があっては事故を招く。

アメリカとは逆に、カナダはヘリコプター救急が始まった1977年以来、35年間にわたって死亡事故ゼロの運航を続けてきた。気象条件の良くない北辺の地で、パイロットは2人乗務、使用機は計器飛行の可能な双発機を条件とし、離着陸の場所も限定していた。さらに費用は州政府が負担する。これらの条件もドクターヘリとよく似ている。
ところが最近、深夜の飛行場から患者を迎えにゆこうとしたオンタリオ州の救急ヘリコプターが離陸直後に墜落、乗っていた4人が全員死亡した。事故調査の最終結果はまだ出ていないが、これまでのところ機材の故障は見あたらない。長年の無事故に安心しきった慢心があったのではないか。

日本のドクターヘリは運航開始から12年、幸い死亡事故はないけれども、危険な要因はあらゆるところに潜み、われわれのスキをうかがっている。
(西川 渉、日本航空医療学会誌2013年8月刊掲載)
(表紙へ戻る)