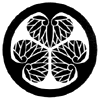
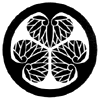
今さら誰もが知っているような古典的名作『最後の将軍』(司馬遼太郎著、文芸春秋刊)を取り上げるのは、今年初めNHK大河ドラマ「徳川慶喜」がはじまった機会に、25年以上前に読んだ本書を読み返して、気がついたことがあったからである。
というのはNHKがなぜ今頃、大政奉還をテーマにしたドラマを1年間にわたる国民的放送番組にしたのか。おそらくは現今の行政改革や金融改革に対する一つの考え方を司馬遼太郎の名前を借り、時代を変えたドラマに託しているのであろう。それも、改革の方向はかくあるべしという手本を見せようとしているのではないのだろうか。
ドラマの3回目、いよいよ浦賀沖に黒船4隻がやってきて、米国を代表するペリーが日本の開国を要求する。1853年6月のことだが、これは、いうまでもなく現今のさまざまな自由化要求に相当する。それに対して、幕府は諸大名に火消し装束で待機するよう指示を出す。ところが敵が攻め込んできているのに火消し装束とは何事か。戦かうのか戦かわんのか、はっきりせよというのが大方の世論となる。
慶喜の父、徳川斉昭に至っては「老中は年がら年じゅう議論ばかりしておって、何もしようとしなかった。今になって慌てふためいておる」といって幕閣を批判する。今の永田町や霞ヶ関界隈にそのまま当てはまる評言であろう。
その老中では「徳川の御代はすでに250年間、一度も戦( いくさ)がなかった。われわれは誰も戦を知らぬ。このまま戦っても負けるだけだ」という意見が大勢を占める。といって敵のいう通りになってしまっては、こちらの「面目丸つぶれ」。閣僚たちの考えることは面目だけなのであった。
彼らは取りあえずアメリカ大統領の書簡をあずかり、1年後に返事をするということでその場を取りつくろうが、1年たって再度黒船がやってきたときにどうするか、何か目算あってのことではない。現在もよく見られるような、問題の先送りにすぎなかった。
そのだらしない有様を見て、1年後の黒船来襲から国を護るために海防参与となった斉昭は「この250年来、無駄のかたまりとなってしまった幕府の仕組みを手荒く変えねばならぬ。あとは、この国を一気によみがえらせるのじゃ」と檄を飛ばす。日本の現状にも通じる台詞であろう。
こうした中で、慶喜はまだ将軍にはなっていないが、黒船を自分の目で確かめたいと思う。変装して浦賀へ出かけようとすると、幕府から一橋家へ派遣されている役人たちに押しとどめられる。代わりに役人の1人が画板をもって現地へ行き、黒船を写生することになった。
しかし写生は目明の盲が描いたような絵になっていて、横からのぞきこんだ人に注意される。「この遠めがねでよくご覧なさい」といわれて見ると、舷側の砲門が開いている。いつでも火蓋が切れるような戦闘態勢――当時の言葉では「喧嘩腰」なのである。おまけに、戻ってきて報告する中で、慶喜に黒船はどのくらいの大きさかと訊かれて、「こーんなに大きうございました」といって両の腕を広げるばかり。要するに具体的な実態が何にも分かっていないのであった。
同じように今の日本も、長いこと鎖国状態を続けてきた。戦(いくさ)すなわち競争はすっかり忘れているところへ、米国を初めとする先進諸国が市場開放や貿易の自由化を要求し続けてきた。その要求にいよいよ耐えきれなくなって、行政改革や金融改革に手を着けはじめたが、まだ議論だけしかしていないのに早くも混乱が起き始めた。逆にいうと、やると決めたからには素早く、しかも徹底して実行する必要があるはずだが、それをぐずぐずした議論と恰好だけで糊塗しようとしたために、「ビッグバン」などという言葉だけが先行し、却って混乱を招いたのである。
ドラマの中で「このごろ都にはやるもの」という前置きはなかったけれども「火付け、強盗、人さらい、夜鷹、おひねり、間男野郎、小判の好きな御老中」といった戯れうたが出てきた。これも今の日本にそっくりではないか。
当時の江戸幕府は言い換えれば「徳川政権」であり、今の政府機関である。そこに老中といった閣僚がいて、選ばれた大名諸侯がこれを勤める。また、それぞれに省庁のような役割を分担し、官僚としての武士が問題の処理に当たる。
しかし、この体制が250年もつづき、黒船に象徴されるような外圧が高まるにつれて制度のほころびが出はじめる。現実の変化に対応できなくなり、放火、強盗、殺人、不倫、接待、贈収賄などの不正腐乱が猖獗をきわめ、ついに最後の首相となった徳川慶喜が周囲の反対を押し切り、英断をもって大政を奉還する。
これがフランス革命やロシア革命のような流血の様相を呈さなかったために、単なる政権交替のようにも見える。けれども、そうでないことは明治維新によって国家の構造そのものが大きく変わり、憲法を初めとする法律体系や政府組織がすっかり改められたことからも分かる。まさに世界史上類のない無血革命であったことは多くの論説が一致するところである。それが今の日本にも必要であることを、あの大河ドラマは訴えようとしているのではないのか。
航空界もまた、日米航空交渉の合意が成立した。これは単に不平等の解消が実現しただけではない。新しい維新の時代に入ったのである。
果たして平成維新はうまく無血革命を成し遂げられるだろうか。
(西川渉、週刊『WING』紙、98年2月11日付掲載)