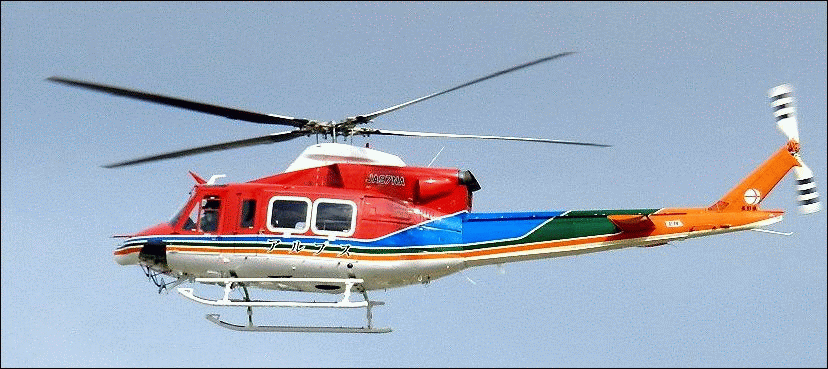<防災ヘリコプター事故>
無念の志を生かすには 長野県防災ヘリコプターの事故について、発生の3日後に『航空情報』誌の依頼を受けて書いたのが下の文章である。事故の状況や原因など書いているときは殆ど不明で、今となっては見当違いのところもあるが、ここにはそのまま掲載しておきたい。

去る3月5日、長野県防災ヘリコプターが墜落し、乗っていた消防航空隊の9人全員が死亡するという惨事となった。同機はベル412EP双発機(標準15席)で、午後1時半頃、松本空港を離陸、東へ17kmほどの鉢伏山へ山岳遭難の吊上げ救助訓練に向かう途中だった。ところが離陸後15分くらいで連絡が取れなくなり、無線の呼びかけにも応答がなくなる。事故機が見つかったのは、ほぼ2時間後。機体は仰向けになって大破していたが、発火の跡は見えなかった。
当日の天候は薄雲がかかった程度で風速5m以下。現場付近もおだやかな気象だったという。そんな中で、なぜこんなことになったのか。
初めのうちは、不意の山岳波やダウンバーストのような激しい下降気流によって叩き落とされたか、何らかの不具合が機材に生じたか、電線もしくは索道に衝突したか、あるいはドローンのような飛翔体と接触したか、などの原因が考えられた。しかし3日ほど経ったところで、機体の落着地点から斜面の上方数十メートルにわたって滑り落ちてきたような跡があり、その先のカラマツ林にローターで切断したような痕跡が見つかった。
また、事故機に乗っていた消防隊員の1人がヘルメットに小型のビデオ・カメラをつけていた。その映像によれば離陸からしばらくは正常な飛行だったが、墜落までの最後数秒間に画面が大きく乱れ、複数の隊員が倒れているシーンで途切れていたという。
こうしたことから本稿執筆(3月8日)の時点で推定されるのは、何らかの乱気流によって高度が下ったか、訓練を受ける隊員を木々の間にホイスト降下させようとして高度を下げ過ぎたか、ということである。そのため主ローターか尾部ローター、もしくは両方が樹木に当たったのではないか。特に尾部ローターが破損して方向操縦が効かなくなると機体が激しく旋転し、仰向けに落着することが多いので、事故機の状態とも合致する。
なお、事故機のホイスト・ケーブルがいかなる長さだったかは、長野消防航空隊で初めから分かっていることだが、ちなみにスイスのエア・レスキューREGAは、標高4,000m級の高山が連なるアルプスの山岳地で遭難者の救助をおこなうため、通常90mのホイストを使っている。さらに垂直に切り立った断崖の途中で立ち往生した登山者を救出するときは、ケーブルを継ぎ足して最長200mまで伸ばすこともある。無論このときのパイロット、ホイスト操作員、それにケーブルの先端にいる救助隊員の技術力や胆力は並み大抵のものではない。誰もが簡単にできることではないが、徹底的な訓練を重ねた結果である。
もうひとつ、最近は自動車にもドライブ・レコーダーやイベント・レコーダーといった記録装置が取りつけられ、事故発生時の映像はもとより、速度、ブレーキ操作、衝撃度などを記録するようになった。これらのデータは事故調査にあたって、迅速かつ客観的な証拠として使うことができる。
そこでヘリコプターにもフライト・データ・レコーダ(FDR)を取りつけるべきではないか。旅客機ほどの重装備ではなくとも、軽便なFDRを、特に消防、警察、ドクターヘリなどの緊急任務に当たる機体には必須の装備といっていいかもしれない。これらは、事故調査に資するばかりでなく、その後の事故防止策を考える上で重要な役割を果たすこととなろう。
雪の山岳地で倒れた長野消防航空隊員たちの無念の志(こころざし)を無にしてはなるまい。
(西川 渉、航空情報2017年5月号掲載)

【追記(2017.4.26)】
上の事故から50日を経過したが、事故調査の結果はまだ公表されていない。しかし、この間に、事故機はホイスト操作をしていたわけではなく、異常な低空飛行をしていたらしいことが伝えられるようになった。とすれば、何故ローターが樹木に当たるほど低空を飛んでいたのか。一緒に乗っていた整備士その他の隊員たちが何故パイロットに注意を呼びかけなかったのか。チームワークが大切なはずの緊急機関にあって乗員相互の意思疎通はどうなっていたのか。そのあたりの疑問は残ったままである。早く解明して、次の安全策に生かされるよう希望する。
(表紙へ戻る)