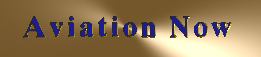<PICU>
ジェノアの小児救急

イタリアのジェノアは地中海有数の港町である。その明媚な海岸を見おろす丘の斜面に大きな建物がいくつも並ぶのは、戦前からの由緒あるガスリーニ小児病院である。その病院へカルロ・ベルリーニ先生を訪ね、イタリアのヘリコプター救急についてレクチャーを受けたのは昨年夏のことであった。
イタリアの救急ヘリコプターは、現在47ヵ所の拠点で活動している。日本の面積に当てはめるならば60ヵ所。しかも10年ほど前までは20ヵ所ほどしかなかったから、その急増ぶりはめざましい。
何故そんな急に増えたのか。それがベルリーニ先生を訪ねた目的のひとつだった。
イタリアの新しい救急制度が国の法律によって体系づけられたのが1992年で、さほど昔のことではない。96年には、118番の救急電話を受けてから救急治療開始までの時間を都市部で8分、山村部で20分以内という基準が示された。これでヘリコプターを使う必然性が生じた。むろん救急車は従来通り使用するが、地上では間に合わない場合にヘリコプターで補完するのである。
といって、財政的な裏付けがなければ何もできない。そこへ1998年、税制が改められ、国税を減らして、州政府の徴収する地方税を増やすことになった。しかも地方税の増収分はほとんど、州政府が実施する医療政策に充てることになり、救急ヘリコプター導入の財源にも目途がついた。
もうひとつ、イタリアは昔から都市国家が乱立してきた歴史を持つ。この競争意識は今も州と州との間に残っており、どこかの州が救急ヘリコプターを導入すれば、「よし、こっちも……」ということになるらしい。
こうした法規、財政、競争といった3点を基本とし、その他の条件もうまくかみ合って救急ヘリコプターが急増した。ただし余りの急展開のために、全国20の州がそれぞれの実情に合わせて思い思いのシステムを組み立てており、標準的、統一的な基準ができていないという新しい課題も生じている。
それにしても、日本の現状に照らして、いささかうらやましい思いで、ベルリーニ先生の話を聴いたものである。

パソコン画面を使ってレクチャーをしてくれたベルリーニ先生
さて、先生は本来、小児医療もしくは小児救急が専門である。話題は当然その方へ移るが、この病院でも毎年多数の小児患者を受け入れる。救急車で送られてくる子供はもとより、屋上にヘリポートがあって、ヘリコプターでも搬送されてくる。
そのヘリコプターを使った未熟児の救急搬送に関して、ベルリーニ先生には一つの苦い経験がある。2006年1月14日午前10時頃、このリグリア州ジェノアのガスリーニ小児病院に隣のトスカーナ州ポントレモーリの病院から早産した新生児の救急依頼電話がかかってきた。ポントレモーリはジェノアから東へ80kmほどの地点である。
しかし、ガスリーニ病院はベッドがいっぱいで、新しい患者を受け入れることができない。やむを得ず、ピサのサンタ・シエラ病院へ搬送することにした。ピサはポントレモーリからさらに東南へ海岸沿いに100kmほどのところにある。
患者は23〜24週で生まれた双子であった。通常40週の妊娠期間に対して、胎内に半分ちょっとしかいなかった未熟児である。専門病院でなければとても対処できない。ベルリーニ先生が電話を受けたときは、まだ1人目が生まれたばかりだった。ポントレモーリの医師は2人目が生まれる前に、母親ごと高度医療の可能な病院へ搬送することを考えたのである。
いわゆる「母体搬送」だが、ヘリコプターの準備をしている間に、2人目も生まれてしまった。
先生は普段、救急出動にあたって、ジェノア国際空港に拠点をもつ消防ヘリコプターを使用する。ガスリーニ病院までは、飛行時間にして6分。出動依頼から8分後に、アグスタ・ベルAB412が屋上ヘリポートに到着した。冬のことで寒くはあったが天候は良く、機は80km余りを25分で飛び、先方のポントレモーリ病院上空に到着した。
ところが、ヘリポートがない。以前は病院のそばに草地があって、そこを使って未熟児の搬送をしたことがある。ところが今では駐車場に変わってしまい、車がいっぱいで着陸できない。
「そのことを、消防もわれわれも知らされていなかった」先生はわずかに不満の表情を見せる。
ヘリコプターはしばらく病院の周囲を旋回して、着陸場所を探した。パイロットは最終的に、やや離れた小川のふちを通る細い道に着陸する決心をした。道の周囲には立ち木が多く、誰もが不安を感じたが、やむを得ない。ヘリコプターは数分後に無事着陸し、医療チームは大急ぎで病院へ駆けこんだ。

ガスリーニ病院の救急病棟屋上にあるヘリポートと地中海
生まれたばかりの双子は、体重が480gと520gであった。直ちに小さな気道に挿管し、空気を送りこみながら、インキュベータに収容した。ここからピサまでは飛行時間にして約30分。赤ん坊の状態が安定するまで25分ほど待ち、インキュベータをヘリコプターに乗せた。
ピサまでの飛行中は何の問題も起らなかった。脈拍も正常で、体温の低下もなかった。ヘリコプターはできるだけ低く、高度300m以下で飛び続け、27分でピサのサンタ・シエラ病院に到着した。赤ん坊は2人とも安定した状態にあった。その小さな患者を先方へ引渡すと、ヘリコプターは50分ほど飛んでジェノアへ戻った。しかし、それから36時間後、双子の2人は集中治療の甲斐もなく死亡したという知らせを受けた。
体重2,500g 未満の新生児については近年、急速に医療技術が進み、正常に生育できる可能性が高まった。しかし出生体重1,000g未満の未熟児では、まだまだ問題が大きい。そのうえ如何に早く適切な治療をほどこすかという課題が残る。ガスリーニ病院のように、そのための施設や医療スタッフがそろったところでは、異常分娩にも直ちに対処できる。
しかし、今回のようにヘリコプターを使っても本格治療までに1時間以上かかるような場合、ましてや体重500g前後の双子という悪条件が重なると、事態はきわめて深刻になる。世界保健機関(WHO)も、体重500g未満、妊娠22週未満の未熟児については、生存限界以下とみなしている。
しかし、こんなとき母親や家族は気が動転し、対応する医療関係者もあせりを感じる。誰もが、何とかして助けたいと思う。けれども、しばしば異常分娩に立ち会っている医師や看護師は、死亡の危険性がきわめて高いことをよく知っている。といって何もしないで放置するのは無論のこと、いい加減な処置ですますことはできない。
だが、ついに赤ちゃんが死ねば、家族は医師に対して、異なった感情を持つようになる。その間を取り持つのは、お互いの倫理感であろう。どこかで我慢せざるを得ない。それでも我慢できないときは、イタリアの場合、牧師さんなどの仲介者を立てて話し合う。それでも解決しなければ医療倫理委員会といった公的な機関にゆだねざるを得ない。

地中海に面してジェノアの丘の斜面に建つガスリーニ小児病院
ベルリーニ先生はそこまで話を進めたうえで、そんな事態に立ち至る前に、実務的にも感情的にも効果があるのは「やはりヘリコプターでしょうね」と話を戻した。未熟児の赤ちゃんを、ヘリコプターによって適切な病院へ迅速に運ぶことができれば、家族の眼から見ても、これは最高の緊急手段を取ったものと納得することができる。もとより形だけではなく、実際に助かる例も多いのだ。
「それにしても」と先生は続けた。「1世紀(100年)も生きる人がある一方で、1日で死ぬ赤ちゃんもいる。人の誕生、人の一生、人の死亡は、この世の神秘ですね。誰ひとり同じではありません。それでいて世の中の調和が取れている。そうした生命の本質や生命の神秘は、如何に未熟児といえども、生命の尊厳すなわち生きる権利を絶対的に肯定しているものと思います」

ガスリーニ小児病院構内の道しるべ
(西川 渉、「HEM-Netグラフ」2008年夏号所載、2008.11.26)