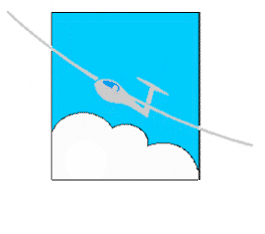
1998年11月25日、わが国有数のグライダー教官、丸伊満氏がオーストラリアでグライダー競技中に接触事故で亡くなった。このことについて、最近ある人からイーメールを貰った。内容は飛行の安全に関することだったが、メールを読んでいるうちに、むかし丸伊さんに会ったときのことを想い出し、『風を聴く』という本のことを思い出した。
以下の文章は1993年夏、今から5年以上前に書いたものだが、丸伊さんのご冥福を祈りつつ、ここに掲載しておきたい。
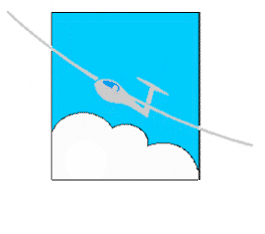
この8月7〜8日の2日間、北海道滝川市で恒例の「スカイレジャー・ジャパン」が開催される。空のスポーツを愛する多数の人びとと、グライダーや熱気球、パラグライダー、ウルトラライト、ヘリコプター、軽飛行機などが大集合する空の祭典である。
グライダーは昔から空の貴族といわれてきた。空力的に最も適合した美しい姿で、動力を使わずに、悠々と空を舞う様子は、あたかも宮廷音楽に合わせてワルツを踊る貴婦人のようにも見える。だから、その貴婦人がやってきたときは、ジャンボ機ですら道を譲らなければならないというルールがあるし、上昇気流がなくなればいつでも地面に降りて、ゆっくりと羽根を休めることも許されているのだそうである。
そうした空の貴族への敬愛ぶりを最も忠実に制度化しているのが英国、または英国系の国々で、そういう国ではグライダーに乗るのにライセンスは要らない。グライダーというのは空のスポーツであって、野球やサッカーをするのに免許が要らないのと同じ理屈である。
しかし日本では免許制だから、イギリスのグライダー・チャンピオンが日本にやってきてデモ飛行などをしようとすると、これは大変なことになる。普通の飛行機のように免許の書き換えをしようにも、その根拠になる免許がないし、さればといって正規の手続きで試験を受けるには呆れるほどの時間と費用と手間がかかる。
短期間の旅行者がそんなことをしている暇はないから、外国人が日本で飛ぶのは非常にむずかしい。利根川の河川敷などで活動しているグライダー・クラブにも、ときどき外国人がやってきて「乗せてくれ」などと言うそうである。むろん自分で操縦するつもりなのだが、免許がないから気軽に飛ぶことはできない。結局は諦めてもらうほかはないが、航空というものに対する彼我の考え方の違いが如実に示されている。
つまり日本の場合は、航空を特別扱いしすぎているわけで、それほど閉鎖的な殻の中に閉じこめてしまわなくてもいいのではないか。グライダー人たちにいわせると、同じ操縦をするのでも、自分たちは金をかけて飛んでいる。金を貰うために飛んでいる事業用操縦士とは違うんだというのである。ライセンスが要らないのも、全ては自己責任だからである。日本はまだそこまでは行かないけれども、お役所に責任を取ってもらう積りはないという気概を秘めていることは確かである。
とはいえ、そこにはおのずから一定の約束ごとがある。どんなスポーツにも上手下手の差異があり、その差異から競争心が生まれるのは当然で、グライダーの場合も盛んにスピード競争がおこなわれる。
速度ばかりでなく、目に見えない上昇気流をつかまえて、どこまで高く昇るか。その上昇気流を飛び石伝いに捉えながら、どこまで遠く飛んでゆけるか。動力や計器類に頼らず、人間本来の直感力と判断力と決断力だけで、そうした困難を達成できる技能を身につけなければならない。
そのような一人前のグライダーマンとみなされるためには航続距離500km、目的地を定めた飛行距離300km、獲得高度5,000mという3種類の記録を達成する必要がある。それぞれを国際滑空記章で「ダイヤモンド章」といい、三つそろった「スリー・ダイヤ」を獲得することはグライダーマンたちの大きな目標になっている。
そのダイヤモンド章獲得のためにオーストラリアへ出かけた奮闘の記録が、瀬尾央著『DIAMOND GOAL』(API、1993年7月刊)である。「航空情報」誌の連載をまとめたもので、写真家らしく、全頁にわたってみごとなカラー写真が掲載されている。いずれも著者自身が撮ったもので、自分が操縦しながら、自分の飛んでいる姿を、自分で撮影した写真である。しかも急旋回や宙返りの場面もあって、グライダーでそんなことが出来るのかと思う人は、本書をご覧いただくほかはない。
文章は、これもきびきびした「口調」で、日本のせまい空域を脱し、オーストラリアの無辺の空で、往復300kmのクロスカントリーでダイヤモンド章を取ってきた体験談が語られる。その飛行ぶりは、わずかな経験しかないのに教官やチャンピオンも舌をまくほどの玄人はだしであったらしい。
私も、いつぞやグライダーに乗せて貰ったことがある。動力つきのモーターグライダーで、離陸のときは普通の飛行機のようにエンジンを回しながら飛び上がり、上空に上がるとエンジンを切って滑空に入る。
エンジン音がやむと急に辺りが静かになり、風の音が聞こえてくる。ざーッというような音だが、グライダーマンたちは、この音によって滑空速度を判断するらしい。
速度の判断はグライダーの場合、3種類の方法でおこなわれると聞いた。ひとつは機体の姿勢で、たとえば機首を下げると速度が速くなる。つまり、わずかながら未来の速度を予知することになる。また速度計にあらわれた数値は、これは過去の数値だそうである。
したがって現在速度は、風の音で判断する。耳をすまして自然の音を聴く。このような風の音が聴けるようになるための手ほどきをしてくれるのが、丸伊満著『風を聴け』(酣燈社、1992年9月刊)である。グライダー・パイロットのためのフライト・マニュアルで、著者は学生時代からグライダーに親しみ、現在は滝川市の職員である。
この町で今年のスカイ・レジャージャパンが開催されるのも、この人が長年にわたって滝川市をスカイ・スポーツのまちに育て上げてきたからであろう。
グライダーのための滝川滑空場が開設されたのは10年ほど前のことであった。その滑空場での訓練から生まれたのが本書である。すべては著者みずからの飛行と教育の体験にもとづいて書かれている。
本書には図版も多い。特に操縦者自身が操縦席から見た外界――曳航機や地平線や雲や山のもようが、自分の操縦桿の位置や、計器盤の上の速度計、昇降計、滑り計などの指針と共に描かれている。しかも各計器の針やボールの位置が図版の一枚ごとに、実際の作動通りに描かれていて、この多数のイラストもすべて著者自身の手になるというから驚く。
初心者にはまことに分かりやすい教科書である。筆者の勤め先でグライダーに乗っている女流愛好家も、操縦を習いはじめた当初、まだ本書の出る前であったが、丸伊教官の訓練用のノートをコピーさせてもらったそうである。つまり著者が、いわば私家版としてつくり、その生徒たちがコピーをして教科書代わりに使っていたノートが、いま誰でも入手できる本になった。著者の技術と知識と知恵が、めでたく公けのものになったということができよう。

グライダー人口は、いま日本では5,000人だそうである。そのうち冒頭に述べたスリー・ダイヤモンドの保持者は12人だが、これらは、やがて大きく増加する気配である。というのは、オリンピック委員会がすでにグライダーをスポーツ競技のひとつとして認めているからで、いずれはオリンピック大会で滑空競技も地上の競技と同じように扱われるはずである。
そのときは、もっと多くの人びとが、グライダーという空力学の象徴のような美しい航空機を駆って、空のスポーツを楽しむようになるであろう。そこから日本の航空界にも新たな発展がもたらされるに違いない。
(西川渉、『日本航空新聞』1993年7月29日付掲載)
 (「本頁篇」目次へ戻る) (表紙へ戻る)
(「本頁篇」目次へ戻る) (表紙へ戻る)