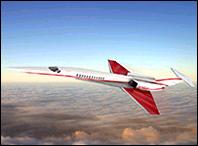<NBAA>
超音速ビジネス機
超音速飛行60周年
人類の移動速度は文明の発展とともに進歩してきた。徒歩や駕籠の時代から騎馬や馬車へ進み、自転車を経て自動車や汽車のような動力を使うようになる。やがて地面を離れて一挙に飛行速度が増し、ついに音速を突破したのは今から60年前のことである。
1947年10月14日アメリカ空軍のチャールス・イエガー大尉は、超音速実験機ベルXS-1に乗りこみ、モハービ砂漠の上空で母機から発進して「音の壁」にいどんだ。ロケット・エンジンによって機は天空高く12,800mまで上昇し、マッハ計が1.02を超えたのだった。
その後、戦闘機の発達によって、超音速飛行はごく普通の事柄のように受け取られるようになり、民間機のコンコルドSSTがマッハ2を超え、やがてSR-71偵察機がマッハ3.3を記録した。しかし、これらの超音速機は、いずれもわずかな機数がつくられただけで短命に終わり、後継機が出ていない。長時間の超音速は、今も特殊な飛行なのである。
特に民間航空界は、2003年秋にコンコルドが最後の飛行をして以来、再び亜音速でしか飛べなくなった。文明の発展は21世紀になって後戻りしたかのようにも見える。超音速は余りにコストがかかり、環境への影響も大きい。やはり無用な贅沢というのであろうか。
しかし、人はなかなか高速移動の魅力を諦めきれない。とりわけ政府や企業の多忙な要人たちにとって、移動時間を如何に短縮するかは、仕事を進める上で重要な要素でもある。そこから今、改めて超音速ビジネスジェット(SSBJ)を希求する声が高まりつつある。
その高まりを示すのが、去る9月に開催されたNBAA(米ビジネス航空協会)総会でのSSBJの可能性を追究するシンポジウムである。アトランタの会場にはSSBJの開発研究にあたっているSAI(Supersonic Aerospace International)、ガルフストリーム、エリオン(Aerion)の3社が招かれ、研究の現状や将来への考え方について講演し、聴衆との間で討議が行なわれた。以下、そのもようをご紹介しよう。

NBAAの壇上に並ぶSSBJ関連の各社代表
スカンクワークスで開発
最初に登壇したのはSAIの代表であった。同社はQSST(Quiet Supersonic Transport)と呼ぶプロジェクトを進めている。会社の設立は2000年。翌年からロッキード・マーチン社のスカンクワークスに、ソニックブームの少ない静かな超音速飛行の可能性について研究を依頼し、その実用化に向けて作業を進めてきた。
基本的な考え方は、航空機の形状を空力的に洗練してソニックブームの発生を軽減するというもの。たとえば機首の曲面を非対称にしたり、自然層流翼を採用したり、尾翼を逆V字形にするなどの方法によって、ソニックブームの強さをコンコルドの1%以下に抑えこむことに成功した。また離着陸時の騒音や大気汚染についても、同機は米連邦航空局(FAA)の今の基準に適合する。
飛行性能は巡航速度マッハ1.6〜1.8で、航続7,000km以上。機内は乗客8〜12人乗り。天井も高くて、通常のビジネスジェットに劣らぬ快適なキャビンになる。これで、たとえばシカゴからパリまで、今のビジネスジェットで8.8時間かかるところを半分以下の4.2時間で飛ぶ。またニューヨークに近いビジネス航空専用のティータボロ空港からロサンジェルス近郊のバンナイズ空港まで今の4.6時間を2.2時間に短縮する。
こうした研究のために最近までに費やした費用は5,000万ドル以上(約60億円)。実用化の目標は2014年。1機当りの価格は8,000万ドル(約100億円)だが、向こう15年間に多くて518機、少なくとも244機の需要があると予測している。
だが、その前途に立ちふさがる問題は米連邦航空規則(FAR)である。FAR91.817によって、米国内上空の超音速飛行が禁止されているのだ。対象は民間機だけだが、これではSSBJが実現しても、アメリカの企業にとって効果は半減もしくはそれ以下になるであろう。
それに対してSAIは、この規則は1970年、いまから30年以上も前にできた時代遅れの代物にすぎない。30年間の航空技術の進歩は、ソニックブームの少ない静かな超音速飛行を可能にした。今後は一定の限度を定め、QSSTのように軽微な音しか出さない超音速機については陸地上空の飛行を認めるよう法規を改正すべきだ。もはや法規をもって超音速飛行を禁止する根拠はなくなったと主張した。
そのことを前提に、同社は2008年から実機の予備設計に着手、1年半かけて仕様を固め、装備品やソフトウェアの詳細設計に入り、評価試験のための機体を試作、型式証明の承認申請を提出するなどの作業を進めることにしている。
そして2010年からは細部設計につづいて機体の製造に着手、3機の試験機を製造し、4年間をかけてFAAおよび欧州JAAの型式証明を取得したいと語った。

QSST
F15で超音速実験
続いてガルフストリーム社が登壇した。その構想は「静かな超音速ジェット」(QSJ)と呼ばれるもので、全体の形状をウィングボディとし、空気取入れ口や排気ノズルに手を加えて有害抵抗を減らし、ソニックブームを軽減するというもの。
比較のために、同社最大のビジネスジェットG550は最大離陸重量41,270kg。乗客8人を乗せてマッハ0.80で飛び、12,500kmの航続性能を持つ。それに対してQSJは最大離陸重量45,360kgとやや大きく、乗客は同じ8人乗り。速度は2倍以上のマッハ1.80になるが、航続距離は3割減の8,800km。
むろん陸地上空を飛んでも、地上に与えるソニックブームの影響は小さい。それを実証するために、NASAと共同で2006年8月から2007年2月まで、F15を改修した実験機を使って超音速を含む32回の試験飛行をおこなった。その結果、新たに改修した部分の構造上の荷重や空力特性が予想通りであること、ソニックブーム軽減のための機首、主翼前縁、エンジン・ノズルなどの可動システムが設計通りの機能を発揮すること、また離着陸時の空港周辺に及ぼす影響も計算通りであることなどが確認された。
こうしたQSJは、たとえばニューヨークからロサンジェルスまで3時間足らず、モスクワまで5時間弱、東京へはG550で14時間余のところ9時間かからずに飛ぶことができるという。なお将来への見方としては、移動時間の短縮はこれからますます重要になってくる。したがって超音速飛行を求める声も、高まりこそすれ消えるようなことはない。米国内上空の超音速飛行も必要になるはずで、今の禁止条項は改めるべきだと結んだ。
既存の技術で超音速飛行
3番目のエリオン社は既存の技術を使って超音速飛行を実現しようという考え方。最大の特徴はエンジンで、ボーイング727、737、MD-80などに使われている大型ターボファン、プラット・アンド・ホイットニーJT8D-219の派生型を使用する。これにより米国内上空では亜音速、それ以外のところでは超音速で飛ぶ。JT8Dは11,800基が生産されているだけに信頼性も高い。推力は8,890kg×2基。エリオン機に装備して、アフタバーナを使うことなくマッハ1.6まで加速することができる。
主翼は自然層流翼。これで超音速飛行中の有害抵抗は半減する。そうするとエンジン出力も少なくてすみ、燃料消費も減る。また層流翼の採用によって離着陸時の滑走距離は今の大型ビジネスジェットと同じくらいに短縮することができる。さらに遷音速時の抵抗も減るので、マッハ1に近い速度でも燃料消費が上がることなく巡航飛行が可能となる。したがって航続距離への影響も少なく、マッハ0.9から1.6までどんな速度でも航続7,000km前後は変わらない。
層流翼は着陸進入時の飛行特性も改善する。進入速度は、機体重量の軽いときは220km/h、重いときは260km/h程度で、他の亜音速ビジネスジェットとほぼ同じ。したがって接地に際してはコンコルドのように機首を大きく上げる必要がなく、それゆえ視界を確保するために機首を折り曲げる必要もない。つまり、ごく普通の離着陸ができるわけである。
経済性は年間550時間の飛行をするとして、1.8km当りの運航費がマッハ1.5で飛んだ場合10.5ドル程度、マッハ0.95では11.5ドル程度と計算されている。同じ条件で、チャレンジャー605が9ドル程度、ガルフストリームG550が11ドル弱、グローバル・エクスプレスが約11.5ドルで、エリオン超音速機の運航費は、これらの大型ビジネスジェットとほとんど変わらない。
そこで最終的にエリオン社がめざす超音速ビジネス機とはどんなものか。速度はマッハ1.6、航続距離7,200km以上、離着陸に必要な釣り合い滑走路長1,800m以下、最大離陸重量45,000kg程度。キャビンの大きさは今のスーパーミッドサイズのビジネスジェットに匹敵する8人乗りで、亜音速でも柔軟な飛行が可能。騒音と排気ガスは現在の環境規定に適合し、経済性は今の長距離ビジネスジェットに相当する。
こうしたエリオン超音速ビジネス機はティータボロ空港から東京成田空港まで、ガルフストリームVならば無着陸で14時間21分を要するところ、途中アンカレッジに降りて1時間ほど燃料補給をしても9時間33分――3分の2の時間しかかからない。さらに東京からパリへは、途中1時間の燃料補給を含めて7時間35分。またパリからニューヨークへは、亜音速機の7時間23分がエリオン機で4時間14分になり、エリオンがニューヨークに到着しても、亜音速機の方はまだ大西洋上の真ん中あたりを飛んでいるといったことになる。
そこで、米国内上空の超音速飛行禁止の法規だが、エリオン社によれば、この改正には今後なお10年以上の実験や検討が必要であろう。議会の中にも改正の機運は出ていない。したがって当面はエリオン機のように、法律の範囲内で亜音速でも超音速でも柔軟に使い分けのできる機材が必要となる。たとえばニューヨークからロサンジェルスまで、ガルフストリームVが5時間で飛ぶところを、エリオン機がマッハ0.98で飛行すれば所要時間は4時間19分ですむ。
つまり、エリオン機は通常のビジネス機としても超音速機としても、柔軟な運航が容易にできるという結論であった。

エリオン社の構想する超音速ビジネス機
音の壁に代わる法律の壁
以上が去る9月に聴いた超音速ビジネスジェットに関する講演内容である。3社それぞれの考え方と設計仕様だが、ここでSSBJに共通する課題について整理しておこう。
ひとつは、航空機が超音速で飛ぶためにはエンジン出力が強大でなければならない。特に超音速巡航が問題となる。戦闘機が超音速飛行をするといっても、敵と遭遇した短時間だけ速度を上げればよい。これにはアフタバーナが有効だが、アフタバーナを長時間にわたって噴射しつづけるわけにはいかない。燃料もあっという間に燃え尽きてしまうだろう。したがってSSBJは、長時間の超音速飛行が続けられるようなエンジンが必要となる。逆に超音速の継続飛行が可能なSSBJが実現すれば、軍用機としても有効な活用ができるであろう。
さらに速度がマッハ2を超えると空気摩擦が大きくなって機体外板の温度が上昇し、特殊な材料を使わなくてはならない。上述のSSBJがいずれもマッハ1.6程度の巡航速度を考えているゆえんだ。
次の問題はソニックブームである。物体が超音速で移動すれば衝撃波が生じる。それは圧力の高まりに始まり、次いで減圧が生じ、もう一度急上昇して周囲に広がる。この圧力変化はエレベーターで1階と3階を行き来する程度のわずかな違いしかない。けれども瞬間的な変化なので大きな音を発する。人の耳にはドーンという鈍い音となって聞こえる。
こうした圧力の変化や音の大きさは、超音速機の大きさ、重量、形状によって、また飛行高度や大気の状態によって異なる。速度や気温や風も関係はあるが、マッハ1.3を超えると影響は小さくなる。こうしたソニックブームの軽減に最も効果があるのは、NASAの研究によれば、高度を上げること。またブームが最も強いのは飛行経路の真下で、横へそれるほど弱くなる。
いずれにせよ各社が講演で語っているように、ソニックブームの問題は理論的、技術的にほぼ解消された。にもかかわらずアメリカ政府は国内上空の超音速飛行を禁じている。音の壁に代わる「法の壁」である。超音速で飛べない超音速機は何の意味もなく、特にアメリカの企業にとっては買っても無駄ということになる。考えてみればコンコルドも、この規則のために当初78機あった注文が次々と取り消され、結局は14機しか就航できなかった。SSBJの将来も、FAAが本土上空の飛行禁止を緩和するかどうかによって決まるといえるかもしれない。
|
|
|
|
|
|
ニューヨーク〜パリ |
4:14 |
7:23 |
M1.6 |
|
パリ〜東京 |
7:35 |
10:48 |
途中1時間の燃料補給 |
|
東京〜ニューヨーク |
9:33 |
14:21 |
途中1時間の燃料補給 |
|
ニューヨーク〜ロサンジェルス |
2:12 |
4:36 |
M1.8 |
|
〃 |
3:52 |
5:00 |
M1.1 |
|
〃 |
4:19 |
5:00 |
M0.98 |
|
ニューヨーク〜マイアミ |
1:33 |
2:27 |
M1.6 |
|
シカゴ〜ローマ |
4:12 |
8:48 |
M1.8 |
|
ロンドン〜ドバイ |
4:55 |
6:40 |
M1.1 |
|
パリ〜アブダビ |
2:54 |
6:06 |
M1.8 |
超音速ビジネス機の必要性
次の問題はSSBJを誰がつくるのか。おそらく莫大なコストがかかるだろうから、どのメーカーもおいそれと手を出すわけにはゆかない。上の3社も開発研究はしているものの、自分だけで製造や販売をするつもりはない。これまでの研究の成果をどこか大きなメーカーに譲渡するか、共同で製造することになろう。
見わたしたところ、フランスのダッソー社は超音速ビジネス機の製造に最適のメーカーかもしれない。これまで多数の超音速戦闘機をつくってきたし、一方で大型高速のビジネスジェットを製造している。だが同社によれば、問題は技術よりも需要である。SSBJは開発費がかかる割に、それほど多くの需要は望めないと見ている。
では将来、どのくらいの需要があるのだろうか。講演の中でも各社の予測が出ていたが、ほかにマサチュセッツ工科大学(MIT)は、価格8,000万ドルとして10年間に300機と見る。
さらに航空コンサルタントのティール・グループは2010〜30年の20年間に512機の需要を見こむ。もっとも、これはごく控えめな数字で、最大900機まで考えられる。いずれにせよ最終的にSSBJは実現すると彼らはいう。この見方には、ボンバルディア社も支持を表明している。ただし同社は今のところ、SSBJに関する具体的な動きは見せていない。それというのも先行きが見えないからである。そこでSSBJに関して今最も必要なことはFAAが法律上のロードマップを明確に示すことであろう。将来への道筋がはっきりすれば、それに向かって具体的な計画を立てることもできる。
政治、経済の活動が地球規模で行なわれるようになった現在、それにたずさわる要人たちが地球規模で飛び回るのは当然のことだ。それには少しでも速い移動手段が望ましいわけで、SSBJの必要性はそこから生まれる。
SSBJの将来は、アメリカ政府が本土上空の飛行禁止を緩和するかどうか、実際に登場してくるSSBJのソニックブームが技術的にどこまで軽減されるか、どれほど安く実用機を製造できるか――この3要素によって決まるであろう。
(西川 渉、『航空ファン』2008年1月号掲載)