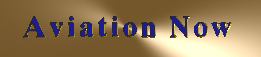<パリ航空ショー>
エアバス対ボーイング

パリ航空ショーを契機として、A350が飛んだり、787-10の開発が始まったり、どの旅客機が大きいのか小さいのか、だんだん分からなくなってきた。と思っていたら、先週の英フライト・インターナショナル誌が各機の比較表を掲載していた。分かりやすい表なので、ここに書き写しておきたい。ただし航続距離は海里をキロに直し、端数をまるめてある。

機 種 座席数 航続距離(km) 機体価格(億ドル) 787-8
250 15,000 2.07 A350-800
270 15,700 2.54 787-9
290 15,700 2.44 A350-900
314 15,000 2.88 787-10
330 13,000 2.90 A350-1000
350 15,600 3.32 777-8X
360 17,000 未定 777-9X
400 15,000 未定 747-8I
467 15,000 3.51 A380
525 15,700 4.04 この表に示すのは、キャビン通路2本のワイドボディ機である。座席数は3クラスの標準座席配置の場合を示す。その座席数の順にならべたのが上の表で、ボーイング787とエアバスA350がきちんと交互に並んでいるのが面白い。両機の競り合いぶりが充分にうかがえるというものだ。
座席数もしくは乗客数が増えると、旅客機は燃料搭載量を減らさなければならない。そのため航続距離が短くなる。この座席数と航続距離の微妙なバランスが旅客機の使い勝手を左右し、経済性つまり利益を上げたり上げられなかったりする。
米エアリース社が、787-10について問題としていたのがこの点で、787-8、787-9と客席数が増えてきたのは好いけれども、航続距離が減っては就航路線が制約され、使い勝手が悪くなり、利益を上げることもできなくなる。
ボーイング社は悩んだあげくに、787-10の航続距離を7,000海里(13,000km)まで上げることにして開発着手に踏み切った。それを見てエアリース社も先ずは30機を発注することとし、パリ航空ショーで調印したのである。
これで競合機のエアバスA350にも対抗することができる。上表に見るように、787に対してあとから出てきたA350は少しずつ大きい。その代わり機体価格は当然のことながら、787の方が少しずつ安い。
このように座席数、航続距離、機体価格が各旅客機に適した就航路線を決め、経済性を決めるといってよいであろう。

ところで、今回のパリ航空ショーで発表された旅客機の受注数は、A320、737、エムブラエルなどを合わせて1,000機を超えた。この中には予約や仮注文も含まれるが、そのうち確定受注数は666機と英フライト・インターナショナル誌が書いている。
エアバス、ボーイングの両社に絞れば、航空ショーの会場で、予約や覚え書きも含む契約調印のなされた機数がエアバス630機、ボーイング342機となった。このうちワイドボディ機はエアバス165機、ボーイング125機という。
なお、6月末までの半年間の旅客機引渡し数は、ボーイングが306機、エアバスが295機であった。ボーイングの306機の内訳は、737NGが218機、747が12機、767が12機、777が47機、787が17機。
旅客機のほかにボーイング社は軍用機として、半年間にF/A-18戦闘機を24機、F-15を3機、C-17輸送機を6機、P-8を5機、アパッチ攻撃ヘリコプターを20機、チヌーク大型ヘリコプターを17機、国防省に納入している。
(西川 渉、2013.7.6)
A350の初飛行(表紙へ戻る)