
<西川修著作集>
別々紀行(終編)
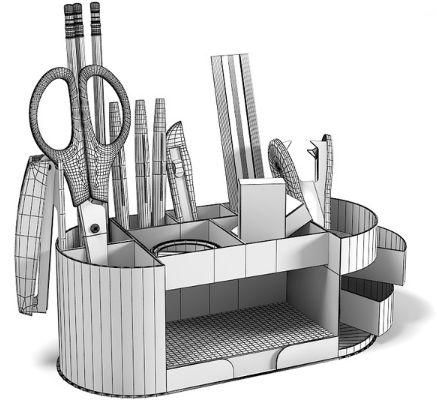

「別々紀行はまだ終わっていないようですが、あの続きをお願いできないでしょうか」編集のO嬢から催促された。しかし、当人にとっては、なかなかそう簡単に行くものではない。
一体に筆不精で、ものを書くとなると葉書一枚でも容易に決心のつかぬ男である。O嬢の毎号のお勧めにも返事だけは尋常だが、ややもすればすっぽかしてしまう。いかなる風の吹きまわしか稀に神機熟して机の前に席を定めることがある。霊感の失せないうちにとガサガサと原稿用紙を引っばり出してインキ壷のふたを取る。そこでもう霊感を妨げるような故障が起こる。インキが底の方に少ししか残っていないのである。ペンを突込むとペン先がコツコツと底につかえる感触がまことに不愉快である。これではロクなものが書けるはずがない。子供に命じて買いにやる。
……間もなく買ってくる。見ると中学生向きのコバルト色だ。これでまた感興をそがれる。ブルーブラックに買い換えさせたいのだが子供のふくれ顔を見ると、これは少し親父のわがままが過ぎるかなと思って虫を押さえることにする。次がペン先だ。これも妻君や子供が共用するので先が二つに割れたようになっていて、カサカサと引っかかる。ベン先は流れるように動いてくれないと溢れる霊感を写し取るわけに行かない。新しいのに取り替える必要がある。ところがその新しいペン先がどこに行ったかちょっとのことでは見つからない。やっと押し入れの一隅にそれらしい小さな紙函が発見される。開けて見るとクリップしか入っていないという始末だ。硯箱の中でまだ使ってないらしいのが二つ三つ見つかったが、これは既に錆びていてつかう気にもならぬ。また子供に命じて買いにやらせる。
その間、原稿用紙を前にしてぼんやり考える……。どうしても専用の書斎机が必要だ。紙でもインキでも鉛筆でも必要なものは全てきちんと一定のところに納めてあって、興至らむか机の前に駆けつけてこれらを駆使すれば、たちまた珠玉の名編が産み出されるというが如き……そうだ、まず一つそういう机の設計をする必要がある。そこで原稿用紙を裏返して書斎机の設計図を引くことになる。机の正面には小さな棚があって、ペン皿、インキ、墨汁、糊、はさみ、小刀などなどあらゆる必要品を格納する……机の両袖には必要な用紙類を分類して入れておけるように浅い引出しを散多くつける……いや、それは片袖だけにして一方はウィスキーの一本位しのばせることにしてもよいな……。
結局あまりスマートな設計ができない。何か参考になるかもしれないと思って、百科辞典を本箱から運び出して、机のそぱに積み上げる。今流行の「新しい住まい」などと名付けた住宅や台所の写真を集めた書物、そうそう、あれにも何か具合のよい家具の写真が出ているに違いない。……そこでまたその本を探しに行く。かくてものを書く気持ちは霧の如くに消え失せて、折柄バサリと玄関に放り込まれた夕刊などを読み始めておしまいということになる。子供が買ってきた新しいペン先はまたも硯箱の中に入れられてしまう。
こんな具合で文章などなかなか書けるわけのものではない。それでも短いものならまだしもで、時のはずみでどうにかできることもある。ところが、柄にない続きものなど始めると、それこそ大変である。最初はたいした意気込みで取りかかるのだけれど、一ケ月たって二回目を書く時になると、最初の企画がいかにも無意味な、浅薄な、我ながら冷汗の流れる代物だったことに気付く。しかし前回の末尾に以下次号などと書いてしまったものだから何とかしなければならない。全く興味索然お義理でこね上げることになる。三回目になるとまた違う。二ヶ月前、一ヶ月前とはさらに心境が変わっているから、今改めて前の分を繰り返し読んでみると、まるで他人が書いたように面白く読める。二回目にいやいや書いたものさえ、一回目と統けて見ると何ともいえぬ対照の妙が出ている。そうなると三回目を書くのは一層大きな負担となる。下手をするとこの一連の名作を台なしにしてしまうおそれがあるからだ。その次、第四回以下になるともうどうにもならない。勝手にふくれ上ったその「書かれたもの」は筆者の力でうまく引きまわそうとしても、最早どうして手に負えるものではない。これは既に産み出した人間の力では自由にできない別個の存在となっている。
かつて、おたまじゃくしに脳下垂体ホルモンを注射してみた学者があったそうだ。そのおたまじゃくしは蛙にならぬまま、急速に成長して間もなく鼠位の大きさになり、さらにホルモンをやったら犬位になり、さらに続けたら遂に人間を凌駕するような巨大なおたまじゃくしになってしまった。この巨大なるものは前世紀の爬虫類にも似て、いかにも無気味だったに違いない。同じ研究所の所員達はこぞってこの学者に向かってこの怪物の始末に善処せんことを要求した。しかし学者は、永の年月、心血を注いでここまで育て上げた愛着の情に堪えず、おたまじゃくしを殺すことを承知せず、遂にこの怪物を連れて研究所を去りそのまま行方知らずなりにけりという話だが、いっの間にやら膨脹してきたこの「書かれたもの」に引きずりまわされている筆者も何となくこの話に似ている。
歓楽極まった後の哀傷を思わせるように、鹿児島の学会から霧島温泉での懇親会と華やかな行事が滞りなく終わったその翌日は、朝から雲低く垂れて温泉旅館からの展望も、葉の散り果てた桜の樹や離々たる冬草に荒れた山肌など、近景のみあらわに見はるかす鹿児島湾のあたり、それかと思う桜島の姿濛気に覆われて空しく、やたらに遙かなる国へ来つると思わせるばかりであった。
矢字教授、喜田博士、それに六傘先生夫妻などの一行はそれぞれに宮崎に向かって出発した。鹿児島から宮崎への汽車はまず霧島火山の裾を巡って、いったん都城盆地に入り、さらに青井岳、鰐塚山の分ける峻険な山脈を東に貫通すると、突如、日向灘を前にして一望広々とうち開けた大淀川のデルタの上に出る。高く迫った山の間を抜けて、いきなり明けひろげた世界に出るその感じが、何か桃源郷の故事さえも思いださせるような不思議な喜びを与えてくれるのである。
矢字喜田両先生は宮崎に馴染みが深い。ことに、喜田先生は二十才台の若い頃の幾年かをこの土地で過ごしたことがあるから、感慨はひとしおであろう。その夜、若い頃に奉職していた病院を訪れて、矢字教授らと共に一タの歓を尽くした喜田博士は、尽きぬ思い出を芳醇な土地の酒に全く酔い痴れたが、翌日矢字教授らを中津に送ってから、さらに細雨の降りそそぐ大淀川の畔で、またも旧知の人と杯を含んで、懐旧の情に溺れようとしたのもまた無理のないことであった。
喜田博士がまだ宮崎で訪ねたい人があるというので、一足先に中津に向かった矢字教授と六傘先生連が、六傘先生の病院に落着いて、後を追って夜遅く到着するはずの喜田博士を心待ちにしながら話をしていると、宿直の看護婦が「今、局からの電話で、電報がきていると知らせて来ているんですが、まるで訳が分からないんです。局の方でも何のことか分からないって言うんですが、ちょっと代わって頂けないでLょうか」と言ってきた。
六傘先生が出てみると、なるほど妙な電報で、局員の方も意味の通じない電報では申し訳ないと恩っているらしい。
「はじめの所は、明日七時着くでこれは分かります。そのあとが意味がとれませんが、サラマクをヒキという句がありますが、何か御心当たりでもありませんか。……その次に臼樽がどうかしたというのがあるんですが……臼か樽に御心当たりは……そうですか……弱りました……まあ考えてみて下さい」というようなあんばいで、届いた電報は、
「アスアサ七ジツク」ヒムカノクニサラマクヲシキフルトシ
ノウスタルジヤノツキシハテネバ キタというのである。喜田博士から到着が明朝になることを知らせてきたものには違いない。そのあとに……なるほど、サラマクやウスタルが出て来る。しばらくして六傘先生は、これは短歌だろうと見当をつけて句切ってみたところ、簡単に意味が分かった。ウスタルだけはちょっと変だが、これもノスタルジヤのことだと考えついた。
翌日矢字教授と中津で再会し、一緒に別府に引き返して、また往路と同じしゃこ丸の客となって、甲板上から九州の山々に別れを惜しんでいた喜田博士のボケットの、例の小型のノートの一番新しいページには、次のような短歌めいたものが書きつけてあった。
日向の国去らまく惜しき
旧年のノスタルジアの
尽きし果てねばやがて鹿児島も宮崎も中津も別府も、国東の岬も、九州の姿はことごとく蒼茫たる海浪の彼方に没し、水平線上には残照のみが明るかった。
(南斗星、大塚薬報、1952年)
【関連頁】
別々紀行(1)(2011.9.1)
別々紀行(2)(2011.9.26)

