

去る11月29日、救急ヘリコプターの高速道路着陸訓練があるというので、朝早く起きて出かけて行った。内閣官房安全保障・危機管理室、自治省消防庁、東京消防庁など、多数の人びとが、この冬最も冷えこんだ訓練の現場に晴れやかな顔で集まってきた。おそろしく高い高速道路へ、工事用のらせん階段を怖々よじ登っていくと、快晴の眺望が遠くまで開けて、朝もやの向こうに富士山がよく見えていた。(念のために、上の写真のヘリコプターのコクピット上方に、かすかに富士山の白い頂が見えている)
関係者の晴れやかな顔というのは、多くの人が長年にわたって主張してきた高速道路でのヘリコプター救急が実現する第1歩が、今日のこの訓練だと思うからである。

高速道路の事故は、車の速度が出ているだけに、死傷の程度もひどい結果になる。ところが、いったん事故が起こると道路は渋滞する車で動けなくなり、救急車もなかなか現場へ近づけない。それならヘリコプターで行けばいいではないかとは誰しも考えることだが、どういうわけか従来ヘリコプターの現場着陸は認められなかった。
理由のひとつは建設省や道路公団の考え方であろうか。その頭の中までは知るよしもないが、高速道路は公団の私有地ということらしい。そこへヘリコプターが着陸するのは、何故か認めないというのである。
そうすると運輸省も、その場所の所有者が着陸を認めないようなところへ場外着陸の許可は出せないということになる。そのうえ許可を出すにしても、手続きに1週間も10日もかかるから、分秒を争う救急出動にとっては論外である。
さらに警察までが、高速道路の交通規制はそんなに簡単ではないと言い出す。普段は道路の補修工事で勝手気ままに規制しているわけだが、そのことからすれば人の生死よりも補修工事の方が余ほど大事なのであろう。しかも工事会社が規制しているのに、なぜ警察ができないのか。第一、事故が起れば、無理に規制しなくても自然に車は止まってしまう。
道路の構造も問題で、周囲には騒音防止のための塀がめぐらしてあったり、街路燈が立っていたり、車線の幅が狭かったりする。ヘリコプターだって、そんなところへ無理に降りて行こうというのではない。都心部のせまい首都高速はともかく、東名や関越などは道路の幅も広いし、どこまで行っても着陸できないというはずはなかろう。銀座通りだって、技術的には可能である。
既成の構造から着陸は無理というのではなく、これからつくる道路は、たとえば夜間照明は路面近く低い位置につけるとか、もっと数を減らすなどの工夫をすべきであろう。また既成の道路も何百メートルおきか、ところどころの電柱をなくすなどの補修をすればよい。夜間の運転をする者にとって、頼りになる照明は高いところから照らす電灯ばかりではないはずである。

こんな議論はいつまでやってもきりがないが、同じような論議は今年夏にはじまったドクターヘリ検討委員会でもおこなわれた。その一部は議事録として首相官邸のウェブサイトで公表されている。
余談ながら、あの委員会の議事録がインターネットで公表されているとは知らなかった。昨日、斉藤実昭さんのウェブサイト「Rotor Wind 」を見て初めて知ったのである。 この議事録は、委員のところへは、発言者の名前入りで送られてきていたようだが、インターネットのそれは名前を外してある。いずれにせよ、役所の情報公開の一環ということで、大いに歓迎したい。
今回の高速道路着陸訓練が無駄に終わることなく、ヘリコプターによる救急が欧米同様、一日も早く日常的に行われるようになることを願ってやまない。
(西川渉、99.12.7)
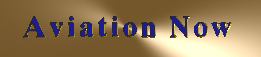 (表紙へ戻る)
(表紙へ戻る)