<スペース・シャトル>
危険の確率(2)

昨日の本頁に、スペース・シャトルの危険度に関するニューヨーク・タイムズ紙の記事をご紹介したが、今日になってNASAが今後のシャトル打ち上げは無期延期という決断をしたらしい。
さもありなんと思うのは、計算上も失敗の確率が高い上に、20年前の老朽機を使っているので、危なっかしくてしょうがないのであろう。おまけにディスカバリーが断熱タイルの剥離のために再突入できないということにでもなれば、代わりの船はどうなるのか。助け船の用意もしてなかったらしく、ロシアに頼むほかはないという。片道切符だけの特攻精神は、60年前の日本だけのものではなかったのである。

さて、昨日の本頁をウェブに送りこんだ後、押入れの中を掻き回して、タイムズの記事に出てきたリチャード・ファインマン教授(1918~88年) の著書を探し出した。いずれも昔夢中になって読んだ本で、岩波書店の発行である。
- 『ご冗談でしょう、ファインマンさんⅠ』(1986年6月)
- 『ご冗談でしょう、ファインマンさんⅡ』(1986年7月)
- 『困ります、ファインマンさん』(1988年8月)
- 『ファインマンさんベストエッセイ』(2001年3月)
このほかにも、先生は沢山の本を書いているが、物理学や重力理論などのむずかしい本は、読んでも分からない。しかし上の4冊――とりわけ最初の2冊は、とてもノーベル賞を貰った物理学者の自伝とは思えないような奇想天外な話が次々と出てくるし、大貫昌子訳の日本文も達者で、通勤電車の中で読んでいたりすると思わず吹き出しそうになって困った覚えがある。念のために、ファインマン教授のノーベル物理学賞は1965年、日本の朝永振一郎教授と同時に貰ったものである。
改めて『ファインマンさん』を読み直してみると、すっかり忘れていたのだが、最後の『ベストエッセイ』の中に、「少数派調査報告」としてチャレンジャーの事故調査の結果が全文掲載されている。それほど長くないのは、これが本文ではないからで、ファインマン先生の書いた部分は核心を突き過ぎたせいか本文に入れて貰えず、付録として綴じ込まれただけだったからである。
この調査委員会は大統領直属の特別チームであった。その発足から報告書をまとめるところまで、半年間にどんなことがあったかは『困ります』の中の「ファインマン氏、ワシントンに行く――チャレンジャー号爆発調査のいきさつ」という長文に詳述されている。
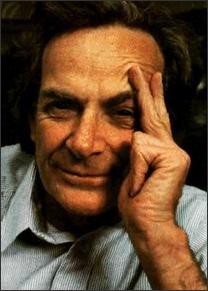
ファインマン先生――頑固そうな顔つきである。
それによると事故の直接原因となったOリングの問題を、公式の席で人びとの前に持ち出したのもファインマン先生だったらしい。それも、みんなのテーブルに配られた氷水のコップにOリングの断片をひたして、どんな結果が起こるかを誰にでも分かるようにやって見せたというのである。Oリングといっても、シャトルのそれは輪ゴムのような小さいものではない。輪の直径が3.6mもある。
この付録報告には、昨日のニューヨーク・タイムズに書いてあった失敗の確率も出てくる。ファインマン先生のはじき出したところでは「比較的不安全な状態で飛んでいる宇宙船の失敗の確率は1%台」であったという。
1%台とは100分の1から100分の2未満で、少なくとも100回に1回、多ければ101回に2回はチャレンジャーやコロンビアのような事故が起こるということだろう。当時はまだコロンビアの事故は起こっていなかったが、この事故までにシャトルは113回にわたって打ち上げられた。そして2回の事故が起こったわけだから確率は1.7%。まさしく先生の計算通りであった。
「ところが」と先生は書く。「NASAの幹部たちは失敗の確率を、その1,000分の1、すなわち100,000分の1と見積もっていた」。これは300年のあいだ毎日シャトルを打ち上げても、事故は1回しか起きないという確率である。何故そんなに甘い数字を掲げたのか。ひとつは予算の獲得のため。もうひとつは「現場で働く技術者たちとの間に信じがたいほどの意思疎通の欠如があった」からとしている。
これらの指摘が余りにきびしく核心をついていたために、ファインマン先生の報告文は、米大統領宛の報告書本文には入れられなかった。危うく抹消されるところだったが、先生も頑強に抗議して、かろうじて付録としてつけることになったというのである。
付録であろうと何であろうと、ファインマン先生の報告文書は公表されてしまった。そのうえ半年間のいきさつが詳しく、しかも面白おかしく「ワシントンに行く」に書いてあるから、すべてが白日の下にさらされた。
あとは、これらを読んで貰えばいいが、いくつか例を挙げておくと、故障の確率を膨大な計算によって出すといいながら、実際はどうも最後の答えが10万分の1になるようにエンピツをなめていたらしい。
また、飛行準備完了までの安全検査基準が徐々に下げられていったことも見つけているが、これは今回のディスカバリーの打ち上げでもおこなわれた。このことをNHKのニュースなどは「安全基準の緩和」という表現で報じていたが、これでは安全性が上がったのか下がったのかよく分からない。うっかり聞いていると良くなったように思えて、誤解を招く恐れがある。あるいは、NASAに遠慮して、わざわざそんな言い方にしたのかもしれない。
また、あの1月28日の朝、Oリングを硬化させるほど気温が低いにもかかわらず、技術陣の懸念を押し切ってまで、何故チャレンジャーを打ち上げねばならなかったのか。実は、その日の夜、レーガン大統領が年頭教書演説をすることになっていて、その中でチャレンジャーに乗っていた女の先生と交信することになっていたからという話も出てくる。
そのためにホワイトハウスから圧力がかかったかどうか、結局はっきりしなかったけれど、圧力がかからなくともNASAの幹部としてはぜひ実現したいと思っていたにちがいない。状況証拠としてはもうひとつ、女の先生をシャトルにのせるというアイディア自体、レーガンの思いつきであった。
さらに、特別委員会のメンバーはNASAのOBやメーカーの出身など、各人さまざまな方面と関係があり、知り得た事実をありのままに発言できない立場にあった。しかしファインマン先生だけは全く怖いもの知らずで、ずばずばものを言うので、最後はやっかい者扱いをされるに至ったこと、など。
こうしたことはアメリカに限ったことではない。政府の委員会なるものの実態がよく分かるし、また事故調査のあり方についても教えられるところが大きい。

その調査の結果として、ファインマン先生は付録報告の最後に次のように書いている。
「ここで勧告したいことは、NASAの幹部たちが今後、現実にしっかりと目をむけ、シャトルの技術上の弱点と不完全さを十分理解し、それを積極的に除去する努力をすることである。……そして実現可能な飛行計画のみ、かつ遂行の可能性あるスケジュールのみを提案すべきである」
19年前の勧告がそのまま、今のディスカバリー問題に当てはまるではないか。
【関連頁】
![]() 危険の確率(2005.7.28)
危険の確率(2005.7.28)
![]() 少数派調査報告「シャトルの信頼性に関する個人的見解」(R.P.ファインマン)
少数派調査報告「シャトルの信頼性に関する個人的見解」(R.P.ファインマン)

(西川 渉、2005.7.29)
